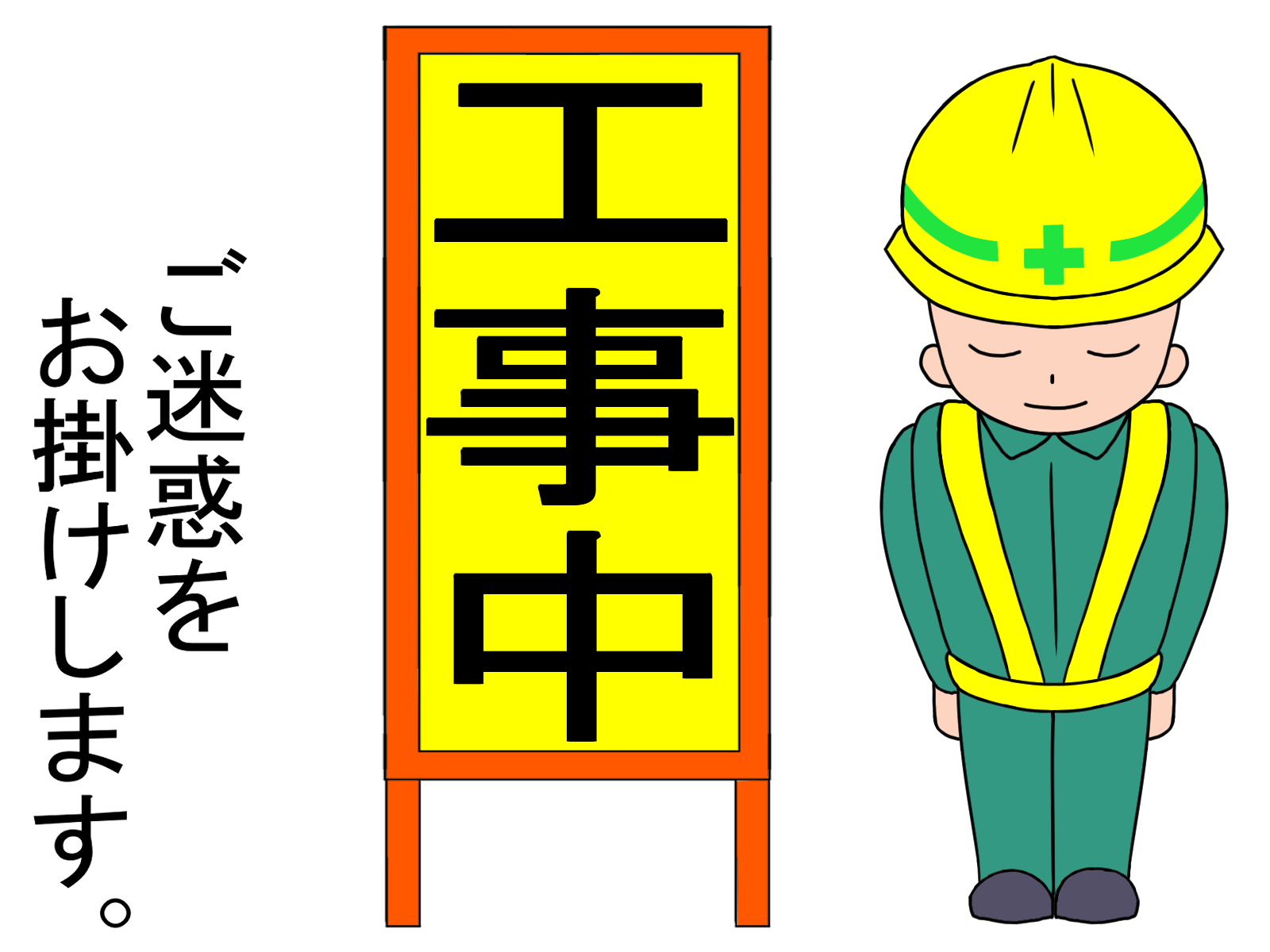――ここからは監督の仕事歴を、時系列で追ってお話を伺いたいと思います。監督がテレビで最初期に手がけた『泣いてたまるか』(1966年)などは、今では考えられない豪華なスタッフで作られていたわけですが、監督は国際放映から参加されていたわけです。監督はその頃、新東宝から国際放映へ移られたばかりですが、監督の中では本編(映画)とテレビは、どのような違いを感じてられましたか。

山際 まったくね、本編だからとか、テレビだからとか違いはなかったですね。『泣いてたまるか』は、ほぼ『コメットさん』と平行した作品だったんだけど、どちらかというと『コメットさん』をたくさんやって、僕は子ども向けの30分番組というそれの作り方をほぼ覚えたと時期でしたね。橋本さんとやっているとね、ほかの人(脚本家)達が、30分物なら200文字原稿用紙で80枚くらい(脚本)を書いてくるんだけど、僕はね、100枚はなくちゃいけないと。シナリオはむしろ長く書いてもらって、詰め込む作り方をして、30分物でもね、ちゃんと起承転結があるというね、作り方みたいなものを覚えたんですよ。だからその前の『泣いてたまるか』なんかは僕は、テレビ用という作劇をわざと意識しないで作っていました。
――短編映画の手法で撮られていたわけですね。
山際 まぁそうですね。『泣いてたまるか』っていうのは渥美清さんが主人公で、多くの監督が渥美清の良さを出すために『男はつらいよ』(1968年)に続く流れでペーソスに行ったのね。どっちかというとチャップリン的な、泣き笑い的なところへもっていく監督が多かったんですけど。それは結局、森繁久彌にも通ずる日本の喜劇の典型で「社会的には負け犬なんだけど、庶民の立場で本音を出して、何か強い者が来ると尻尾巻いて逃げちゃう」っていう、そういうね、情けない男っていう描き方の中に「人生とはこんなもんだ」ってのがあってね。僕はもう、そういうの大嫌いだったんですよね。同じ喜劇でも、スラップスティックコメディの方が好きだったのね。僕と真船禎さんは、渥美清でスラップスティックコメディで行こうと、二人で意気投合し、大いに盛り上がったんですよ。ところがね、渥美清って人は肺病で手術してて、体の動きがね、暴れたり出来ないんですよね。暴れたりするシーンを撮るとセットの隅ではぁはぁ息を切らしてるのね。「なんだよ、喜劇の人がそんなんじゃしょうがねぇじゃねぇか」みたいに僕は思ったわけですよ。まぁ二本撮ったんだけど、一本は『やじろべえ夫婦』で、もう一本は『僕も「逃亡者」』で。あれのプロデューサーは岩崎嘉一さんといって橋田壽賀子さんの旦那なんだけど、僕を買ってくれたんだけども、渥美清と僕は、それからはもう意見が合わなくて、喧嘩しちゃって、それからもう僕は二度と渥美清の組からは呼ばれなくなっちゃったんだよね。

――その後『コメットさん』で中心になっていかれた過程で……。
山際 テレビって物を意識しましたね。
こうして始まりました、山際永三監督インタビュー連載。
次回は、『コメットさん』の初動を伺い、その後ウルトラシリーズでコンビを組んだ、脚本家の上原正三氏についてお伺いします。「山際永三と『コメットさん』と上原正三と」さあ次回もみんなで読もう!