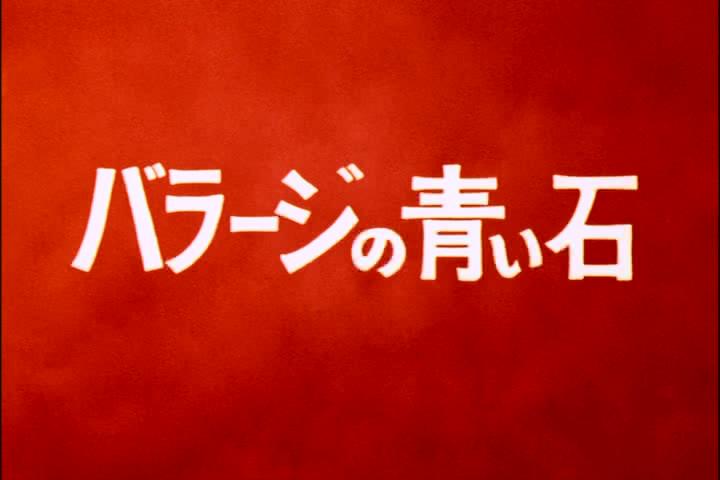一応『蘇える金狼』や『野獣死すべし』は、完全犯罪を目的とした頭脳戦という側面もあるので、そこでは展開にもちゃんと緩急がついて、頭脳戦と肉弾戦が、絶妙なバランスで配置されて物語が展開したりするのだが、この手のスパイジャンルは(書き手の志向性にもよるのだろうが)、展開のモチベーションが「受動型ミッションの達成」なものだから、どうしても、道行きが一本調子になってしまいやすい。
本作の場合はその典型で、そこには物語らしい物語も、全体構成的なストーリーテリングも何もなく、ただただ「水野が与えられた情報を元に、敵組織を追って、ポイント(それは例えば、敵スパイの住んでるマンションだったり別荘だったり、敵国が運営している銀行や教会だったり、自分の住んでるマンションだったり)に移動するたびに、そこで待ちかまえていた敵国スパイが、銃やマシンガンで襲いかかってきて、水野はそれを、撃退し皆殺しにし、生き残ったわずかな人質から情報を得るも、その人質は敵の手により粛正暗殺されて、水野は次の手がかりへとまた向かう」という、本当に、マジでこれの延々ルーティンワーク。
その合間合間に、大藪先生が書いても書いても書き飽きない(笑)自動車と銃のウンチクが延々挟み込まれているという内容。
ある意味で、この思い切りの良さとB級さは、たまらんもんがある(笑)
水野のマンションを急襲した敵スパイが、逆に水野に追いつめられた挙げ句、空からやってきた敵国ヘリコプターに、マンションのベランダから救出されるくだりなど、もはやそこには、リアリティとか現実味なんてものは欠片もなく、それでも物語序盤から中盤までは、おとなしく拳銃やマシンガンで繰り広げられていた銃撃戦も、終盤クライマックスが近づくにつれて、手榴弾だのバズーカだのと、東京都内の立地条件とは、はなはだ縁遠そうな物騒な代物が飛び交うようになっていき、ついにはクライマックスでは、奥多摩ダム湖畔において、敵国家の戦車(笑)が、秘密基地(笑)から威風堂々と登場し、水野はこれを、単身バズーカ一丁で粉砕して、めでたくエンドマークになるという寸法。
大藪先生、都内で全部展開するのは無茶ですよ、と笑いたくなるが(笑)
こうまで荒唐無稽だと、さすがに清々しさを感じてしまう。
しかもその合間においては、登場する女性は全部敵国のスパイなのに、一人残らず水野の体の虜になって、水野の為に自己犠牲を惜しまず死んでいく、なんて展開を見れば分かるとおり、全編是「鬱屈した日常から解放されたい、常識社会の男性諸氏」の憂さを晴らし、気分を壮快にさせるためだけに描かれた、まさに「オトコノコのため」の娯楽なのだ。
そういう意味で考えていけば、大藪文学の代表格として数えられる『蘇える金狼』や『野獣死すべし』だって、そこにあるのは本作と同レベルにB級で低俗な(褒め言葉)「しがないサラリーマンの身としては、普段はどんな嫌な思いを受けながらも、ひたすらへーこらするしか手だてがないような、不愉快な上司やオエライさんが、その構造枠やしがらみに一切縛られない悪漢英雄の手によって、腰を抜かして醜態をさらける姿を見てみたい」的な、庶民的サラリーマン男性の欲求を、満たす要素で構築されていたわけではある。
大藪文学はそのような「俗っぽい」欲を満たす依代として、60年代から70年代の「がんばる日本のお父さん」達の「暗い顔(by大藪春彦)」を、描き続けてきたと言えるのではないだろうか。
300ページ近くのほぼ全編で、銃弾が飛び交い、手榴弾で教会が爆発し、ダイナマイトで下水道が炎上し、最後には高尾山近くの奥多摩で戦車が砲声を轟かせる。
それはもう、バスティーシュ元になった007映画も真っ青の展開で、むしろそのハチャメチャなジェットコースターアクションのエスカレートっぷりは、90年代以降の、ジョン・マクティアナン監督や、ヤン・デヴォン監督の送り出したアクション映画のイメージに近い。
もちろん、そこをして「大藪ハードボイルドアクション小説は、60年代後半には既に、ハリウッドを20年先取りしていた」等とは、映像文化と紙文化の、双方に足を突っ込んだ履歴を持つ筆者などは、軽々しくぶちあげたりはしないが、むしろ、大藪文学に何か高尚なテーマ主義を勝手に抱いている人であるなら、逆に読んでおいた方が良い一冊と言えるかもしれない。
いや、でもこの作品は女性にはお勧めはしない。
だってきっと、女性にはつまらないよこれ(笑)