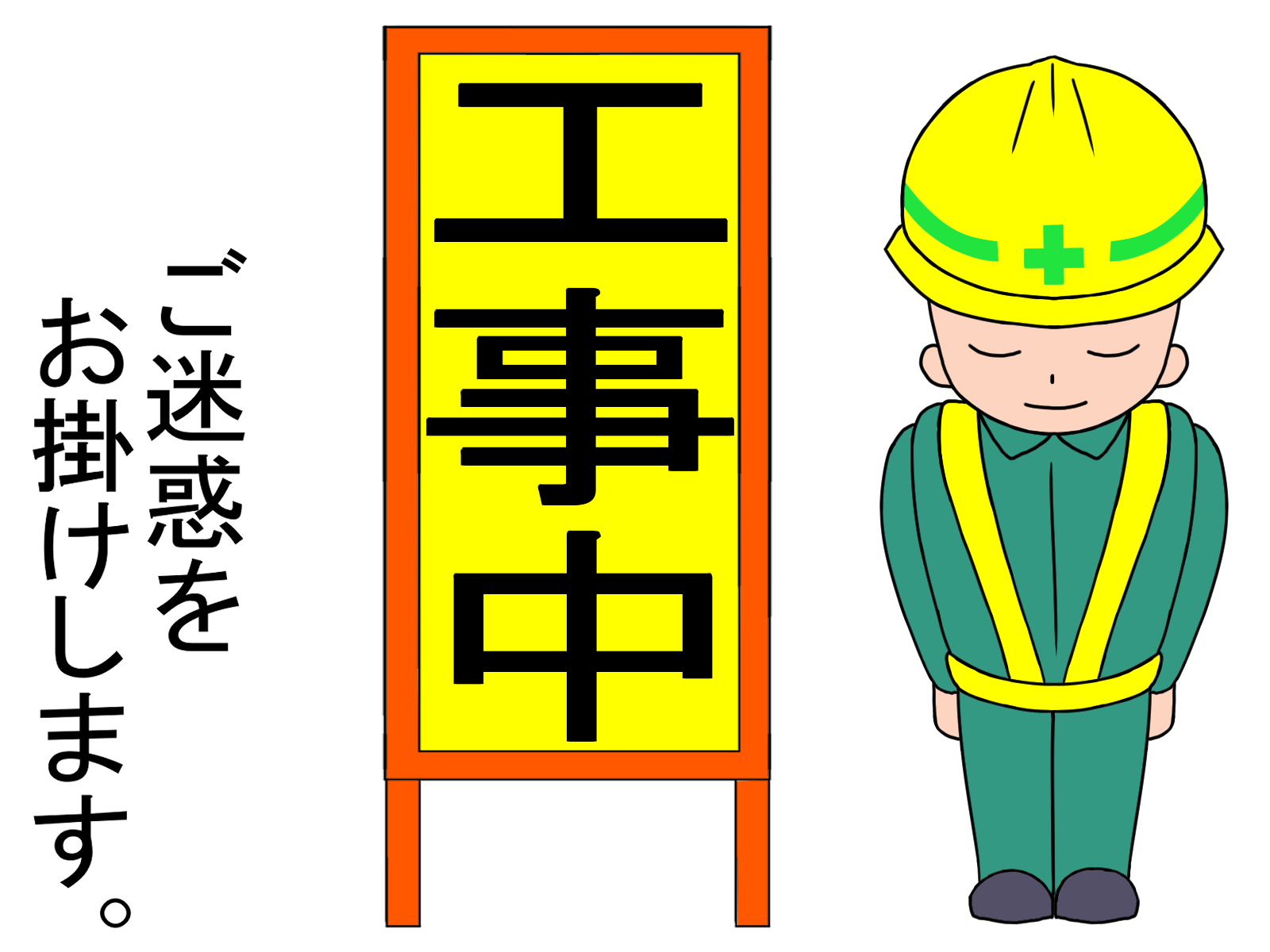――『怪奇大作戦』から『帰ってきたウルトラマン』(1971年)までの間に、円谷プロは一度、大規模リストラを行いました。それまで会社の為に尽くしたスタッフや脚本家をほとんど解雇して、改めて作品単位で契約するというリストラだったと聞きます。いろいろなジレンマゆえに沖縄に帰郷した金城氏がその後の手紙で、『円谷プロは困っていると言いながら一家は3台も外車を買っている』と書き残したりしていました。
安藤 金城氏のそれは正論ですよね。僕なんかは監督をやった期間は短いけど、この中ではやっていけないなと思ったのは、その同族意識の茶坊主ばっかりが周りに集まって……。僕に言わせりゃ、所詮お前ら監督ってガラじゃねぇだろうっていう、ね(笑) ○○、△△、□□みたいな監督ばっかが残ってるわけよ(笑) で、そいつらと同じシリーズ(の監督を)やるわけよ、もう耐えられないって!(笑)
――そういう意味では、実相寺昭雄監督なんかはちゃんと映像を分かってましたね。
安藤 そういや『第四惑星の悪夢』(『ウルトラセブン』実相寺昭雄監督作品)で、実相寺が出てるの知ってる? 体育館の射殺のシーンで、自分で出演してるんだよね(笑) 『安ちゃん、号令かけてよ!』だって(笑) それからあの時はちょうど、飯島(敏宏)さんの作品が終わって、そのあと実相寺班に続いたんだけど、円谷プロで飯島・実相寺ってのは一緒(連続)になることが多かったじゃない? 僕は両方付いてるわけだ。そうなると三人で『飯食いに行くか!』とかなるわけよ。だからTBSの(映画部解体に伴う)リストラに関しても、三人でかなり生々しい話をしてたわけだ。
――そういった戦友感覚という関係はいろいろありましたが、安藤監督にとって、円谷プロで一番気心が知れた仲間というのはどなただったんですか?
安藤 上正だよ! それはやっぱり上正だったし、あとは、僕の方はなんとも感じてなかったけど、『怪奇大作戦』で僕が撮った作品を見てた実相寺が手紙をくれてね。『お前は同士だと思ってたけど、なんでこんな凄い作品撮ったんだ!』って。僕、円谷にいて思ったけど、あそこには助監督でドラマ育ちの奴がいなかったんですよね。だからそういうことでは、多分円谷の人達にしてみたら、僕はユニークな存在だっただろうということは、今思うと感じますね。以前、ミッちゃん(上原正三氏の奥様・元円谷プロ社員)も言ってたけど、『いや安ちゃん、びっくりしたよ、円谷の皆が。あんな助監督が本当にいるのかと。いつも格好良いアロハシャツ着て入ってきて、仕事してんだかしてないんだか分かんないんだけどね』って(笑)
――市川森一氏に関して上原正三氏が書いた逸話に、似たようなエピソードがありました。そういう意味では安藤監督も市川森一氏と同じように、円谷プロという閉塞した会社にしてみたら「外の風」だったんじゃないかなと思うんです。
安藤 そうでしょうね。外の風って意味では、脚本家連中にもそう思われたらしい。まぁ、たまたま親しくしていたのは、上原正三であり若槻文三であったんだけども。で、皆書いて持ってきて、作品が完成したら、『安ちゃんどうだった? 完成品の出来は』とか言うからさ。『いや最高だよ!』って言ってね、『今までで一番良い作品だよ』とか言うわけですよ(笑) そうすると上原正三なんかはさ、『安ちゃんお前さぁ、作品の出来を聞かれたら、普通はうーんとか言って、謙譲の美徳を発揮しないか? お前みてぇに自分の作品を最高だよとか言う奴、俺は初めてだよ』ってよく言ってたよ。だからミッちゃんにも『安ちゃんって恥ずかしさとか知らないの?』って言われるからさ(笑) 恥ずかしさ知らないというよりも、与えられた条件の中で自分が撮った作品に対して僕は、いつでも最高の物だという自負があるから。聞かれりゃ『最高だよ』って、決まってんじゃないかそんなのさぁ(笑)
――これは山際永三監督にもお伺いしたことがある質問なのですが、安藤監督がそういった「普通の映画屋の感覚」を持った一人の映像作家として、「巨大な宇宙人が、巨大な怪獣を倒す」という荒唐無稽な、言ってしまえば、良識ある大人からすれば馬鹿馬鹿しい作品の世界で、そこに留まり仕事を続けてこられたモチベーションなり、理由といったものはなんだったのでしょう?
安藤 一番大きな理由というのは、とにかく映画の世界に居たいというのはあったね。そして自分が一度飛び込んだ以上は、目指した以上は、監督になるまで辞められないなっていうのが次にあったのね。そして、さっきも言ったけど、松竹以降の流れがあって円谷に行き着いて、『なんだよ、怪獣かよ』っていうのはあったよね、実際ね(笑) でも、そこで出会った人達がね、円谷一であり実相寺であり、野長瀬三摩地であり、そういう人達の仕事を見てたらね、『そうか、こういう世界でもピシッとしたドラマが描ける。じゃやってみるか。それだけの価値があるかもしれない』って思ったのね。だから、本当のこと言えば○○とか△△とか(の助監督)に付くとさ、情けない思いもあったんだよ(爆笑) ただ僕が幸せだったのは、少なくとも円谷育ちじゃないから、実力がちゃんとあった円谷一や野長瀬三摩地や、飯島、実相寺に(助監督として)ついたといった経験が、テレビドラマ作りにまだなれてなかった僕に、希望を与えてくれたっていう。これが、○○と△△だけについてたら、多分耐えられなかったと思う(笑) だからね、僕が飯島・実相寺に付いた時には、多分僕の監督昇格は決まっていたからね。ただ、特に実相寺さんはね、僕に対して同士的な感覚でいつも話してたよね。単なる部下とかっていう感覚じゃなくて、一緒にやっていく人間っていう、そういう感じでお互い話し合ってたね。年齢も一つか二つしか違わなかったし。
安藤監督の人生は、映画においては監督であり、その後の全ての時間においても「表現者」でありました。そんな安藤監督の、胸のすくインタビューも次回で最終回。「安藤達己と関正子とダヴァオと」さぁみんなで読もう!