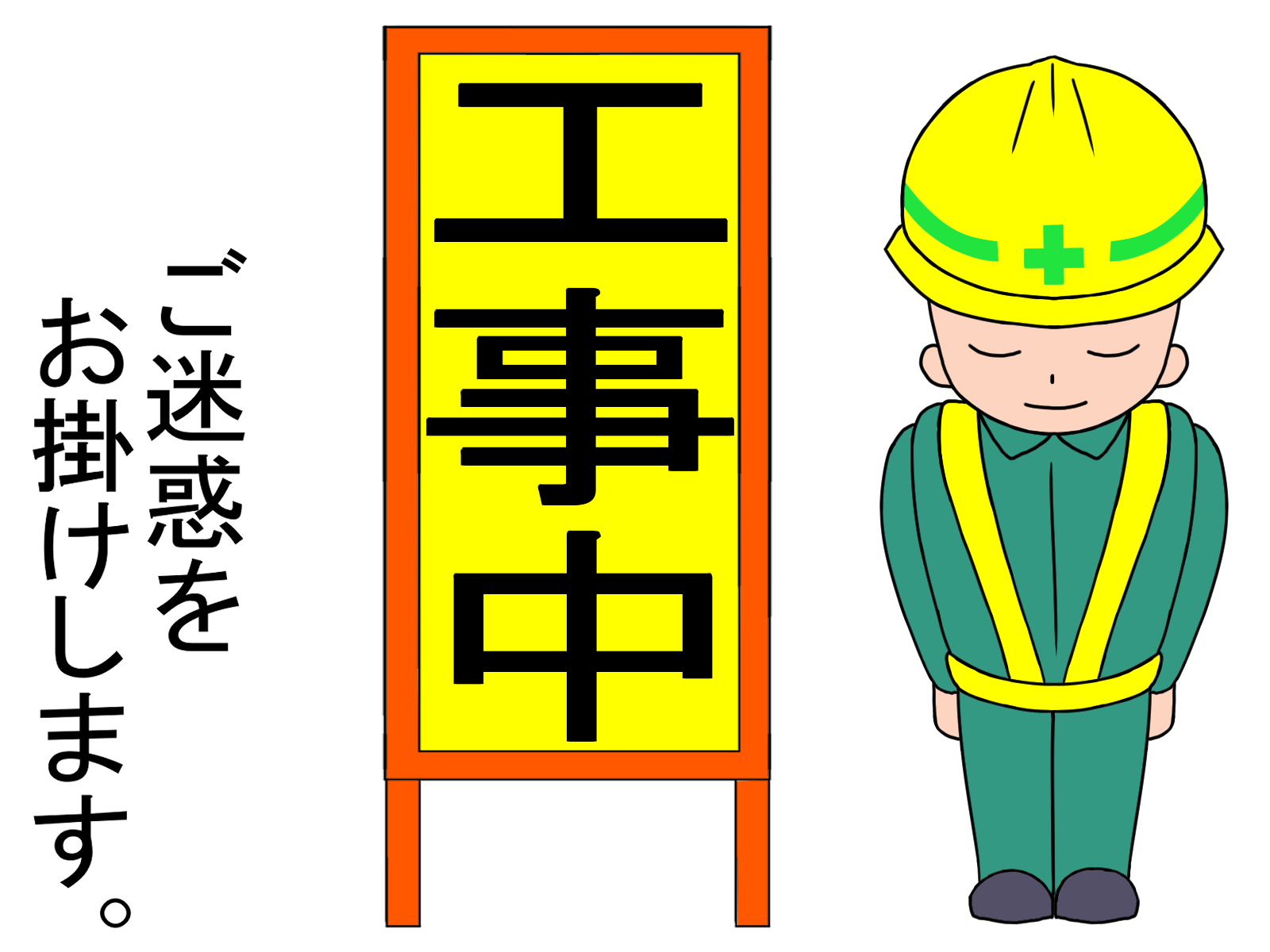『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』(1984年)
80年代を代表するラブコメ漫画として知られた、高橋留美子女史の原作大ヒット漫画を、テレビアニメ版の初期チーフディレクターでもあった押井守監督が、おそらくスクリーンを舞台に初めて「映像作家としての本性を現した」作品であろうと思われる、アニメ史にとっても、日本映画史にとっても、外すことが出来ない記念碑的な作品。
元々の原作漫画は、高橋留美子女史の女性原理で描かれていて、異星人であり異人であるヒロイン・ラムちゃんの方は、むしろ生々しく「女性」としての感情・生理曲線が描かれていたが。逆に「普通の高校生少年」でしかなかったはずの主人公・諸星あたるの側の方が、徹底した「女性視点から見える浮気男」のカリカチュア、ステレオタイプでしか描かれていなかったため、当時の筆者は、連載初動では引き込まれたが、諸星あたるの「嘘っぽさ」に嫌気がさして、早々と連載を追うのをやめた記憶がある。
同じことを、テレビアニメをディレクションしていた押井守監督が、感じていたのか、いないのか(何かのインタビューで、筆者と同じ論調を語っていたのを拝見したことがあるが)。この『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー(以下・『うる星2』)』は、押井監督がもちろん男性であるため、それまでのテレビシリーズで、リアリティの欠片もなく、ラムに惚れられつつ、疎ましがり、他の少女に片っ端からナンパを繰り返してはラムの電撃をくらい、それでもこりなかったあたるの内面の深層と、周囲を取り巻く桃源郷パラダイス(ラムにとっての)が「終わらない時間」である(それはアニメゆえだからなのだが)ことへのエクスキューズを、徹底的に追求し、自己批判し、様々な哲学や心理学を作劇に持ち込んだ結果、以下のような骨子、内容になった。
「主人公は一人の高校生の少年。その少年はなぜか、自分からは好きではなかった一人の少女に強引に振り回され、その結果、周囲を宇宙人等の、異人達が取り囲むコロニーに変化させられる。しかし、そのコロニーの変化は、実は主人公を引っ張りまわす、そのヒロインの深層心理的な願望から築かれた、そのヒロイン中心に変化創造された世界であり、その世界は、ヒロインの願うままに変化をしたり、あるべき変化を拒んだりし続け、常に中心にヒロインがいるという構造で成り立っている。しかし、やがてその謎も解け始め、登場人物達のディスカッションや情報交換等で、現状の世界そのものが『胡蝶の夢』のような条件で存在していることが主人公少年にも分かる。分かると同時に世界は崩壊へ向かいだす。それまで、ヒロインを頑なに拒んでいた主人公少年だが、世界の崩壊の危機を前に、自分の深層心理の中にも、そのヒロインへの愛情があったことを自覚し、クライマックス、主人公のヒロインへの『好きだ』という意味の告白によって世界崩壊は直前で回避され“目が覚めて”主人公たちは元の日常の世界に戻れるが、果たして、戻ったはずの世界もまた、ヒロインの望む世界構造のままであった……のかもしれない……」
『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』要約
同じである。今回もまったくして、一字一句違わぬ内容になる(註・それはコピペだから……)。
ちなみに余談ではあるが、この映画『うる星2』は、当時カルト的だった『うる星やつら』ファンの一部からは「こんなのはもう、『うる星』でもなんでもない!」と、激怒を買い付け、原作者の高橋女史も試写で「これはとても素晴らしい映画ですね。でも、私の『うる星やつら』とは関係ないアニメですね(大意)」というような旨の発言をされて、早々に席を立って去られたという逸話も、まことしやかに語られてはいる。
しかし、当初はそういった「原作原理主義」からの反発やアンチ活動によって無駄な騒動を生んだ『うる星2』も、そもそもの映像作品としての出来は、当時のアニメシーンでも抜きんで一級品であったため、一過性の『うる星』ブームが収束し終わった後の時代においても、むしろ『うる星2』だけは、一本の映画作品として、語り継がれるようになったというのは(その後の押井ブランド映画『機動警察パトレイバー2 The movie』(1993年)や『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)との、テーマ的連結性が見られたからか)、これはやはり、娯楽や文化で最後に生き残る要素は「普遍性」であることの証明であると思われる。
仮に、『うる星2』と『ハルヒ』の相似形に、なんらかの連結性を抽出しようと思ったとして、『ハルヒ』の作者・谷川流氏が1970年生まれであることを考えると、谷川氏が仮に『うる星2』を観たとしたら、劇場でなら14歳、ビデオ版でなら高校生以降ということになり、一番多感な思春期に観たことになり、そこでのめり込むように『うる星2』に入れ込んで、心酔しきっていたとしても、不思議はない年齢。
併せて、ライトノベルというメディアが『ハルヒ』出版のこの時期の前後から、爆発的な広がりと市場の拡大をもたらしていった中では、パロディとパスティーシュとオマージュとパクリが、区別なく「ファンと読者をつなぐ大事な要素」扱いをされていたという、いささかリテラシー的に問題がある構造も表層化しつつあった時代でもあって(その辺りは、ガイナックスの全てのアニメ群や、笹本祐一氏の『ARIEL』、等の前例もあるのではあるが、多分送り出す側の出版社や編集サイドも、その膨大な作品群の、完璧なチェックを行えずにいただろうことも想像に難くない。
いや、ここまでをして、筆者は別に谷川氏が、悪意や常識の欠落で『うる星2』をパクった、模倣したとは思ってはいないことは断言しよう。『ハルヒ』の出来やアニメのクオリティに敬意を表するなら、むしろ『ハルヒ』は谷川氏による「『うる星2』を愛しすぎたあまりの、自身の創造による、再構築と再検証」であり、『ハルヒ』自体が、作品という形での「『うる星2』批評としても、読めるところが面白い」という主旨のことが書きたいのだ。
これは、アニメ側も確信犯だなぁと思うのは、例えば『ハルヒ』で、ハルヒの存在と世界の構造論を、インテリ超能力少年が、主人公少年に語り解く時が、わざわざ「タクシーの後部座席で、延々と長台詞の会話」であるところなど、『うる星2』でも、あたると面堂終太郎が(面堂家御用車で)同じことをやっていたし、押井監督の初商業用実写映画『紅い眼鏡』(1987年)でも、タクシーでタクシー運転手と主人公の間で同じシチュエーションが展開されるし、押井監督自らが「哲学的な会話を、動く密室の中でする描写が好き」と言っているように、そのリフレインは『機動警察パトレイバー2 The movie』でも展開され、この時期既に「押井作品の定番演出」として、アニメファンには広く認知されていた。「タクシー後部座席の会話」は原作『ハルヒ』にも登場するが、そもそも「そのシーン演出」は、文字では簡単だが、動く映像にするにはすごく難しい。そこでの「会話があるが、映像は窓の外の景色だけ」とかの映像技法が、京アニの『ハルヒ』の該当シーンでは、見事に『うる星2』のパスティーシュとして成り立っていた。
また、『うる星2』は、「何度でも『学園祭前夜』という一日が、ループし続ける」が基本骨子なのだが、『ハルヒ』では、『うる星2』へのオマージュなのか、それとも学園物の定番ネタなのか、やはり学園祭がネタになる話があるのだが、それを扱ったアニメ版第12話『ライブアライブ』劇中で、主人公達がぞろぞろと学園内で歩くシーンで、背景に『純喫茶 第三帝国』なる張り紙が貼られてあったが、この「純喫茶 第三帝国」は、『うる星2』でそもそも、ラムやあたる達2年4組が、文化祭で出店する出し物の喫茶店の名前であり、つまり『ハルヒ』サイドは最初から、自分達の作品が、『うる星2』の影響下にあることを、隠してなどいなかったのである!