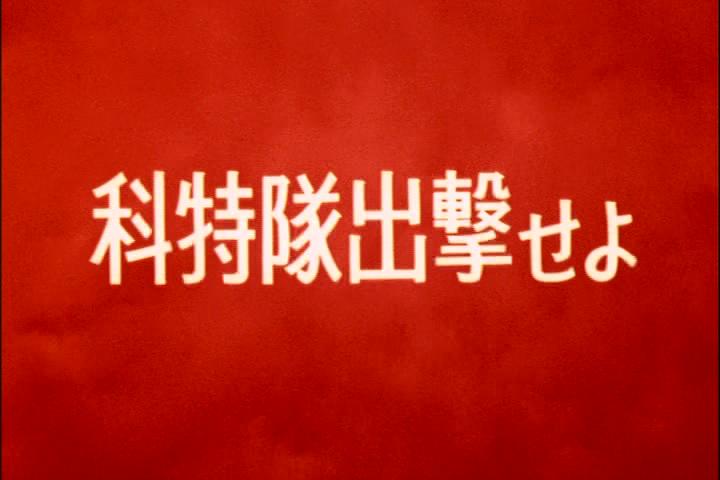木村ゴローは、自分を取り巻く世界全てを唾棄し、孤独を求めて故郷の街にたどり着いた。
そしてネムと出会った。
ネムは、あえて才能を見出してくれた売れっ子少女漫画家からの誘いを拒否して、ゴローが差し出し続ける手をつかもうとする。
各話、構図にかなりの意欲的な試行錯誤が観られ、俯瞰や煽りを積極的に取り入れることで、漫画を読む者の視線誘導に、主人公の不安定感を植え付ける高度さは、木崎氏の天才ぶりが伺えた。また、漫画デジタル化時代前夜であるというのもあってか、スクリーントーンを一切使用しない原稿の仕上がりも、この漫画の「儚さ」を表現する力にもなっている。
“それ”は、狩撫氏の「怒り」も表現してみせていた。
中盤、ゴローになんとしてでも連載をと、おしかけにくる「某出版社の編集」が登場するのだが、劇中では「河村」と名乗るが、それはどう見ても(というか、それなりの時代と状況の知識がないと気付かないが)この作品が掲載されていた、月刊コミックビーム(当時アスキー出版)の編集長、奥村勝彦氏をモデルにしており、確かにこの時期、IT企業だったアスキーが、ゲームバブルで売り上げ好調だった雑誌『ファミコン通信』編集部をスピンオフさせての、漫画雑誌立ち上げの『月刊コミックビーム』だったわけだが。
なにぶん、漫画編集のノウハウを社内に持たないアスキーが、ファミ通時代からのエース漫画家・桜玉吉氏以外の漫画連載と雑誌自体をプロデュースできるはずもなく、かつて秋田書店で、伝説の編集者と呼ばれた壁村耐三氏の「最期の弟子」とも呼ばれる存在である奥村氏を、ヘッドハンティングして漫画界に新風を巻き起こさんとしていたのが、まぎれもない90年代から2000年代にかけてのコミックビームであったのだ。
しかし「奥村氏の鏡像」と別れたゴローに、狩撫氏は「河村」についてこう言わせる。
「あいつ、今は新雑誌創刊で燃えてるが、そのうち会社から尻たたかれて、善悪の判断もつかねえようなマンガ家連中が描く“売れ線”にしか、興味を示さなくなる典型的なタイプだ」
『少女・ネム』より
ただ、誤解してはならないのは、この台詞がまんま狩撫氏による、奥村氏評ではないということ。むしろ「悪役」を出すにあたって、わざと掲載雑誌の顔(先ほども少し書いたが、この時期奥村氏は、名物編集長として、桜玉吉『防衛漫玉日記』や須藤真澄氏『おさんぽ大王』等のエッセイ漫画連載に、頻繁に登場していた)を共犯関係として漫画に刻み込んだ、つまり奥村氏は、上で引用した狩撫氏による「イマドキの漫画編集観」と同じ危機感を抱いた同志であるという解析がここで成り立つのである。
そんなネムと、そんなゴロー。
共に歩く。
共に食事をする。
共に同じ景色を見る。
“その先”で、ネムは初めて、ゴローに自我をぶつける
「結局見せられなかったな。編集長にお前の……キミの“作品”を……」
『少女・ネム』より
「……ネムです。おまえ、じゃなくて、キミ、じゃなくて、あたしの名前は……」
「わ……わかった」
ネムの「儚い魂」は、まるで中島みゆきの『銀の龍の背に乗って』の歌詞のように、ゴローをして「ヒナ鳥だ」と突き刺さる。