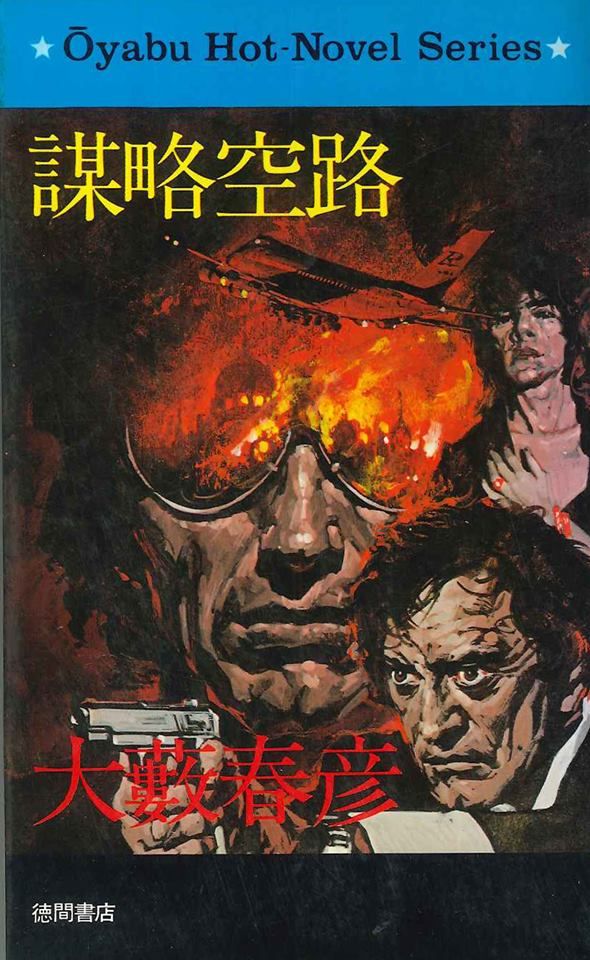その兆候は70年代から既に、伝説の写真集『少女アリス』などに見られていたが、70年代までのロリコン文化は、オタク的なる漫画・アニメ的な趣向とはあまりリンクが見られず、よくいえば文学的でもあり、悪く言えば生々しい作品が多かった(1973年に、沢渡朔氏撮影によって制作された『少女アリス』には、谷川俊太郎氏が詩を添えている)。
70年代までの、ロリコンの創世記までの時期における「少女性」は、どんな形で表現に結実していたのか。そこを読み解いていくと、80年代以降のロリコンブームが、今回冒頭で記した、『ゴジラ』シリーズや『男はつらいよ』シリーズの末期のように、如何に表層的に解体され、無意味化してしまった即物的商売であったが分かってくる。
70年代初頭までは、表現への批評や評論は、批評元になる作品と対等な「表現」であった。それは、当時、佐藤重臣氏が編集長を務めていた『映画評論』などでの映画批評などにも顕著である。佐藤氏は、大島渚監督とも懇意ではあったが、同誌での(大島渚監督が主導権を握っていた)松竹ヌーベルバーグ運動に関する評論において、互いに激しく揉めた事案があった。
一方で、先ほど名前を挙げた、ハリウッドの傑作映画『2001年宇宙の旅』も、実はこれは、当時世界中を議論の渦に巻き込んでいた、カナダの社会学者Herbert Marshall McLuhanが、1964年に発表した『メディア論―人間の拡張の諸相』(原題:Understanding Media: The Extensions of Man)と、そのブームへの、反論立証的な意味合いを持った映画であったことは、当時を知る者の間では常識である。
これらは、70年代序盤までの顕著な事例であって、70年代もその中盤からは、大衆や市場達は、その図式に疲れ始めてしまうのである。
その時期、日本だけではなく、世界中が疲れ始めていた。継続する朝鮮戦争、ベトナム戦争、そしてそれに伴う冷戦の緊張感。それらを支持する右派も、それらを打倒しようとする左派も、双方とも泥沼の消耗戦で体力を使い果たしあっており、互いに逡巡を抱え、現実の醜さ、汚さ、複雑な構造と、向き合い続けることに、疲れはじめていた。
「社会の、表も裏も見てしまい、汚れてしまった大人には、社会を何一つ救済することも、改革することも、守ることもできない」
当時の大人達が、そこまで具体的に考えていたのかどうかまでは、筆者にはうかがい知れない。しかし、70年代序盤、70年安保騒動を過ぎた辺りから蔓延しだした「敗北感」が、社会を包み込み始めたのは確かだ。言い切ってしまえば、70年代中盤を席巻した「終末ブーム(『日本沈没』『ノストラダムスの大予言』等)」は、明確な敗北感の結実であり、エクソシスト・UFO・ムー大陸・超能力(念力)などのオカルトブームは、現実逃避の日常への浸食化であり、ブルース・リー映画ブームなどは、致命的かつ屈辱的な敗北からくる「もっと強さを、という渇望感」の現れであるとも言えた。
そして「大人」達は、作品と評論を、拮抗させ合う表現バランスに保つことを手放し、それが最終的には80年代以降どこへ行きつくのかは、本論の後半に譲るが、まずは自分達が汚しきってしまった「世界」の浄化を、まだ社会で汚れに手を染めていないだろう「少女」に求め始めたというくだりから、本論は語らねばならない。
その片鱗が、日本文化では、前述した少女写真集『少女アリス』の発刊であろうし、同時期の大島渚監督の松竹ヌーベルバーグ映画『夏の妹』(1972年)でもあったであろう。

『夏の妹』のヒロイン・スータンは、幼女でこそないものの、劇中では「日本と米国という、腐れきった二つの大国に翻弄され、蹂躙される、イノセンスな沖縄」のメタファーとして描写され、天真爛漫で純真無垢なその少女性は、大島監督が、あえて「アイドル映画」に偽装して制作したスタンスも併せ見ることによって、「聖少女への、最後の希望」の発端が見えてくる。
その『夏の妹』で脚本を担当した佐々木守氏と盟友関係にあった、同じく脚本家の内田栄一氏は、その直後にこちらは藤田敏八監督と組んで、そのタイトルもそのままに『妹』という映画を1974年に送り出すのであるが、少し興味深いのは、ここで共通ワードとして使われている「妹」という概念が、佐々木氏と内田氏で、かなり重なり合う部分があるだけではなく、これから語り着こうとする(80年代の)「ロリコンブーム」の先にある、2000年代以降の「ポストロリコンブーム」の象徴でもあった「妹萌え」という現象とも繋がるということである。
もちろん、70年代の聖少女性や妹性崇拝と、近代の「ロリコン」「妹萌え」は、全く異なる主旨と価値を持つという前提で、この論を進めるのではあるが。