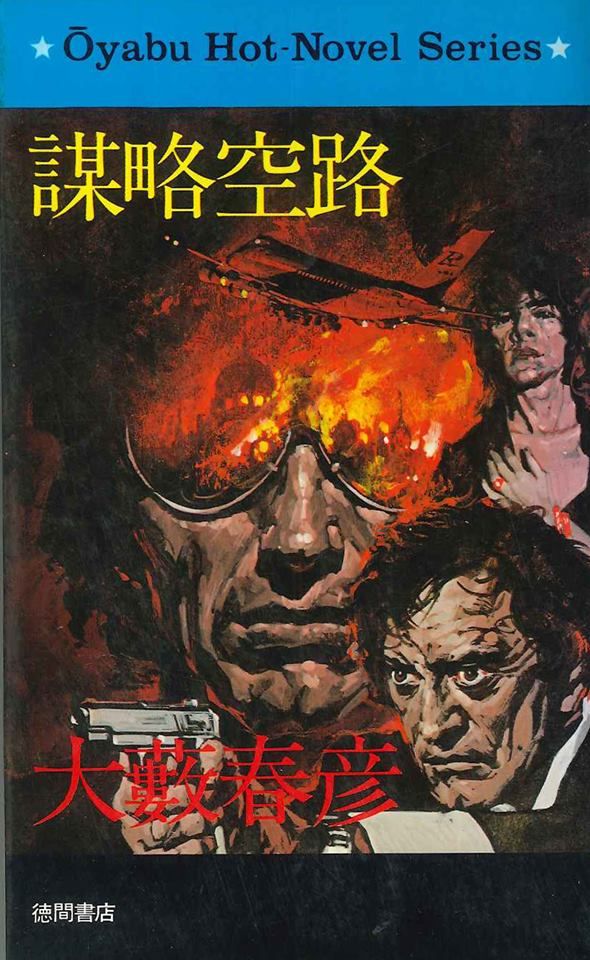さて、やはり70年代初期、写真家の篠山紀信氏が、雑誌『GORO』に、13歳の少女のヌード写真を掲げて社会問題に紛糾しそうになる直前期。
こちらも社会派の作家・野坂昭如氏が、歌手として「バージンブルース」という曲を発表して話題をさらった時期があった。「日の丸弁当ぶらさげて どこへいくのか ギンギラギン あなたもバージン あたしもバージン バージンブルース」と歌った野坂氏の、その歌詞の持つ衝撃性も強かったが、その曲もまた、歌謡映画として、内田栄一氏と藤田敏八監督(そしてヒロイン役も、『妹』に続いて秋吉久美子氏)によって映画化されている。
その『バージンブルース』(1974年)劇中で、内田氏は主人公の中年男性に「俺はバージンを守る義務があるんだ」と言わせている。ここまでくれば、彼らが表現に用いた「妹」がなんであって、その存在を取り囲む大人たちがなんであるかは、もはや明確だろう。
イデオロギー的にテンプレートで読み解くのであれば、中年男性と男性主権社会は、父権社会の象徴であり、それは「天皇陛下という父の下で、集い形成される、天皇制社会」言い換えるなら、戦前日本社会の象徴である。そして、そこでの女性は、天皇制によって蹂躙された、卑弥呼以下邪馬台国を当てはめてもよいし、男尊女卑の象徴として、日本原住民族やマイノリティをメタ的に背負わされることもある。
では、この場合「まだ社会に染まり切っていない少女」「守られ、育てられるべき妹」とは、それは果たして、佐々木守氏や内田栄一氏や野坂昭如氏(「そこ」に、『少女アリス』に詩を寄稿した谷川俊太郎氏を混ぜてもいいかもしれない)が、あの猛暑の8月15日に、玉音放送と入れ違いに夢に見た「本当の戦後民主主義」への想いの象徴であったのだとは、言えないだろうか?
一方「バージンブルース」を歌った野坂氏の、作家としての代表作を問われれば、いまやジブリアニメの影響で、誰もが知るところとなった『火垂るの墓』であろう。
この作品も、戦争という国家と社会の残虐行為に、翻弄されて命を散らしていくことになる「幼い妹」を、なんとか救おうとして救えなかった、一人の少年の物語であった。その『火垂るの墓』の核の部分について、独文学者でもあり評論家でもある種村季弘氏は、1991年に『映画芸術』誌の『小川徹の妹さがし』なる文章でこう言及した。
ずばりいってしまおう。妹を探している。妹がいなくなってしまったのだ。ある世代に宿痾のように取り憑いてしまった喪失感を、とりあえずそういっておくしかない。三島由紀夫から野坂昭如にいたるまで例外ではない。実際に妹がいようがいまいが、それはどうでもいい。夭折や戦災死をしようがしまいが、それもどうでもいい。はじめから妹なんかいなかった、のだっていい。妹がいなくなってしまった、という表現でしかいいあらわせない。ある種の喪失感を抱えこんで数十年を生きてあるきまわった男がいる、ということをいいたいのである。
種村季弘 『小川徹の妹さがし』
戦後のインテリ、文化人にとって、「少女性の象徴としての妹」が、どう喪失感に見舞われて錯綜していたのかが、端的に現されている文章である。
前述の佐々木守氏は1968年のTVドラマ『怪奇大作戦』(1968年)『死神の子守歌』でも、不治の原爆症で死にゆく妹を、なんとか助けようとして、連続殺人を犯す科学者の青年を描いた。ここでもイノセンスな「妹」は、残虐な「戦争という現実」によって、罪無く命を奪われるだけの被害者であった。
大島渚、佐々木守、藤田敏八、内田栄一、篠山紀信、野坂昭如をはじめとして、70年安保に敗れ去ったインテリたちは、妹という存在の少女を探し、求め、そして決してその手を掴めないまま終わる「セカイ」を、描く方向へシフトしていった。