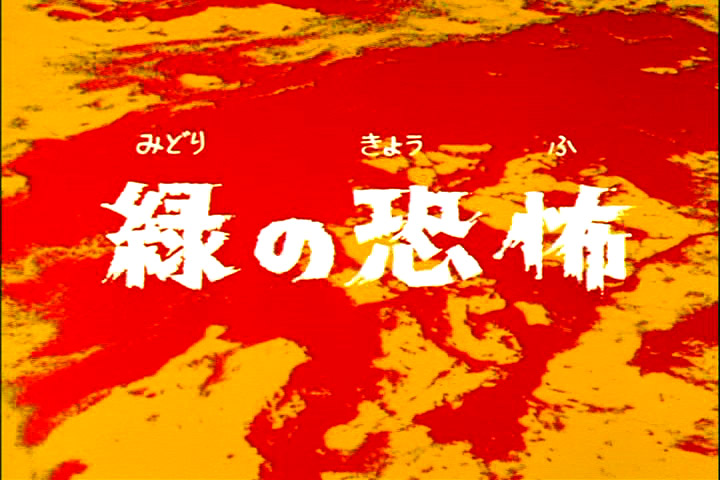だが『侍ジャイアンツ』と『野球狂の詩』、そこに面白い存在の共存を見ることも可能だ。
『侍ジャイアンツ』は、読売巨人軍の漫画化権を、『巨人の星』の講談社から、当時まだ弱小少年週刊漫画雑誌だった集英社の『週刊少年ジャンプ』が買い取って始めた連載だ(余談だが、なので梶原巨人漫画史では、『巨人の星』の星飛雄馬引退の年と、『侍ジャイアンツ』番場蛮ドラフト指名の年は同じなのだ)。
なので当然「巨人軍公式漫画」の『侍ジャイアンツ』は、巨人を中心に描かれ、主役は巨人に在籍し、展開する試合もほぼ全てが巨人戦であることは当たり前になる。
一方『野球狂の詩』は、そこでセ・リーグの架空の球団「東京メッツ」を主人公に設定。かといって巨人の存在が抹消されたわけではないが、そこで水島氏のアンチ巨人精神が働いたからなのか、巨人漫画化権の問題からなのか、『野球狂の詩』では巨人というチーム自体の出番が殆どなく、僅かに長嶋茂雄にあこがれた男等のエピソードがあるだけで、メッツと巨人の試合も、殆ど描かれなかった。
当時の漫画読みの中では、このような偏りの両極の中で、『侍ジャイアンツ』と『野球狂の詩』が、同じ世界に存在したという夢想も可能であった。
数奇な一致も山ほどある。
『侍ジャイアンツ』は1971年のオフシーズン、『野球狂の詩』は1972のシーズン中から、つまり野球シーズンとしては同じ年から始まっているのだ。
その上で、当初は双方とも「魔球漫画ではなかった」。
方や荒くれサムライのアバンギャルドで破天荒な常識を破った活躍の数々、方や50歳を超える老人ピッチャーを主軸にした、一話完結一人の野球人を主役にしたアンソロジー。どちらも『巨人の星』の逆を行く野球漫画としてはじまるが、最終的にはどちらも魔球漫画に帰結する。
「そこ」には、敵対するイデーの漫画家同士が描いたとは思えない、奇妙で数奇な一致も存在するのだ。
『侍ジャイアンツ』主人公の番場蛮と、『野球狂の詩』後期主人公の水原勇気。ともに「少年で小柄なチビ」と「女性」という、およそプロ野球に似つかわしくないフィジカルハンデを背負って登場するにも拘らず、プロの一線級のピッチャー以上の速球と野球の実力を持ってドラフト一位で選ばれるが、当初は入団をかたくなに拒否。なのにいざ入団してみると、初期こそその稀有な存在と野球の奥深さを描くシチュエーションで物語の主軸に収まるが、なぜか評価が一変して「お前がその体で投げる速球ではプロでは2流どまりだ。速球も、速いだけで球質が軽い。打たれればすぐホームランにされる。だからお前は誰も投げたことがない魔球を作れ。それしか生き残る術はない」とされ、事実それ以降番場も水原も、通常の球種を投げた時はたいてい打ち込まれるという方程式の中で魔球漫画へとシフトしていく流れも一致する。
また、これは逆の意味での一致でもあるが、『侍ジャイアンツ』は当初から、読売巨人軍と集英社との間で、漫画の連載期間は巨人の連続優勝が途絶えるまで、もしくは巨人のスーパースター、長嶋茂雄の引退までとされていたので、それらが途絶えた1974年のペナントシリーズ終了と共に終了する。しかし、『野球狂の詩』が当初のアンソロジー読み切り一本につき一人の野球人群像月刊連載を終えて、水原勇気をめぐっての週刊連載に移行するのが、番場が去った後の1976年からなのだ。
だからなんだって?
そりゃそうだ。
僕が今回語りたいことは「そんなこと」じゃない。
かつてこの国では、プロ野球が娯楽の王様であった時代があったのだ。
高校球児達が誰もが皆、プロ野球、それも巨人のユニフォームを夢見て白球を追いかけた。
一方で、架空の球団とはいえ東京メッツには、「野球が好きで、野球場でしか自分は生きてはいけない」者たちが、浮浪者、大富豪の御坊っちゃん、両親失い子、前科者、歌舞伎の跡取り、果てはサバンナの黒人から女性、ゴリラに至るまでが浮世の自分を捨ててグラウンドに集まり、白球に命を懸けた。
そんな時代に、番場蛮はハラキリシュートなど、文字通り白球に命を懸けて死に、続く年から(近年ようやく改正された)野球協約を突破した初の女性投手、水原勇気がまさにドリーム(夢)を投げた。
イデーの違いはあるかもしれない。漫画というエンターテインメントへの姿勢の違いもあるかもしれない。
魔球漫画というのは得てして野球漫画の枠を超え、サーカスと手品の一本勝負になってしまう部分は大きく、梶原氏は自らの『巨人の星』の癖手でただただ『侍ジャイアンツ』でそれをやり、水島氏は梶原氏になるまい、真似はするまいと意固地なまでに逆を行きつつ、結局『野球狂の詩』は一周回って梶原野球漫画と同じところに着地していった。