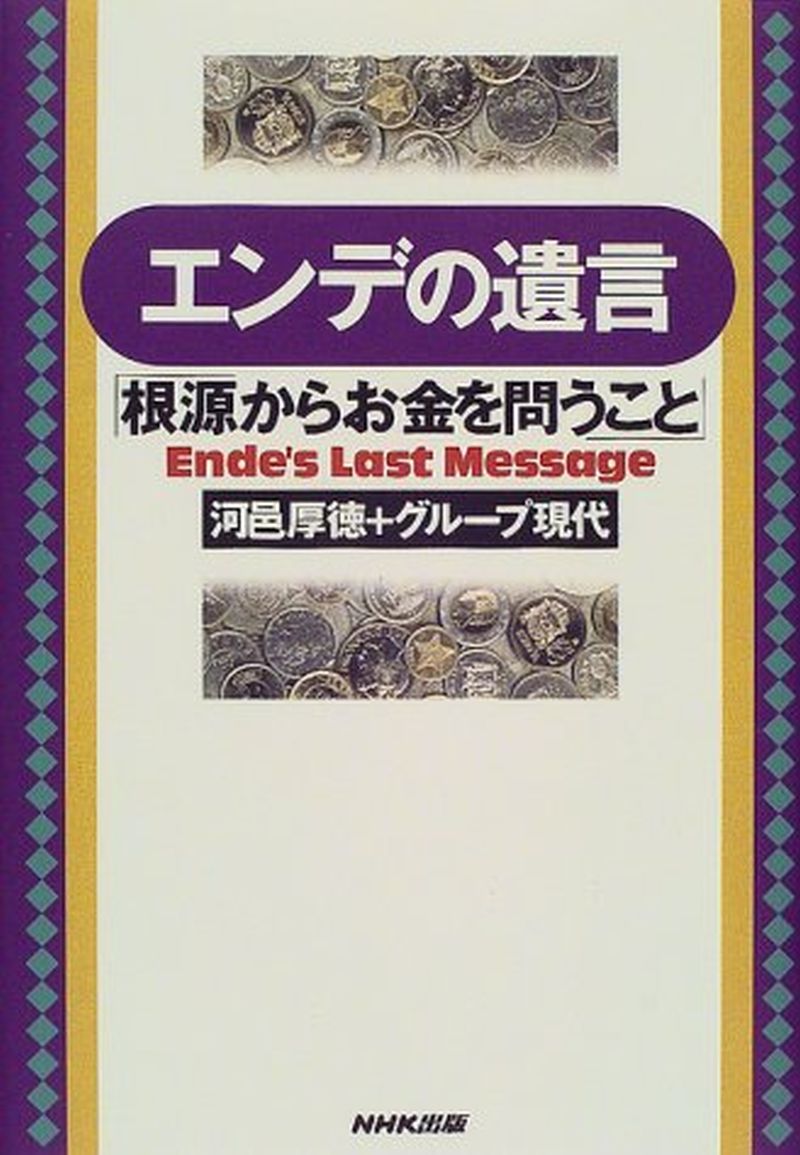そんなMichael Endeが、子ども達に託した願いの結晶の一つが、『モモ』だったのである。
「モモ」はすでに、限界の向こうに何があるか、を暗示している。特に僕の念頭にあるのは、マイスター・ホラのところでの話なんだけどね。そこでは物語は、何よりも外的な日常の現実を越えて、超越的で、形而上的な、あるいはシュルレアルな領域に移っている。
『オリーブの森で語り合う』
みんなは現状に満足している。思い出がなく、比べることが出来ないのだからな。みんなに残されているのは個々の瞬間だけなんだ。奴隷状態以外を知らぬ奴隷はおとなしい奴隷だ。俘虜生活しか知らぬ俘虜は自由がないことに苦しまない。
『ミスライムのカタコンベ』
モモは急に自分の中に不思議な変化が起こったのを感じました。不安と心細さが激しくなってその極に達したとき、その感情は突然に正反対のものに変わってしまったのです。
『モモ』
『モモ』の中で、灰色の男たちが登場しますが、私は大真面目にあれを書いています。灰色の男という「力」は目に見えない世界に明らかに実在していますから。それが悪魔という存在の現代的な姿です。
『三つの鏡』
Michael Endeは『モモ』を書き上げるのに7年もの歳月を費やしたのだという。これは日本における、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の逸話に似ているが、そこで描かれた寓話は、平和な街にやってきた、「時間貯蓄銀行」を名乗る灰色の男たちの甘言に誘い込まれた人々が、どんどん拝金主義に陥っていき、その謎の男は「時間泥棒」としての正体を現し、人間が人間らしく生きるための貴重な時間、人生を、奪い去る魔物として、モモは少女の身でありながら、屹然と立ち上がり、向かっていくしかないという、ファンタジー冒険ジュブナイルがここに完成したのである。
リアリズムが、すべての現象の全体的連関から、ある特定の現象―例えば社会的関係―を取り上げようとすれば、好むと好まざるとにかかわらず、虚構の世話にならざるをえない。そして虚構はその時々の文化に結びついているのだ。
『エンデのメモ箱』
確かに筆者は、今でこそ左翼主義者かもしれないが、その当時通っていた東京都区立の小学校では、毎朝の朝礼で国旗掲揚と国歌斉唱が義務付けられていて、誰も疑問に思わなかったような校風であり、しかしそんな土壌からも、筆者のようなはぐれ者が生まれてしまうという現実を前にする時、教育というシステムの効能論みたいなものにまで懐疑的になってしまうのではあるが、はたして筆者をしてこの、奇妙で生々しく、そして果てしなく暖かいファンタジーに引きずり込んでくれたのは、最初はこの児童書そのものではなかったのである。
1978年.筆者がまだ小学六年生の頃、劇団四季がこれを題材に『モモと時間どろぼう』というミュージカルを公演。東京をはじめとした5大都市での公演で、学童招待が1162校、134686名という記録が残っているが、筆者もこの134686名の中に入っているという前提があるのだ。
その上で、筆者自身も感銘を受けたが、それ以上に、なんというか恥ずかしい話だが、当時の筆者の初恋片思いの少女が、いたくこのミュージカルを気に入られたようで、そこはそれ(どこがどこだ?)筆者も懸命になって、原作の本小説を児童文庫で借りて読んでみたという、微笑ましいんだか浅ましいんだかという逸話があったりする。
しかし、それでも今でも覚えている。
鈴木邦彦氏作曲、岩谷時子女史作詞の、『モモと時間どろぼう』ミュージカルの主題歌でもある、『わたしには聞こえてくるの』という名曲の、澄んだ美しさと音色の融合が、拝金主義的時間泥棒達に向かって放たれていく中、モモの歌声が全てを浄化していく、あのクライマックスのカタルシス。
「私は歌う せせらぎの歌」
『わたしには聞こえてくるの』歌詞
この始まりと共に、現実の醜さは流され、やがてサビの
「生きてることはすてきなことね 夢見た人にいつかあえるわ」
『わたしには聞こえてくるの』歌詞
という結びに向かう。
そこには、Michael Endeが求めた、いやMichael Ende自身が持ち合わせていた、PrimitiveなInnocenceが凝縮されている、ストレートな人生賛歌として歌に結実しており、さすが、筆者が初恋するに値する聡明な美少女が入れ込んだだけあって(ツッコミ無用)、筆者も瞬く間に、Michael Endeの世界に吸い込まれてしまった。
大人の決めたIdeologyなど関係なく、子ども達は子ども達で、何が美しくて何が間違っているのかを理解している。それを大人社会が、胡散臭い嘘と醜いごまかしで、自分達の虚像を必死に繕ってみせても、子どもは見抜く力をもっていることを、誰よりもMichael Endeは信じていたのだろう。そして(しつこいようだが)大河さんの初恋の美少女はそれに反応し、息遣いを感じ、「その世界」当時の筆者たちが泥まみれになって転げまわっていたグラウンドではない「どこか」へと、旅立って行ったのであろうと、筆者は今でもそう思っている。
だから、あの当時など、ろくな読書感想文も書けなかったであろうし、今この年齢になっても、おいそれと迂闊なMichael Ende論など書けやしない。
『ネバーエンディング・ストーリー』の映画化が、かなり不満な出来であったこと、日本のエイケンのアニメ『ジムボタン』の出来にもたいそうお怒りで、だからなのか、放映後40年以上経った現在でも、一度もソフト化されていないことなど「あくまでオタクとして」しか、Michael Endeは語れないし、語ってはいけないのだと、自分を戒めている。
Michael Endeといい、最初期の虫プロアニメ版『ムーミン』(1972年)を全否定した原作者のTove Marika Janssonといい、児童文学、とりわけファンタジーの文学者というのは、気難しい人が多いというべきなのか、それだけ自分の作品に対する愛着や拘りが強いというべきか。
結局、僕の初恋は、時間泥棒ならぬ初恋泥棒に盗まれたまま、消え去ってしまったのである。