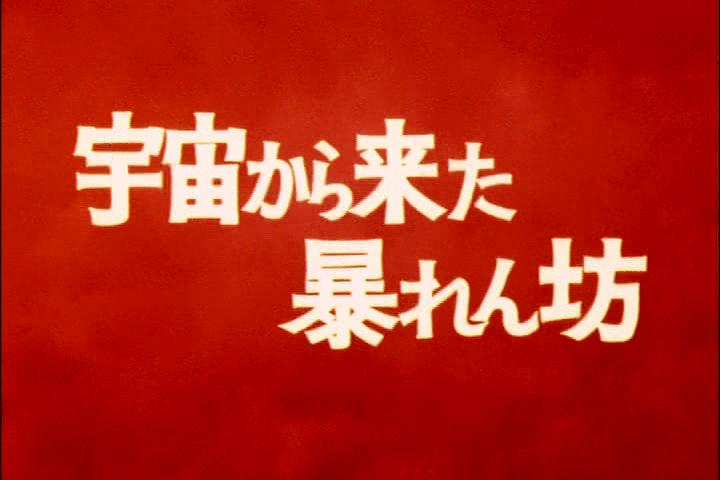その当時は気づかなかったが、本作を初めて読んだ小学生の頃、子ども向けの推理クイズブックで、「びっくりする凶器の例」として、Roald Dahlの『羊の殺戮(短編集タイトル『おとなしい凶器』Lamb to the Slaughter)』が紹介されていたが、今思えば、本格推理小説の隙を狙った、人を食ったようなここでの凶器トリックは、Roald Dahlならではの、ブラック・ユーモア精神が産み落とさせたアイディアなのかもしれない。
Michael Endeの『モモ』発表が1973年、Roald Dahlの『チョコレート工場の秘密』発表が1964年。10年近くの開きはあるが、世界は冷戦状態から文明化が進み、ベトナム戦争を脇で見ながら、ようやく終えた世界戦争の再来に怯える時期でもあった。
その時期に生み出された、ドイツとイギリスの児童文学。
どちらにも言えるのは「差別と貧困をなくし、人と人が本当の意味で手を繋がっていく中で、大事にしなければいけないものはなんだろうか」という、普遍的な問いかけ。
Tim Burton監督はさらにそこで、映画化するにあたって、原作では「素敵な大人は謎だらけ」の象徴だったワンカ社長のバックボーンを掘り下げることで、ワンカ社長を、自らの映画『シザー・ハンズ(DWARD SCISSORHANDS)』(1990年)の主人公、DWARD SCISSORHANDSとの鏡像にすることで、等しく「謎と夢が詰まってる王国の、寂しき独りの王」として描くことに成功した。
この『チョコレート工場の秘密』がどれだけインパクトがあって、どれだけ魅了されたのかといえば、その工場内部の素敵な世界観もさることながら、そこでギミックとして有効活用される「食べ物」の数々に尽きるだろう。
冒頭、貧乏な老人ホームから始まって、そこで登場する「具の殆ど入っていないキャベツスープ」だって、後々登場する豪華な食べ物群とのコントラストの配置だろうが、子ども心には随分と憧れたものだ。
ウンバルンバが現れる、チョコレートの川だって、想像が既に追いつかなくなるほどインパクトに溢れていたが、バイオレット・ボーレガードなる、ガム中毒少女が虜になる「次々と味の変わるガム」は、主観的には藤子不二雄氏の名作漫画『ドラえもん』の「おすそ分けガム」より早く読んだので、藤子先生の方が後追いパスティーシュかと思ったほどだ。
それよりなにより、この作品で「欲しい! 食べたい!」と思わせられたのは、劇中のどんなトンデモ御菓子よりも、冒頭で登場する、工場見学チケットが挿入され販売されていた「極普通の、ワンカ製板チョコ」であった。
チャーリーが、老人達のプレゼントの「その一枚」を剥くとき、その描写のリアルさは(当時はまだまだ、日本の製菓業界も、輸入菓子基準フォーマットだったからか)今も残る、森永チョコレートや明治ミルクチョコレートを剥く動作と寸分たがわず、その時のチャーリーの至福感がそのまま伝わってきたような描写が染みついていて、大賀さん、この年齢になっても、適度な「チョコ菓子」よりも、バレンタインで頂くゴディヴァのチョコよりも、結局「普通のメーカーが出している、一番スタンダードな板チョコ」が、一番好きだったりするのも、この児童文学の影響なのだろう。
なので。
小学生の頃、『MOMO』の感想文を書くときは、初恋のあの子を想起しながら、モモと重ね合わせながら、少しでも頭の良い、カッコイイ感想を書いてみせて、憧れのあの子に、ちょっとても良い印象を持ってもらおうと、肩ひじ張り過ぎた感想文になってしまい。
一方で『チョコレート工場の秘密』の感想文を書くときは、結局最初から最後まで、食べ物に関してしか言及していなかったという「目的や対象によって文体からキャラから、何もかも変える」も含めて、今回のこのコラムを総括してみても、結局言えるのは、どんなにプロの物書きでございと虚勢を張ったとて「三つ子の魂百までも」という呪縛からは、永遠に逃れられないのが人なのよねと、Michael EndeやRoald Dahlが、夢を託してくれた子ども自身としては、なかなか恥ずかしい、面目ない気持ちになったりもするものでありますよ、ハイ。
人間には神話が必要なのです。神話は人間の生の矛盾を、ひとつの物語やひとつの絵にまとめてくれますから。人はそれを指針にできる。
『ものがたりの余白』