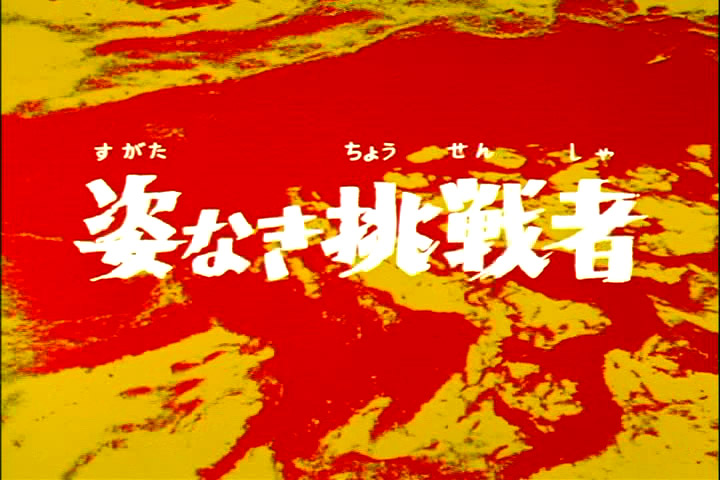『ヌードダンサーに愛の炎を』
『ヌードダンサーに愛の炎を』(監督・深作欣二)は「アンニュイな(劇中の岸田森の台詞より)財閥の令嬢」ストリッパー・マリ(演ずるは『ワイルド7』(1972年)でバイクに乗った黒尽くめの女殺し屋・ヘルキャットを演じた中山麻理氏)の、親元への奪還をメインのミッションにして、そんな元財閥令嬢・現ストリッパーと、そのヒモとしてしか生きられない室田日出男氏の、儚くも夢遠い、義理人情に生きた人生の終焉を綴った名作。
その中でショーケンは「いかにも」な任侠物語に巻き込まれていくことになるが、クライマックス、仁義を貫きドスを抱えて仇に討ち入りした室田に、ショーケンは義理人情で付き添うも、抱えたドスを包んだ新聞紙を解く判断も出来ず、相打ちになった挙句にメッタ刺しにされる室田を前に、悲鳴を上げて腰を抜かし、何も出来ず、醜く怯えながら、叫び逃げ回ることしか出来ない。

室田の死後、ショーケンも水谷も、二人ともマリから逃避行に誘われてその気になるが、次の日、マリはどちらの前にも現れることなく、父親の元へ帰っていった(この辺の「女の気まぐれで逃避行が決まり、男の側はその気になるが、女はしっかりと現実に正気を取り戻し、男だけが取り残される」は、後年の『ゴールデンボーイズ 1960笑売人ブルース』(1993年)の中で、若い作家・市川森一(演ずるは仲村トオル氏)と松島トモコ(田村英里子氏)の関係でも描かれていた末路だった)。
『殺人者に怒りの雷光を』
『殺人者に怒りの雷光を』(監督・工藤栄一)では、誰からも守られることのない、いつ消えても誰も気にしないような、ショーケンと水谷豊の仲間達の「街のチンピラの群れ」が、理由も相手も分からないまま、次々とダニか害虫の駆除のように殺され続けていく。
その「見えない恐怖」に対しては、ショーケンも水谷も、ただただ怯えるしかなく、逃げ惑うばかり。
犯人は被害妄想の女看護婦で、自分で自分の身辺調査を依頼した、探偵事務所の関係者を皆殺しにすることが動機だった(この辺はある意味で円谷プロの『怪奇大作戦』(1968年)っぽい。その仮想視線で岸田森氏を見てみると、演技巧者っぷりにニヤニヤしてしまう(笑))。
水谷は、迫り来る死を恐れすぎて自暴自棄になって、酔った勢いで(事件とは全く関係のない)チンピラをナイフで刺してしまい、留置場へ入れられる羽目になってしまう(この辺の「半端じゃない泥沼っぽさ加減」は
市川脚本の白眉と言えよう)。一方のショーケンは、岸田森と今日子の策で、犯人の勤めている病院に、病人(になりすまして、ではなく本当に服毒して)として、入院するのだが、そこへ襲ってきた犯人に対して優作の刑事のように格好良くアクションでなぎ倒すでも、拳銃で撃ち抜くでもなく、聞き取り不明な叫びを上げながら、服毒で自由の利かない体でとにかく暴れ周り、なんとか撃退することしかできない。

ラスト。普通の刑事物ドラマであればなんらかの形で、逮捕か射殺されるだろうはずの犯人の女は、ただの(本当にただの)交通事故で、あっけなく死んでしまう。
このエピソードが描きたかったのは(劇中で、何度もネタとして出てくる)「ゴキブリ死ぬ死ぬ」という(劇中内での)流行広告コピーに象徴されるような、「いつ死んでも誰も悲しまない。いつ死ぬことも誰も守らない。いつ死んでも気づかれもしないゴキブリ」のような、若い屑の群れの群像であった。
そこには、刑事ドラマであれば絶対に描かれない、「社会の財産と称され大事にされるはずの、若さと青春の時代を生きる青年」であっても、それは結局美辞麗句でしかなく、一握りの勝ち組の称号でしかないのだという現実。
現実の社会や日常は、そんな「ゴキブリ死ぬ死ぬ」で溢れ返っているのだという真理を、後年『必殺!シリーズ』で語り草になる「光と闇の工藤演出」が、これでもかというシャープさで、描き出していた。
また、劇中で追い詰められていくショーケン達「若いゴキブリ」のもたらす、救いようのない惨めな足掻き方は、行き詰まった当時の社会世相や世代感を言葉では言い表せないレベルで、描写し尽していた。
一言で言えば『傷だらけの天使』(の特に市川脚本作品)は、毎回毎回全てが「ここまでグダグダになっちゃうともう、普通のドラマだと、これで最終回にするしかないんじないの?」的な「もう何もかも積んでる感」が、満載(過ぎる)なのである。
『ピエロに結婚行進曲を』
それは、怨念にも似た女の執念を克明に描いた『ピエロに結婚行進曲を』(監督・児玉進)で、ショーケンが岸田今日子に呟いた、
「はなっからプライドなんて、俺持ってませんから」
という言葉に象徴されるだろう。
『母のない子に浜千鳥を』
『母のない子に浜千鳥を』(監督・恩地日出夫)では、まだ少女の面影を残していた桃井かおり氏が、一人の少年(ショーケンの息子役)を巡り、女の生き様もまた、死に物狂いで幸せをつかもうとして懸命なのだと、優しく、やがて哀しい物語が現実と直面していく。
そこでショーケンは、幼い子どもが生きていかなければいけない「環境」もまた、醜く、小ずるく、薄汚れた大人の打算と見栄に満ちた世界の枠の中でしかないことを実感しながらも、自分の亡妻の姉である桃井かおりが、自分の息子である健太を利用し、女の維持と情念で、なんとか田舎町で生きていこうとする姿を見る。
脚本の市川氏は、子どもの頃から父親の顔を知らず、母親も幼い時に亡くし、その後は親戚の家を転々と、鬼子扱いでたらい回しされていた過去を持つと聞くが、それを思うと、ドラマ展開以上にやるせない気持ちにさせられてしまう名作である。

『街の灯に桜貝の夢を』
『街の灯に桜貝の夢を』(監督・恩地日出夫)のゲストは、市川脚本の『太陽にほえろ!』で準レギュラーの女刑事・シンコで活躍していた関根恵子氏。
関根の今回の役は、水商売の女で(珍しく)水谷豊が彼女のヒモになるのだが、二人で一山当てようと目論んだ末、ショーケンを巻き込み、いつものペントハウスを改修して「絨毯マンションバー」をはじめる。
順調に仕事は進むものの、そこに目をつけた岸田森が一画策。
一流企業内の社長失脚計画に一枚噛んで、その社長をそのマンションバーへ連れ込み、関根との寝姿を写真に撮って、反社長派に売って商売にしようというもの。
よんどころない事情で条件を呑んだ、ショーケン・水谷・関根の三人だが、計画は上手く行き、写真も撮れるのだが、最後の最後で関根が社長にほだされる。
水商売の世界に生きてきて、こんな優しい人は初めてだったと呟く関根。だから、裏計画の全てを話しても、あの人は笑って許してくれたのよと、関根は夢見心地で水谷に語る。関根の心はたった三日ですっかり社長に奪われたのだ。
それを聞いて、今まさに関根へプロポーズしようとしていた水谷は、泣きじゃくって床を転げまわる。
「いつだってそうだ! いつだって最後はこうなっちまうんだよぉ!」
そんな水谷に「ごめんね」としか声をかけてあげられない関根。
「その社長と結婚するのかよぉ!」
と尋ねる水谷に
「馬鹿ね。あの人が私なんか、本気で相手にするわけないじゃない」
と呟いた関根は、最後に社長にフィルムを渡して、自分は去るつもりなのだと言って、ペントハウスを後にする。
その関根の背中に、フィルムを投げ渡して、後で帰ってきたショーケンの胸で、悲しみにくれて再び泣き叫ぶ水谷。
しかし、彼らを待っていたのは、もっと残酷で過酷な結末だった。
数日後、岸田森がショーケンと水谷に告げた。
「社長失脚計画は社長の知るところにより失敗に終わった。彼は特攻隊崩れの苦労人でね。何事も隙を残さない。そんな彼が、そんな女と結婚するようなロマンチストかね? 数日前、山中で身元不明の女性の死体が発見された。おそらく犯人は捕まらないだろう」
泣き崩れる水谷は、せめて関根の仇を討とうと、社長の乗る車を狙撃するために、山道でライフルを構える。
しかし(同じように、社長を暗殺しようと拳銃を懐に忍び込ませていた)ショーケンが、寸でのところで水谷を押さえ込み
「俺はお前を殺し屋にした覚えはねぇぞ!」
と殴る。
屑は屑でしかなく、屑には相応の生き方と環境しか与えられず、そこで屑が見る夢も、決してかなえられることなどこの世にはなく、分相応の屑らしい生き方を、甘んじて受け入れなければいけないのだ。
それは『傷だらけの天使』最終回に一番顕著な形で描かれることになる。