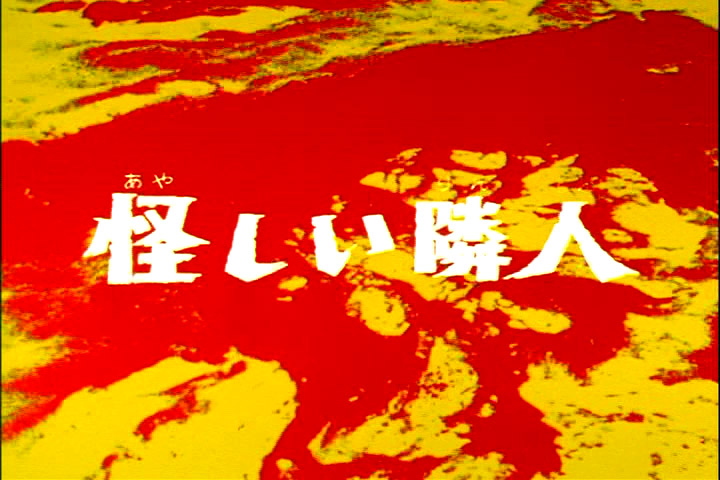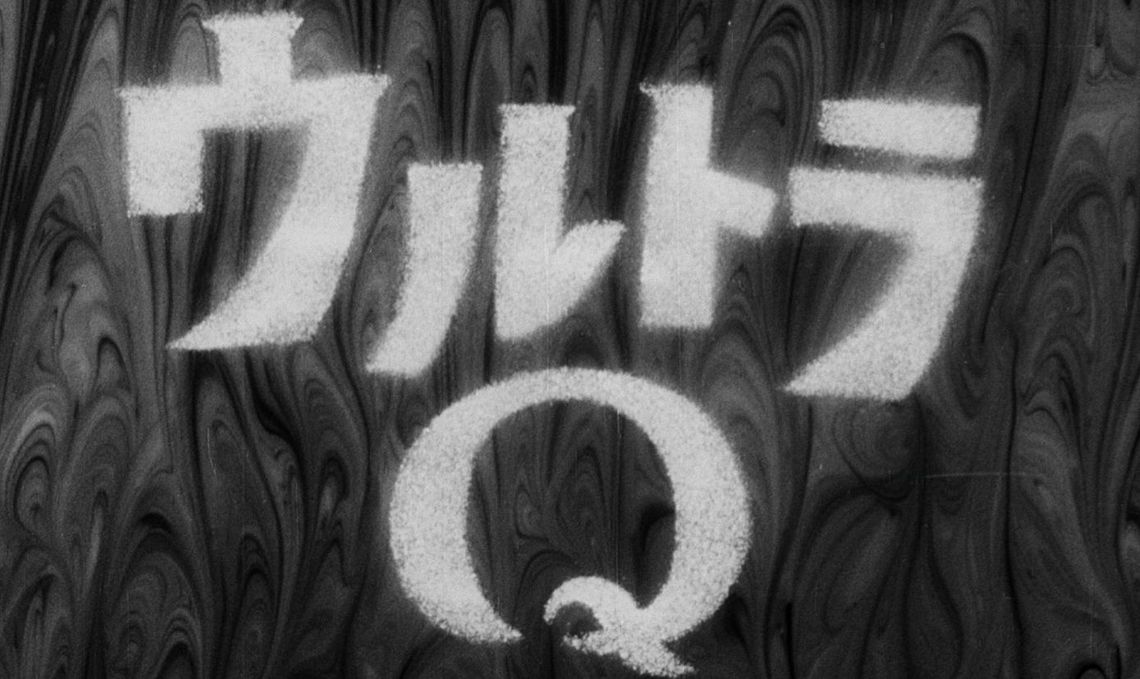さて、後半は初作大成功で乗りに乗った金子修介・伊藤和典・樋口真嗣トリオによる、シリーズ第二弾『ガメラ2 レギオン襲来』(1996年)について語ることになる。
思い返せばシリーズ初作『ガメラ 大怪獣空中決戦』(1995年)は、金子&伊藤&樋口トリオや、制作スタッフや配給会社、出資元からすれば、怪獣映画の製作自体がまだまだ初の挑戦であるからこそ、出来るだけ「個」の作風を抑え、踏まえるべき「王道要素」を着実に踏まえて、恐る恐る手探りで模索して作ったのであろう。
そういう経緯で作られた『ガメラ 大怪獣空中決戦』は、本当に優れた「誰もが共有する『怪獣映画』感に溢れた王道傑作」だし、本当に優れた『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』(1967年)のオマージュリメイクだった。
結果、ガメラというコンテンツは、シリーズ開始時点での志と出来は崇高だったが、しかしむしろ、その予想を上回りすぎた大成功ゆえか、金子&伊藤コンビは、そこで何か致命的な勘違いを起こしてしまい、ガメラを完全に私物化してしまった。
それが本作『ガメラ2 レギオン襲来』では数々露呈するのだが、予想以上の大成功を契機に、初作のときには隠していた「見せずに手の内に隠していた、個の本性」が、その後のシリーズ化達成で、まんまと露呈した形になったのだろうか。
本作では、前作ではあくまでリファインキャラであった「敵役の怪獣」が、改めて完全オリジナルの「レギオン」という新キャラで物語が進んでいく。
これは平成ゴジラが、復活作品の次にビオランテという完全新作怪獣を生み出したのを、なぞるかのような流れではあるが、逆を言えば自然な流れでもあった。前回解説したように、初作『ガメラ 大怪獣空中決戦』では、(その世界観の中では)初登場である二種類の怪獣の設定や特徴や、出現の経緯等が、流れるような筆裁きと、カットバックのようなテンポとリズムで描写されたのだが、本作では、新怪獣レギオンが(様々な意味で)過去にない斬新さを目指したせいからか、「レギオンという生物とはなんぞや」という部分にかなりの尺が取られてしまって、結果的に、他の要素(浅黄とガメラの絆やガメラの存在意義)等が、中途半端な印象をもたらしてしまった感も否めない。
また、その新怪獣・レギオンが斬新過ぎる設定ゆえか、まず、伏線のような形で数々の謎やディティール(電磁波への感応や酸素濃度の上昇、草体との関連性や、繁殖のシステム論)が張られて、それらは律儀に回収はされるのだが、その回収タイミングが必ずワンテンポ遅く、しかも作品理解の為に必須の要素に思える為、(実は案外そうでもない)観客は、リアルタイムで物語を租借しながら、そこで後付で解説されるレギオンに関する設定解釈を、そこまでに張られていた伏線と繋げて理解納得するという、二重のタスク処理を延々求められ続けることになる。
しかも、そこでの「レギオンの草体開花の描写」が、シルエットも出現箇所も、何から何まで『ウルトラQ』(1966年)製作第一話『マンモスフラワー』へのオマージュだけで構成されていて、見ているだけで恥ずかしくなる(というか、思わず「恥を知らないのか?」と問う)レベルで展開されるのだ。
これは確かにある意味で(あくまで「ある意味」で)特撮テレビ番組の始祖である『ウルトラQ』の、しかも製作第一話をリスペクトする心意気の表れとも解釈できるが、しかしオマージュやパロディというものはあくまで、画面の脇やストーリー本筋の外枠でひっそりやってナンボなのであって、ここまでメインで堂々とやられてしまうと、『踊る大捜査線 THE MOVIE』(1998年)クライマックスにおける「黒澤明監督『天国と地獄』(1963年)クライマックスへのオマージュ」のように「知っている人はシラケ」て「知らない人はこれがオリジナルだと感心する」という、本末転倒な現象を、生み出しかねないのである。
それはパロディと言っても良いし、オマージュ、パスティーシュ、なんでも良いが、メインストリームの演出描写で「借り物」を中心に、劇的さが機能させられてしまえば、それはもう、どんなに原典へ向けて敬意を後付けしようとも「盗人猛々しい」だけであり、創作者のイマジネーションの貧困さを、証明するしかないのである。(金子・伊藤コンビからすれば、90年に自分達に任されるはずで企画が進んでいた、劇場版新作『ウルトラQ』が、怪獣権利化権の問題等で企画から降ろされ、実相寺昭雄・佐々木守コンビによる『ウルトラQ ザ・ムービー 星の伝説』(1990年)に変えられてしまったことへの、リベンジの意味が込められていたのかもしれないが……)