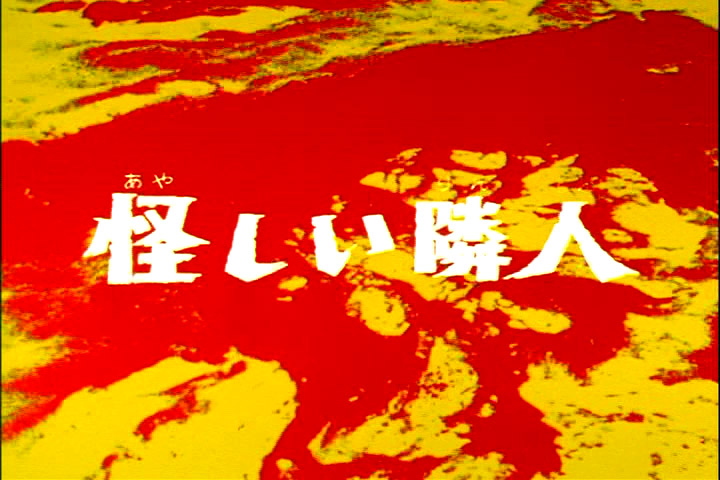今回紹介する『ゴジラ対メカゴジラ』(1974年)は、ゴジラ生誕20周年の、記念の年に作られた作品。
この時期ゴジラ映画は既に黄金期の国民的大作映画ではなくなっていて、いわゆる『東宝チャンピオンまつり』の(メインとはいえ)プログラムの一つに格落ちしていた事もあってか、黄金期作品とは違って物語スケールが小さいとか、明らかに火薬の仕掛けの分量を間違えてタップを踏むように連鎖爆発が起きる中野昭慶爆発とか、クライマックス、琉球伝承の怪獣・キングシーサーの眠りを覚ます歌(『モスラ』(1961年)のよう)の『ミヤラビの祈り』が、沖縄っぽさが皆無の、どう聞いてもムード歌謡曲そのまんまだとか、「ゴジラと若大将にトドメを刺した」と言われる『エスパイ』(1974年)の福田純(笑)監督とか、ツッコミドコロとしては、そういう色々含めて全部がまぁいろいろある作品。
その一方で、オイルショックも直撃していただろうこの時期に特撮用セットを三杯以上組むとか、黒澤明映画・岡本喜八映画を音楽面で支えた佐藤勝音楽のもたらす、重厚かつアップテンポの劇伴と特撮のシンクロ率の高さとか、なによりもこれまでの対戦相手のどんなキャラよりも「圧倒的に強そう」なメカゴジラの存在感と造形力の高さが、この作品を(B級ではあるかもしれないが)一流のプログラムピクチャーたらしめている。
そもそもこの作品は当初「東宝・円谷プロ」で製作する企画があったらしい。
といってもそれは『ゴジラ対メカゴジラ』という企画ではなく、『ゴジラ・レッドムーン・エラブス・ハーフン 怪獣番外地』という仮題であった。
沖縄を舞台に、突如現れた「月から来た怪獣」レッドムーンと、その来訪に呼応したかのように現れる古代怪獣エラブス。
二代怪獣に手をこまねいた人類は、二匹の怪獣を戦わせ合って共倒れを計画するが、逆に二匹の怪獣は「恐ろしい人間」を前にして助け合い、やがて愛し合う。
そして、二匹の怪獣の間に生まれる子ども怪獣ハーフン。
しかし、ハーフンを見世物にしようとする人間が現れ、結果ハーフンは殺されてしまう。
怒り狂った怪獣夫婦は人間社会を滅ぼさんと暴れ出すが、そこに現れたのが怪獣王ゴジラであった……というシノプシス。
読む限りにおいては、まるで『ウルトラマンタロウ』(1973年)で上原正三氏が書いた『親星・子星・一番星』のようであるかのような内容だが、実はこのシノプシス(企画が進めばそのまま脚本も)書いたのは、『ウルトラマン』(1966年)の生みの親でもあり、上原正三氏と同じく沖縄出身の金城哲夫氏。
古代怪獣エラブスが「伊良部島」からきている「古代からの琉球民族」を示唆する存在であって、子ども怪獣ハーフンが、その名もそのままに「ハーフ」を指す事は間違いないが、ではレッドムーンは何を指すのか?
この時期沖縄人と大量にハーフを生み出していた米国軍人か。いやそれも違うだろう。
レッドムーンという存在は、おそらく後に上原正三氏や国文学者の上原輝男氏らが、金城氏に対して指摘したように、折口信夫氏が解析した「まれびと(稀人)」信仰に根差していたものと思われる。
この幻の企画は、当初の予定では監督を東條昭平氏(円谷プロ出身で『怪獣使いと少年』を監督)、特撮監督を佐川和夫氏が務める予定で企画が進んでいたが、諸事情により頓挫してしまった。
(ちなみにこのコンビは同年『ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団』(日本公開は1979年)を手掛けており、日タイ合作のこちらの方に人事と企画がスライドされたと思われる)
結果的に完成した東宝版『ゴジラ対メカゴジラ』には「沖縄が舞台」「沖縄の古代怪獣」「赤い月」というように、幾つかの断片が遺されているが、作品的には全く別物の、シンプルな宇宙人地球侵略スパイアクションのスタイルに収まっている。
話の展開としては凡庸だ。
宇宙人がゴジラを模したロボット・メカゴジラを製造して、ゴジラに偽装させて日本を襲わせる。
その基地は沖縄にあり、その謎を追って主人公青年や科学者達が沖縄へ向かう中で、宇宙人スパイ群との戦いがあり、また沖縄に眠る伝説の守護神怪獣キングシーサーの存在が示唆されるという流れ。
怪獣映画的には、序盤にゴジラに偽装したメカゴジラ相手にアンギラスが登場。
クライマックスにはそのキングシーサーも登場して三体の怪獣のバトルになるが、怪獣物としての主眼は、あくまでも怪獣王ゴジラと、それを模したメカゴジラとの直接対決に絞り込んでおり、そこへ人間達の宇宙人基地攻略が並行して描かれる。
(監督の福田純氏が脚本も手掛けているが、メインで脚本を書くのは山浦弘靖氏)
「本土復帰したばかりの、哀しみの琉球国家から日本へ向けて、日本の戦争の刻印でもあるゴジラの『模倣』が襲う」とでも書けば、上原正三氏作品のようなプロットとも読み取れるし、それなりの奥深いテーマやメッセージを読み取りたくなってしまうが、実際に出来上がった作品を見る限りにおいては、沖縄という「(当時)まだちょっと珍しいロケーション」をフルに活用して、目先の変わった風景の中で展開する、勧善懲悪の娯楽物といったところか。
敵の宇宙人が、死ぬと猿人である正体を現す辺りは、これは当時リバイバルヒットしていた映画『猿の惑星』(1968年)のルックスをちゃっかり頂いた形であろう。
『猿の惑星』は1968年の作品だが、本作の公開の前年の1973年に日本でTV放映されていて、それがちょっとしたブームを呼び、本作と同じ年には小松左京氏などを招いて作られた、『猿の軍団』(1974年)等という「SFドラマ」が放映されていたりもする。
この「敵宇宙人の正体が実は○○」というガジェットを、福田監督は案外お好みのようで、既に同じゴジラシリーズでも『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』(1972年)なる作品では、劇中に登場する宇宙人の正体がゴキブリであったり、その辺りで流行を取り入れていたりもする。
中野特撮監督の(爆発好きはおいておいて(笑))メカゴジラの描写は圧巻だ。
特に偽ゴジラの正体が暴かれてメカゴジラとしての姿を現す時の、佐藤勝音楽とシンクロしたカッティング描写と、最終決戦における全身の武器を一斉発射するもたらす「絶望的な強さ」の描写は、過去のゴジラ映画にもなかなか見られなかったスピードと迫力の名演出。
引っ張るだけ引っ張っておいての、いざ登場したキングシーサーの役に立たなさはご愛嬌としても、全身血まみれになりながらも、満身創痍で奮闘するゴジラというのは、子ども心にウルトラヒーローにはない壮絶さを感じさせられた。
物語は、スパイアクション風味あり、諸星大二郎風伝奇綺譚の趣あり、東宝特撮王道のインテリ科学者の葛藤ありと、隙がなく詰め込まれているが、全体的にはB級作品の印象はぬぐえないかもしれない。
しかしそれを補って有り余るのが、この作品を彩るキャスティング・俳優陣の顔ぶれだろう。
「岸田森・平田昭彦・小泉博・睦五郎・草野大悟」という、東宝特撮的・六月劇場的個性派俳優の揃い踏みには胸がときめいてしょうがない。
あまつさえ、その俳優陣の個性が決して調和する事無く、各自独自の風格と色合いのまま作劇が進行するのだからこれはたまらない(笑)
平田昭彦氏と小泉博氏の「昔ながらの東宝特撮インテリ科学者」が、科学と考古学の双方から謎に迫ったかと思えば、睦五郎氏は睦五郎氏で、とても地球を狙う宇宙人の親玉とは思えない「刑事ものに出てくる悪徳政治家」のような演技で作品世界を素敵にスケールダウンする。
そうかと思えば「インターポールの捜査官」という役どころのはずの岸田森氏は、序盤から(また今回も私服だったのだろうか)誰も想起しない役作り方向で、どんな悪役よりも怪しさを醸し出しまくった挙句、同じ六月劇場の草野大悟氏を狙撃してみせたり、クライマックスには華麗なアクション(笑)も見せてくれる。
ゴジラの時代ももう終わり、そのラストを(昭和ゴジラの「本当のラスト」は、翌年の『メカゴジラの逆襲』(1975年)だが、その作品はゴジラ映画人気というよりも、本作でのメカゴジラ人気が喚起した企画であったのだろう)飾るのに相応しい配役がなされている(劇中の客船の船長役で『ウルトラQ』(1966年)の佐原健二氏がカメオ出演している)。
この時期眠りについたゴジラが次に目覚めるのは1984年であり、その活躍最盛期は90年代だが「毎回主役なのに悪役」という矛盾を背負わされた平成ゴジラシリーズは、やがてはどんどん破綻していく事になる。
その平成ゴジラシリーズで、再びリファインされたメカゴジラが登場する『ゴジラVSメカゴジラ』(1993年)でのメカゴジラは「ゴジラが悪役なのだから」という理由で、人類の英知が作り上げたメカゴジラを、自衛隊(劇中ではGフォースなるある意味戦隊)が、操ってゴジラと戦うという物語であった。
今、『ゴジラ』というコンテンツは迷走している。
ハリウッドで米国版ゴジラが作られたり、邦画でもプライベートムービー的な新作が、興行収入を上げ社会現象化したり、ゴジラの二次創作的アニメも放送されて好評を博している。
「ゴジラの本当の眠り」は、まだまだ訪れそうにもない。