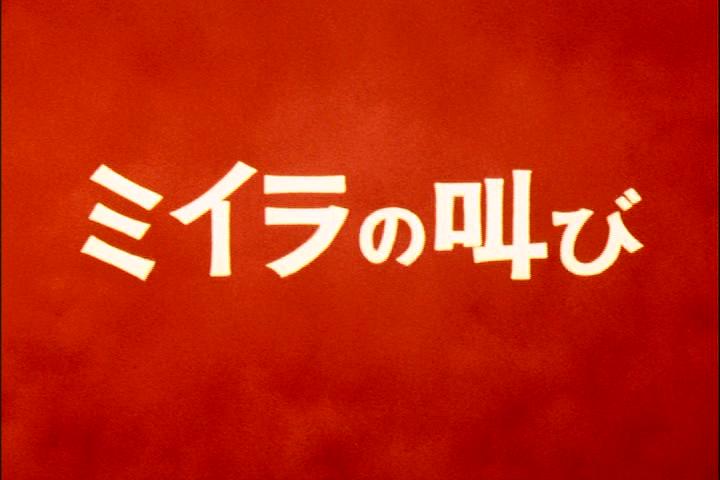公開当時も思ったのだけど、ゲームの映画化として最高峰であるだけではなく「元のゲームがそもそも、既存のSFやホラー映画のオマージュ集大成ゲームなのだから」という理由からなのか、あそこもここもそっちもこっちも、まるで古今東西のSFホラーアクション映画総集編のように、ほぼ全編が「いつかどこかの作品で、既に観たことがあるようなシーン」に溢れてる。
例えば、弾丸一発残った拳銃しか手元になく、ゾンビの群れに追い詰められた男性が、その弾丸で自殺すると見せかけておいて、逆にゾンビを撃って窮地を突破するシーンとか、ゾンビに噛まれた仲間の一人が、痛み苦しみながら意識を失っていき、結局主人公の目の前でゾンビ化して襲い来るとかの、要所に挟まれたシチュエーションは、どう好意的に考えても、あからさまに「アレ」へのオマージュなわけで(面白いのはそもそもゲームの『バイオハザード』自体が、George Andrew Romero監督の『ゾンビ』(1978年)へのオマージュの塊で作られているのは明白なのだけれども、ゲーム版バイオで取り入れられなかった、映画『ゾンビ』名シーンへのオマージュが、数々とこの映画版バイオには取り入れられているのは面白いところ)。
一方「そこ」は『遊星からの物体X』(1982年)で「あそこ」は『エイリアン2』(1986年)で「こっち」は『死霊のえじき』(1985年)とかの「ホラーファンならニヤリ」が続出で、「あのトラップ」はあからさまに『キューブ』(1997年)だったし、アンブレラ社の「ハイブ」統括人工知能・レッドクィーンの元ネタは、そもそも『2001年宇宙の旅』(1968年)のHAL9000といった按配(まぁ確かにイマドキは。「人類に悪意を持った人工知能」という設定を持った映画も増えすぎてジャンル化したし、このレッドクィーンの場合も状況が状況だけに、一概にオマージュとは言い切れないが)。 そんでもって主役のミラ・ジョヴォヴィッチ(Milla Jovovich)嬢はまさに、『エイリアン』シリーズのSigourney Weaverと『マトリックス』シリーズのKeanu Charles Reevesを足しっぱなしにしたような、まさに「過去の名作の主人公像の集積」といった感じで、そういうあらゆる意味でこの映画は「80年代の特殊メイク至上主義時代から、2000年代のCG台頭時代にかけて、映画史に名を刻み込んだ、SF・ホラー・アクション映画の名作群」へのオマージュカタログ作品とも言えるわけ。
その後の『バイオハザード』映画シリーズ化の過程で、とうとうミラ演ずる主人公は、その両者を足してさらにスーパーサイヤ人化した、チート主人公化するのだけれども、個人的にはミラが、なにより可愛いので許すことにしよう(笑)
その上で「オフィスのセットの隅にさらっと置かれたハーヴ」「ゲーム初作の舞台となる『洋館と研究所』を、位置関係は軸を変えつつも両立している」「クライマックスはちゃんとタイムサスペンス」「カラスも犬も登場」「最終決戦は疾走する電車の車両の中」等々、決してキャラや物語自体はゲーム版に忠実ではないけれども、「バイオハザードというゲームが好きな人」のツボは押しまくる作品に仕上がっている。
というのもこの映画、ゲームの実写映画によくあるパターンの「プロデューサーが版権を買い取り、ゲームに何の思い入れも知識もない監督を招き、ゲームとは縁もゆかりもない作品に仕上がる」経過を辿ることなく「バイオを愛し、バイオの映画に参加したくてたまらない」という主演女優と監督を、メインで参加させることに成功したからだ。
監督のPaul W. S. Andersonなどは既に『モータル・コンバット』(1995年)も手掛けていて「コイツ、実はただのゲームオタクなんじゃ?」と思わせてくれる人だし、ミラ嬢も(妹だか弟だかが)このゲームにハマっていて好きだったと語ってるし、そういう人材的な意味では幸せな映画化を迎えたゲームともいえるだろう。(むしろ面白かったのは、ミラを巡っての実生活での恋愛争奪戦。ミラはまず自分に恋して「自分の映画に出演してもらうに当たって、そこで話す宇宙語を、徹底的に勉強して欲しいから」という意味不明な理由で、ミラの家に通いつめた『フィフス・エレメント』(1997年)の監督・Luc Bessonと結婚するがすぐ離婚。その後、この映画版バイオのPaul W. S. Andersonと再婚した経緯がある。『フィフス・エレメント』も徹底した「低知能SF馬鹿映画(褒め言葉)」だったが、こうして経緯を見るとミラ嬢も、Sean Youngレベルの人格破綻美女みたいで、素敵過ぎるというものだ(笑))
まぁこの映画を、そうそう褒めちぎってばかりいてもなんなんだっていう話もあるわけで、確かにこの映画には、難点もいくつかある。
まずは「元ネタがゲームである」以上、製作した米国でも子どもに見せたい都合上(欧米では残虐シーンの年齢制限が厳しいので)R-15指定を狙った結果、ゾンビ自体を描写するための特殊メイクやCG処理は素晴らしいものの、スプラッタシーンやカニバリズムシーンが殆ど描けなかったという、ゾンビ映画としては致命的なビハインドを持っている。
また「ホラー映画の恐怖演出としては余りに初歩過ぎて稚拙な、『突然大きな音を鳴らすことで観客をビビらす』を多用しすぎる」など、マイナスポイントは随所に散見されるものの、いろんな意味で「CG全盛の2000年代ならではのゾンビ映画」のエポックメイクとしては、及第点をあげても良い映画だったよねと、個人的には思うのであります。 むしろ、アレコレ書いてきたが、何はともあれ全ては「ミラ嬢が可愛いので許す」映画なわけだが「主人公が無敵に可愛いというのは、やっぱり大事だなぁ」が今日の結論です(笑)(註・劇場公開当時、仲間内でだけ話題になったけど、ラスト近くの「あのシーン」って「アレ」が写ってたよね(笑))