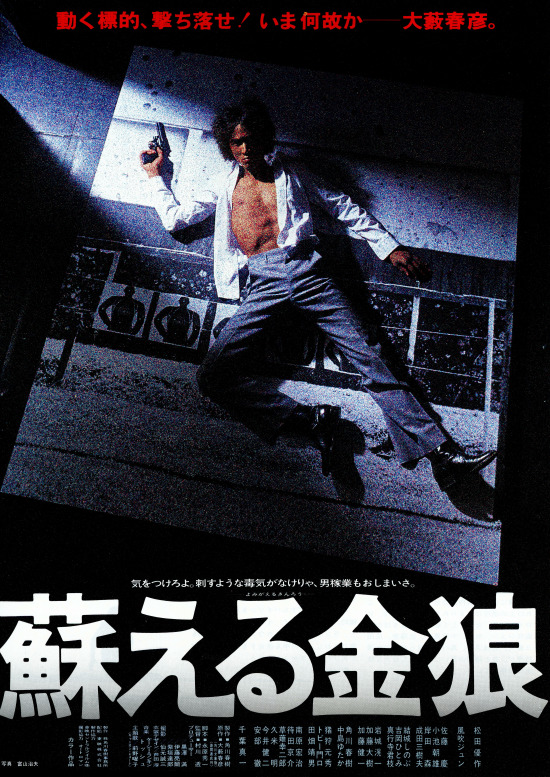最初にお断りしておかなければいけないことが、二つほどある。
一つは、筆者の映像評論姿勢においてそもそもは「映像作品は最低でも三回は観てから書く」と、そういう自己ルールがあるのだ。
映像力学やテーマ、文芸論を全てひっくるめて語ろうというのに、一見だけではあまりにも、情報が処理できないからだ。
しかし、今回の『SPACE BATTLESHIP ヤマト』(2010年)は、映画館で一度見たきりの、直後に書いた文章が、ここから先のベースになっている。
だから今回のヤマト論も、ディティールや細部などで、解釈の間違いやミス、また、勘違いや取り違えもあるかもしれないので、その辺は指摘があれば訂正したいと思っている。
そして二つ目は
筆者は今回のこの映画『SPACE BATTLESHIP ヤマト』の原作となった、『宇宙戦艦ヤマト』(1974年)というアニメが、大嫌いであるということ。
古くから馴染みがある友人やフォロワー諸氏であればご存知かと思うが、筆者はあの、70年代後半に巻き起こったヤマトブームに接し、そこでの「愛国精神の美しさ・正しさ」や「特攻隊の美しさ」「国家の為に死ねる尊さ」や「愛という名目で、全てを自己完結で陶酔するナルシズム」に対して、子どもながらにも「大人が何か、僕達を騙そうとしている」と直感し、薄ら寒いものを感じ、一応テレビシリーズの一部は観たものの、安っぽいロマンチシズムと愛国賛美に嫌気が差し、その後も白眼視していて今がある。
なので、今回書く『SPACE BATTLESHIP ヤマト』論においては、原作たるアニメ版ヤマトに対しての、愛も思い入れも、その一切がない状態で、一人の文章屋が、この映画を観て何を思ったのかという視点で見て頂きたい。
さて『SPACE BATTLESHIP ヤマト』論に入る前に、もう一度アニメ版ヤマトを、ざっと筆者なりに括らなければならない。
『宇宙戦艦ヤマト』とは、保守愛国メディアの読売において、元虫プロ営業だった愛国思想家の西崎義展氏の企画・旗振りで製作されたアニメである。
そこにあったのは、かつての太平洋戦争の愚かさの象徴だった無用の長物・大和を、宇宙SF冒険活劇の世界で蘇らせて、あからさまに白人をモデルにした異星人相手に、獅子奮迅の活躍をさせ、そこでの激闘の果てに、愛すべきキャラクター達が、一人、また一人と、「愛と祖国(ここでは地球)」の為に、喜んで死んでいくという、なんとも、時代錯誤かつ、おぞましいテーマと精神主義だったのだ。
なにせ、シリーズの何作目かでは(いちいち細かく覚えてないが)刀折れ、矢も尽きたヤマト乗組員が、全ての希望を失って自失する中、「武器はまだある! 俺達にはまだ命があるじゃないか!」と、そこでドラマがぐーんと盛り上がり、喜んで特攻死していくという、常識と良識を疑う展開すらあって、それが「これぞ真のSFロマンなんだ!」「男のロマンだぜぃ!」と、賞賛されて送り手も受け手も陶酔していたのが、時のヤマトブームだったのである。
当時、そのヤマトの名物プロデューサーだった西崎某という男は、日の丸を背景に、着物姿で日本刀を構えて写真に写るのが大好きだった御仁らしいが、そんな、右傾思想啓蒙の一方で、ヤマトというアニメ作品は、後々のアニメ文化を支える、数々の才能を世に送り出したことでも知られている。
詳細は、この項の本題ではないので省くが、ヤマトなければ、ガンダムもエヴァもなかったといってもよいのかもしれない。
そんな功罪併せ持ったヤマトであったが、20世紀後半から西崎氏が、その「過去の威光」を担保にして、各所で「ヤマト復活やるやる詐欺」とでもいうべき、金銭トラブルを散々起こした挙句、銃刀法不法所持や覚せい剤所持などで、何度も刑務所とシャバを行ったり来たりするような愚行を繰り返し(政財界で一番の盟友は「あの」石原慎太郎氏である)2010年11月には、なんと小笠原で停泊中の、自前のヨットクルーザー『YAMATO』から転落死してしまった。
彼の死は、今も数々の謎を残すといわれているが、これも本題ではないので言及は避けることにしよう。
そんなヤマトの生みの親・西崎氏が逝去された直後に完成上映となった、今回の『SPACE BATTLESHIP ヤマト(以下・実写版ヤマト)』だが、監督・山崎貴氏(VFXも兼任)と製作の阿部秀司氏は、2005年に大ヒットを飛ばした『ALWAYS 三丁目の夕日』でお馴染みになったコンビ。
脚本は、稲垣吾郎氏が金田一耕介を演じた『犬神家の一族』『八つ墓村』(共に2004年)等、SMAP主演のドラマや映画で名を馳せている実力派の佐藤嗣麻子氏。
佐藤氏は山崎監督とは、この映画の一年前に公開された、やはりSMAPの草なぎ剛氏主演の『BALLAD 名もなき恋のうた』でもコンビを組んでおり、漫画的・アニメ的な世界観や展開を、どう生身の人間のドラマに落としこむのか、そこに関しては経験を広く積んでいるトリオであるといえた。
(註・『BALLAD 名もなき恋のうた』は、アニメ『クレヨンしんちゃん』の劇場版の一つ『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦』(2002年)が、原作になっている)
この映画は、オタクの間では、公開直前まで広く深く「間違いなくコケる」と断言されてきていた。
確かに漫画やアニメ、しかもSFの名作を実写映画化して、成功した例はあまりない。
洋画だと『Xファイル』(1993年〜2002年 The X-Files)の脚本を担当していたJames Wongが2009年に監督した『DRAGONBALL EVOLUTION』が、原作『ドラゴンボール』とはかけ離れた世界観や物語で失笑を買った記憶も新しい。
それと同じように「あのヤマトを」「実写で」「しかも主演がキムタク」となれば、ちょっとアニメ通、映画通を気取っていれば、観る前から批判の一つもしたくなるし、「どうせ」と前置きして、自己満足の分不相応な要求を突きつけ、「そうでなければ、俺はヤマトだとは認めないし、どうせ絶対コケるに決まってるね」などと知った顔の一つもしたくなるものだろうということは、筆者とて理解できる。
中には「俺の中のヤマトを汚さないでくれ!」と絶叫するオタクもいた。
いやはや、信心深い信者が多い宗教は面倒な存在である。
しかし、危惧されていたキムタク実写版ヤマトは、興行初動で40万人・5億円を記録。
先行していた『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』を抜き、最終興行収入予測は結果的に39億円に達した。
なぜ、あれほどまでにオタクが怨念のように「絶対コケる」と念じていたのに、実写版ヤマトはここまで成績を伸ばせたのか。
筆者は今回、劇場で作品そのものを観て、少しその謎がつかめた気になっている。
それを今回は、解説していこう。
いやいや。
先に愚痴るのは男らしくないのだが、筆者は本当にヤマトを観る気はあまりなかったのだ。
確かに、山崎監督も佐藤氏も、その仕事の丁寧さと実力の程は筆者も認めている。
でも、ヤマトなんだろう?
確かに筆者は木村拓哉氏を(意外と)好んでいる。
彼の芝居の持っているスタイルの源流は、筆者が最も敬愛する松田優作氏の演技の系譜から、新劇的要素をストイックに削いでいった先にある一つの「計算されたナチュラルさ」という素材としては、大きな魅力を感じている。
でも、ヤマトなんだろう?
今回のヤマトは確かに、愛国右傾思想メディアの読売系列ではなく
中道リベラルのTBS資本であり、TBSは筆者にとって様々な意味で育んでもらった、恩恵あるメディア局であり、そこではきっと「器を変えれば入れる物も変わる」と、きっとなってくれるだろうと信じていた(そしてその「信じる」は叶った)。
けど、でも、ヤマトなんだろう?
そう、ヤマトなのだ。
筆者は、ヤマトが社会現象ブームを起こした70年代後半、小学校中学年頃、「これを作った大人達は、僕を騙そうとしている」と気付き、それ以来、ヤマトと名がつく作品には、決して金と時間を割かないことを、信条として、誇りにしてきたのだ。
思えば大学時代など、ヤマトブームにかぶれ残った残党の友人に「絶対おもしろいから! 男のロマンだから! 泣けるから!」とか言われ『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(1978年)というアニメのビデオを観させられ、憤慨し、激怒し、その友人を追い返した記憶があるのだが、そのタイトルにもあったように、当時のアニメ版ヤマトは、何かあるとすぐさまに「愛」という漢字を持ち出しては、そこで「御国の為に死す」ことを正当化する。
余談だが、『月光仮面』(1958年)を筆頭に、ヒーロー物の原作者でも知られる、愛国右翼民族派だった川内康範氏(一般の人には、『おふくろさん』という歌を巡る、森進一氏との騒動で晩年知られている)も、そこで作るヒーロー番組にやたらと『愛の戦士レインボーマン』『正義を愛する者 月光仮面』(共に1972年)『正義のシンボル コンドールマン』(1975年)等々、とにかく「愛」とか「正義」というお題目が好きだった。
筆者はそれがまず、無理だったり不愉快だった。
誰も逆らえない金科玉条を持ち出して、それを踏み絵のように差し出して、己の理念に隷属するか反抗するかを迫るのは、こういった愛国右翼のやり口である。
だからだろう。
今回筆者は、実写版ヤマトの劇中にもしも「愛のためだ」というような台詞があったら、悪いが、そこで席を立とうと思っていた。
そう、今回なぜに筆者が人生の信条と誇りを捻じ曲げてまで、実写版ヤマトを観たのかというと、答えは簡単で、キムタクの大ファンであり理解者である友達主婦から「ぜひ、一回観てやってください。そして大河さんなりの感想を聞かせてください」と、そういうオファーがあったからなのだ。
女性のお誘い一つで、30年守ってきた信条をコロッと寝返させるのも筆者らしいが(笑)そんな筆者の信条を知っているはずの友達主婦さんが、そこまで筆者に勧めるのだから、そこにはきっと何かあるだろうと、思って信じはしていた。
いや、それ以前に筆者は、あらかじめいくつかの情報と人選を読み解いて、「今回の実写版ヤマトは、少なくとも往年のアニメ版のような、愚かなウヨク脳メッセージを垂れ流しにする愚作ではないだろう」と、踏んではいたのだ。
踏んではいたのだが、そこには信条と誇りが邪魔をしていた(笑)
それを上手く、作品へと誘導してくださったのが友達主婦さんというわけである。
しかし、筆者はその「この実写版はおそらく、アニメ版のような愚かさはないな」と確信してはいたものの、逆に同じ要素が心配でもあった。
なにせ、原作のアニメ版が「アレ」なのであるからして、そこで、30年経ってもヤマトに思い入れを持っているようなファン層は、つまり「もっとアレ」な人達なのである。
男のロマンと称して、人を殺したり、御国の為に死んだりすることを、賛美して感動して、涙まで流すような連中なのだ。
連中は、カルト宗教の信者のように頑固で厄介だ。
既に公開前からして「なんで古代がキムタクなんだよ! 古代が『おい! ちょ! 待てよ!』なんて台詞いうところなんか聞きたくねぇよ!」「なんで佐渡先生が高島礼子なんだよ、そもそもなんで女なんだよ! (註・原作では佐渡先生は、禿げてメガネのおっさん)」等々「ここが原作アニメと違うから許せない」という論調がアチコチから聞こえてきていた。
いくらアニメ・テレビの歴史に残るコンテンツのヤマトとはいえ、30年前の作品であるのだから、30年前のファンを呼び戻せなければ、目論んだ興行収入に行き届かないのではないか?
「30年前に右翼メディアと愛国プロデューサーが作ったアニメ」に心酔するファンを、「現代において、中道リベラルメディアが陣頭指揮を執った実写作品」が、納得させられるわけがない、呼び寄せられるわけがないのではないか?
そこは筆者も、危惧する部分であった。
しかし、この実写版ヤマトは、最後まで観るとよく分かるのだが、「原作アニメの名台詞やディティール」を、巧みに分解して散りばめ、その一つ一つに「違う意味」をもたらして、換骨奪胎した作品だったのだ。
その換骨奪胎ぶりは、同じ設定、同じ器、同じ台詞、同じシチュエーションを、全く違う角度から再構成する、作劇の奥深さを感じさせてくれる作品に、結実していたのであった。
物語冒頭からしばらくは、少し急ぎすぎた印象は否めない。
心配されていたCG効果やVFX効果は、日本映画にしては丁寧さで磨きがかかっている。
まず、地球を襲った謎のガミラス軍に対して、抵抗なすすべもないまま、地球艦隊が全滅するところから話ははじまるのだが、ここで山崎監督は、徹底した俯瞰アングルとパンニングの切り返しで、物語を動的に動かしながら、人間描写に観客の目を留まらせないで状況を動かし、「物語全体」へと、観客を引き込むカッティングに努める。
主人公・古代の兄である古代守(堤真一)の出撃と死も、その流れの中で描かれるが、そこでもカメラワークは戦闘CGとテンポを崩さない。
一方、地球上で主人公の古代進(木村拓哉)の登場となるが、そこから、古代がヤマトに乗り込み、要職に就くようになってもまだ、カメラは群像劇を映し出す俯瞰を主軸として、物語の流れのみを追う。
しかし、人間ドラマを描写するときに不可欠であるカメラ固定のバストショット(役者の胸から上を固定で写すカット)が現れるのは、ヤマト防衛のための宇宙戦闘機に乗ったまま、戦闘機が故障を起こして、そのまま宇宙空間に取り残されようとしている森雪(黒木メイサ)を救いに飛び出そうとした古代が、沖田艦長(山崎努)に制止されて怒鳴る時なのだ。
「あんたはそうやって、俺の兄貴の時も、切り捨ててきたんだろう!」
戦争で、大の虫を生かすために小の虫を殺すことは、戦局的には大事なことである。
いつだって戦争と、戦争を娯楽として描く物語はそれを「仕方の無いこと」という大前提で描き、その悲惨さと美しさを説いてきた。
しかしキムタクの古代は違った。
キムタク古代は、全編を通して「愛のため 仲間のため 御国のため」にヤマトの仲間が死んでいくことを、否定して阻止し続けるのだ。
そこまで、絵物語の構造とカメラワークで世界観と全体像を見せ付けられてきた観客は、そこで初めて「血の通った人間」を、見せ付けられる。
それがキムタクの古代であり、それが「仲間を見捨てることは美徳じゃない」だったのだ。
一方、ヤマトを狙うガミラスは、往年のアニメ版ヤマトとは正反対に、こちらが次々と、特攻自爆戦略を仕掛けてくる戦法が描かれた。
そこまでで、筆者はふっと気付くことがあった。
これは、山崎・佐藤・阿部トリオによる、ヤマトの形をもった、アニメ版ヤマトへの、膨大なアンチテーゼが含まれているのではないかと。
そう思うと、妙なことが気付くようになってきた。
そもそも、アニメ版と実写版のヤマトには、大きな設定の相違は無い。
ヤマトはもちろん「全滅しかけた地球艦隊が最後の望みを託して、太平洋戦争で沈んだ大和を復活させた宇宙戦艦」だし、ワープ航法も「地球の科学ではない、イスカンダルよりもたらされた超科学航法」だし、波動砲だって「イスカンダルの超科学で実現した、必殺の主砲」なのだが、アニメではそれらが、ここぞとばかりのケレンミとハッタリ演出で、威風堂々と存在感を発揮して描かれていたのだが、実写版ヤマトでは、ヤマトの初登場も、初めてのワープも、意外とあっさりと描かれている。
なるほど、確かにSF的基礎知識レベルに雲泥の差がある30年前と現代では、今更ワープだ波動砲だというSF的ガジェットで、驚く人もそうそういないからだろうが、こと「神軍日本の象徴たるあの大和が、今度は地球を救う宇宙戦艦として蘇った!」に関しては、ヤマトという作品のセンスオブワンダーの根幹を成しているビジュアル要素だけに、普通なら、そこでどどーんと、ハッタリとケレンミを効かせた演出の一つもやってみせるだろうところを、発進こそハイレベルなCGとカメラワークで魅せたものの「ヤマトが大和であること」については、終盤少しだけ触れられたのみ。
それが、アンチテーゼゆえなのか「どうせ観客は皆知ってるわけだから」なのか、どういう判断なのか、筆者には分かりかねるが、ここまでの佐藤脚本と山崎演出は、徹底してその骨子から、「あの惨敗戦争へのリベンジと陶酔・そして美しい軍事愛国精神」を、オミットする方向で、作劇と人間交錯を描いている。
続く後編では、キムタクこと木村拓哉氏の主演演技にスポットを当てて、映画通ぶる一部の人達からは、バカにされ偏見で見られている「キムタクのキャラ」「キムタクドラマ」が、どれだけの意味を持って、どれだけの価値があるのかを、語ってみたいと思っている。