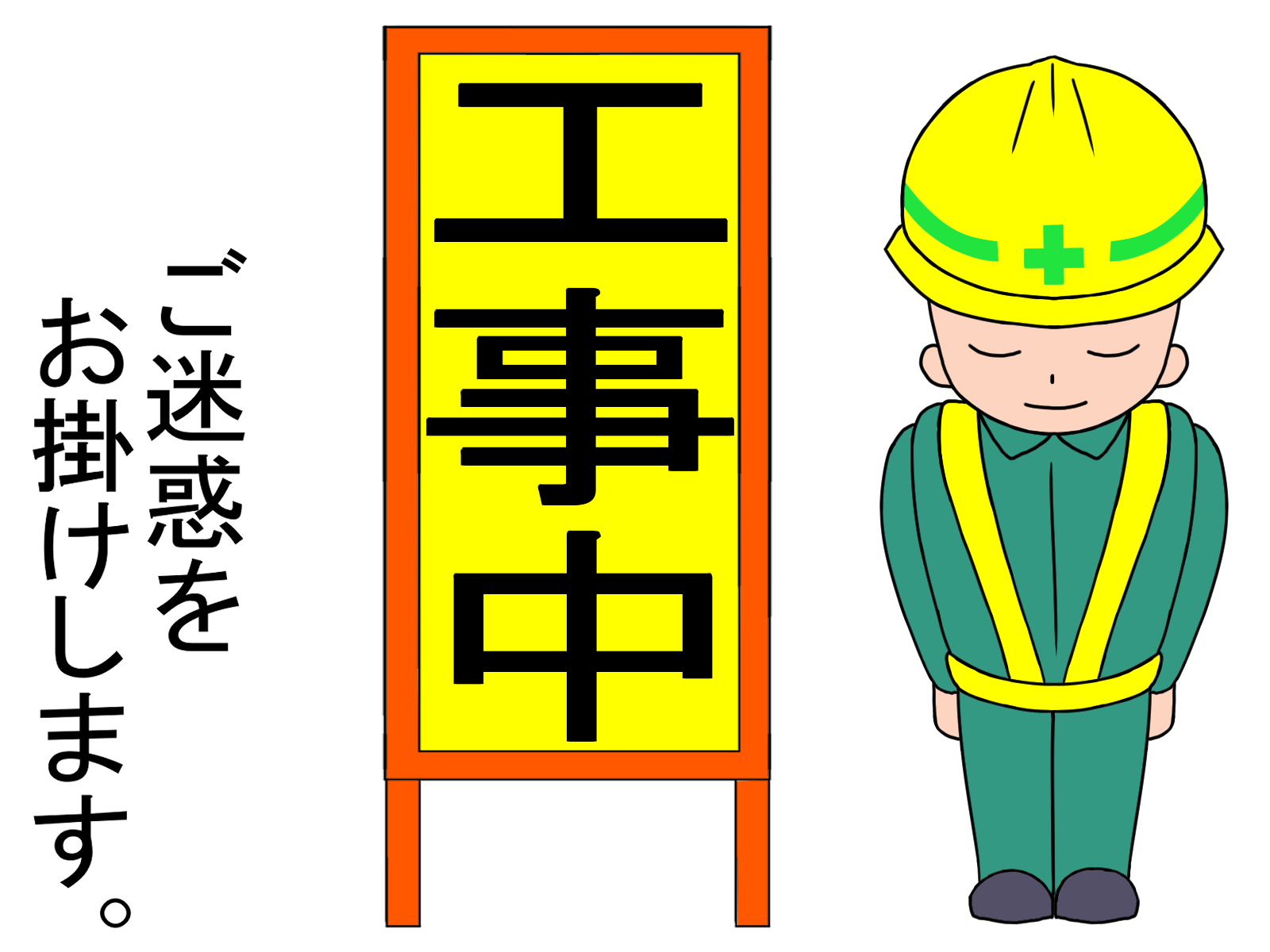前編はこちら。
『SPACE BATTLESHIP ヤマト』論 前編
物語で戦争を描く時に、愛国精神も愛と正義も描かないという前提論は、「ではなぜ主人公は戦うのか」という問いかけを明確化させる。
例えば富野由悠季氏の『機動戦士 ガンダム』(1979年)では戦争そのものを、「それが避けられない状況そのものであったから」からはじまるドラマで、見事に「人と人が繋がる社会のテーマ」へ昇華させていった手腕があったのだが、本作での(アニメ版ヤマト同様)「自らの意思でヤマトに乗り込む古代進」の場合は、ガンダムのアムロのような「巻き込まれ型主人公」ではないため、そこに明快なモチベーションと、それと直結したテーマが求められる。
しかし、この段階ではまだそれは語られていない。
アニメでは「崇高で有能な軍人だった兄・守の意思を継ぐ」という、軍人としては立派なモチベーションがそこには存在していたが、木村拓哉版古代進は、それすらを持たずにヤマトのブリッヂで必死に戦い続ける。
その姿は、観る者によってはとても奇異に写るかもしれない。
もちろん「キムタク節」はここでも健在だ。
今風にいえば「ツンデレ系ヒロイン」になるのだろう、黒木メイサ演じる森雪が、古代に対して批判的かつ頑固な態度を最初見せるが(この辺は、同じ黒木メイサが演じた、TBS日曜劇場『新参者』(2010年)での、ヒロイン青山亜美の性格を思い起こさせる。そういえばこの映画には、同じ『新参者』からマイコも出演していた)、そこで古代が突っ込む
「もうちょっと気楽にいかないと、ね?」
などは、これはもう、キムタクならではの台詞回し、イントネーションでこそ光る台詞であろう。
キムタク嫌いの古参アニメオタク諸氏は、そこで嫌悪感を出しそうだが(笑)
キムタク古代が「何に懸け 何と戦うか」が、逆の意味でほんの少し垣間見えるのが、物語中盤間近の、地球との連絡のシーンだ。
ここでは「ヤマトがもうすぐ、地球とは連絡がとれなくなるので、全艦職員は、各自一分ずつ、地球の家族と通信が許可される」というもの。
島大介(緒形直人)は、地球に残した息子と涙を誘う別れを交わし、斉藤始(池内博之)は、年老いた母親からもらったお守りを通信画面に掲げていた。
皆、愛する家族とのいっときを過ごすのだが、ここで古代の番がくるのだが、通信室へ招かれた古代は、用意された通信機に向かうでもなく、のんびりとした一分をそこで過ごすのだ。
そう、彼にはもう家族がいないのだ。
宇宙戦争の影響で家族を失い、たった一人の肉親だった兄も殉職し、古代は、何も守る物も、待っていてくれる者もないまま、天涯孤独のまま、宇宙で死闘を繰り広げているのだという事実が、ここで観客に初めて明かされる。
本来、アニメ版ヤマトでは古代という主人公は、明るく生真面目で熱血な、好青年として描かれていた。
それは一方で、当時のアニメや子ども番組の主人公は、かくあるべしという典型でもあったし、一方では、カルト宗教や軍国主義に染まった「純粋まっすぐ君」の不気味さも蓄えていた形のキャラクター像であったのだが、キムタク版古代はやはり、あくまでもキムタクなのである。
それは、いつものキムタクキャラであるのと同じく、「ちょっと斜に構えながらも、時に熱く、時に喜怒哀楽がはっきりしている」という、『ロングバケーション』(1996年)や『ビューティフルライフ』(2000年)でみせた「あのキムタク」そのままなのだ。
しかしそれは、キムタク本人や作劇側の無能を意味しているわけではない。
むしろ「キムタクがキムタクであるための理由付け」が、そこで丁寧に作られている。
それは上記したドラマの他『GOOD LUCK!!』(2003年)『華麗なる一族』(2007年)等、木村を主役に抜擢したドラマ全体に言えることなのだが、そこでキャラクターメイキングを担当した、北川悦吏子女史や井上由美子女史は皆「どうしてそこに登場する主人公は、キムタク的なメンタリティを持っているのか」そこに対して、かなりのウェイトを置いたバックボーンを描くことを大切にしている。
「ぶっきらぼうでつっけんどん。でも寂しがりやで口下手」という、誰もがパターン化して記憶している「キムタクっぽさ」が、いかにしてパイロットや美容師といった、ドラマ内配置的に自然に置き換えられるか。
作家やプロデューサーや演出家達は、常にそこを逆算してドラマを組み立てている。
その「キムタク主人公逆算」と「アニメ版ヤマトが持ち込んだ数々のお約束」の、理想的な融合が、その無言の通信シーンをきっかけにしてはじまる。
キムタク版古代は、この実写版ヤマトの古代進は、ただただ「家族」が欲しかったのだ。
戦争で父も母も失い、たった一人残った兄さえも「名誉の戦死」を遂げた。
その「家族全てを奪った」戦争と戦艦に、自ら乗り込むことで、「自分が残された意味」を自分に問いかけて、その中で、出来ることなら「家族」を探したかったのだ。
『機動戦士ガンダム』シリーズの富野由悠季監督は、ガンダムの戦争が必ず、お家騒動や親子喧嘩に端を発してる理由を尋ねられて
「戦争というマクロな出来事を描く作劇だからこそ、等身大の出来事を、対比として組み込まなければ、ドラマには血が通わないんです」
と答えていた。
アニメ版ヤマトは、そのマクロな出来事を「愛と正義」という、もっとマクロなお題目と大義名分で煙に巻いて、若者や思春期の多感な青少年を、愛国へと誘う胡乱な狂気だった。
しかし、山崎・佐藤コンビは、実写版ヤマトに於いては、その「胡散臭い器」に対して「キムタクらしさとは」をぶつけ融合させることで、「人の持っている、等身大の出来事」へ、指針を向かせたのだ。
上で記した多くのキムタクドラマの木村主役がそうであったように、キムタク古代は、そこで抱いている無限の寂しさと弱さを見せることなく、必死に艦長代理という大役を務め続けようとする。
誰にも「寂しい顔」を見せようとはしない。
佐藤・山崎コンビは、そこで徹底的に「「戦争の大義名分」喪失させる。
アニメ版ヤマトの大義名分の「戦争をする核」として機能していた、放射能除去装置・コスモクリーナーでさえも、それが沖田艦長のハッタリと嘘でしかなく、何も根拠のある希望ではないと描き暴く。
キムタクの古代は、その真実すらもたった一人で背負いながら、表層しか観ないドラマウォッチャーや、アニメ版ヤマトオタク達が揶揄する、「キムタク風」な、おどけやシャイさでドラマを彩っていく。
役者は映画という大きなシステムの中では駒にしか過ぎず、その駒を、生かすも殺すも指揮者次第なのだということは映画論・ドラマ論の基本だが、役者の役者ならではの個性・特性を、作劇全体から逆算して効果的に組み込むことも、戯作者や演出家にとっては、大事な技法なのである。
筆者が映画全体を見渡していて、ハッとさせられたカットがいくつかある。
物語終盤近く、ようやく到達したイスカンダルを前に(この、イスカンダル到達もまた、アニメ版とは真逆にして、わざと淡白な印象をもたらすように、あっさりと演出されているのだが、そこに関しては後述する)キムタク艦長代理が皆に向けて演説をするのだが、そこでカメラワークは、若干の俯瞰からパンニングをして古代に迫っていく。
ドリー(横移動レール撮影)ではなくパンニング(カメラ立ち位置固定で、カメラ軸の固定でフレームを移動させる撮影法)ということはつまり、観客に対して主観を与えながら、状況全体を古代という個人と重ね合わせていく、演出とカメラワークなのだが、そこで横パンカメラが古代を捕らえる時、古代ははっきりと「みんなの愛する家族のために」と唱えるのだ。
それを唱える古代には、もう家族は誰もいない。
しかし古代は唱える。
「家族を守るために戦おう」
と。
コスモクリーナーの嘘も、全ての孤独も抱えた天涯孤独の男が、それだけを仲間に必死に訴えるのだ。
このシーンがもたらす、ある種の絶望感は、おそらく、家族がいる人には、感じようとしても無理かもしれない。
誰も共感できない孤独、誰も分かち合うことは出来ない寂しさ。
キムタクが演じてきた『ビューティフルライフ』の柊二が、『華麗なる一族』の万俵鉄平がそうであったように 、キムタクが演じる「寂しい男」がいつもそうであったように
おどけとシャイと、斜に構えたぶっきらぼうさで隠しながら、「寂しい魂」は、求める物を求めようとせずに、やるべき役目を果たそうとする。
それが「キムタク流」の本質なのである。
世間やオタク、批判派は、木村拓哉という俳優の、演技の表層のワンパターンばかりをあげつらい、「何をやらせてもキムタクだ」などと罵り、分かったような顔をするが、それは確かに製作側が、狙ってやらせている部分もあるのは認めるが、それと同時に、キムタクという素材を与えられた製作側が、常に傾けている腐心は「なぜ、そこでキムタクらしさが表現として求められるのか」のエクスキューズであり、本作では、それは見事にこの終盤で「ヤマトでなければならなかったこと」と、「アニメ版ヤマトへのアンチテーゼ」とを、融合させる結果を生み出すのだ。
アニメ版ヤマトで、盟友・真田(今回の実写版では柳葉敏郎)の名台詞だった
「古代、俺はお前のことを、本当の弟だと思っていたぞ」
は、アニメでの「同じ国家、同じ軍に属した者は皆親子兄弟」という気持ち悪い思想を離れ、キムタク古代が抱える、真なる孤独の中にあった「家族がもう一度欲しかった」という、決して埋まらないはずの寂しさを、癒し埋める言葉へと姿を変えた。
アニメ版のヒロイン・森雪の名台詞といえば「だって! 古代君が死んじゃう!」だったが(本当、頭悪い女だなこいつ)実写版の雪は、クライマックス、一人で死を選ぶ古代に対して
「あなたがいない世界なんて、生きる価値はないわ」
と泣いて古代に抱きすがる。
戦争は、誰のために戦うのか。何と戦うのか。
御国のため? 糞くらえだ。
愛のため? 正義のため? そんな見たことも食ったこともないもののために、命を懸けるのはごめんだ。
命を懸けて戦うに値する世界は、命を懸けるに値する「誰か」がいる世界に他ならない。
キムタク古代の戦いは、それを探し、見つけるための戦いだった。
手づかみもない、存在すらもあやふやな「愛のため」なんかではないのだ。
自分を家族と呼んでくれる「誰か」を見つけ、絆を得るため、握り締めるため。
そう。
だからこそ、イスカンダルは「目的地」ではなかったからこそ、その到着と邂逅は、淡白に描かれたのだ。
古代進・木村拓哉の旅の目的地は、そんな虚構の星ではなかったのである。
『SPACE BATTLESHIP ヤマト』は決して「愛と正義を守る、夢と男の戦争ロマン」などではなかった。
一人の寂しい、天涯孤独の男が、全てを背負って笑顔を見せて、もう一度「欲しかった家族」を手に入れるまでの、懸命な姿の物語だった。
「アニメ版ヤマトへのアンチテーゼ」は、かしこに見られた。
ミリタリーマニア心や「ライバルロマンオタク」の心をくすぐるデスラー総統と、「勝利の女神願望」をいまだ忘れられないオタク心を離さないスターシアは、表裏一体の存在として描写され、その存在性が相対化されたのは痛快だった。
エンディング近く、滅びかける地球に戻り、そこで沖田艦長が
「地球か……何もかも懐かしい」
と残して死んでいくまでは、アニメをなぞっておきながらも、その後に最後の大展開を設置している辺りは、アニメ版のナルシズムを、痛烈に逆利用していて面白い。
また、本作をSFスペクタクル活劇として観た時には、セットパターンが少ないことや、モブシーンが足りない(地球の命運を分ける、正規の大発表を扱う記者会見でのマスコミの数が20人程度なのには失笑した。『突入せよ!あさま山荘事件』(2002年)でも、その三倍はいたろうに)ことや、戦闘規模が少ない(全編を見渡した後に、壮絶な艦隊戦をやったという印象が無い)等、気になる面は、確かに少なくはなかった。
そのクライマックスが『エイリアン2』(1986年 Aliens)や『マトリックス・レボリューションズ』(2003年 The Matrix Revolutions)や『スターシップ・トゥルーパーズ』(1997年 Starship Troopers)の影響が大きすぎること(往々にして日本のSF映画ではありがちではあるが)や、ストーリーが大掛かり過ぎて、尺に詰め込みすぎの感も否めない。
そういう意味で、難点や問題がなかったかと聞かれれば、多々あったと答えるしかない。
しかし。
エンディング。
おそらく古代との子どもなのだろう、幼い子を連れて、緑の大地に戻った草原で、空を見上げるヒロイン・雪の姿を見て、筆者は一人、映画館の客席で泣いてしまった。
古代は家族を得られたのだと。
残す物を得られたのだと。
それは決して国家も栄光も関係ない、一人の天涯孤独の男の、生き方がそこにあったのだと。
アニメ『宇宙戦艦ヤマト』は、愛と正義を信じた愛国精神溢れる青年達が、命を犠牲にしても、忠誠を誓った国家(星)の為に殉じて戦う戦争ロマンだった。
『SPACE BATTLESHIP ヤマト』は、愛する家族を全て失った天涯孤独の男が、家族を得るまでの物語だった。
その違いはどこにあったのだろう。
製作配給側のイデオロギーなのか、監督の思想なのか、キムタクという素材の資質ゆえなのか。
筆者にはそれを判別することは出来ないが、事実は動かない、揺るがない。
この映画は、古参ヤマトオタクが如何に批判しようが否定しようが、数十万人の人達を映画館へ向かわせる力を持っていた。
それはきっと「センスオブワンダー」でも「戦争ロマン」でもない、もっと普遍的な、人が誰もが根底で持ち合わせている「寂しさ」へと、訴えかける力を、この作品が持っていたからに、他ならないからではないだろうか。
形骸化した「愛」や、政治利用の「ロマン」じゃぁ、人の腹は膨れないんだよ。
人は誰だって、自分の手を見つめて握ってくれる「誰か」がいれば、それだけで生きていける生き物なんだと、この映画は大きなマクロ視点で、それを描いてみせたのだろう。
そして、それを演じられるのは、木村拓哉氏しかいなかったのかもしれない。
友人キムタクファン女性からのお誘いで見に行ったとはいえ、結果、30年経って、とうとう俺も「映画館でヤマトを観て泣くような男」の仲間入りを果たしてしまったなぁと、つくづく感慨にふけっている。
アニメ版ヤマトがブームを起こして30年は、あんな生き方だけはしてはいけないと、固く誓って「男」をやってきた人生だったのだが、今回の実写版ヤマトのキムタク版古代のような生き方ならば、やってみせて、死んでいってもいいのかもしれないと思っている。
それもまた、天涯孤独の男の、一つの夢でもあるからだ。
「君は何に懸け 何と戦うか?」