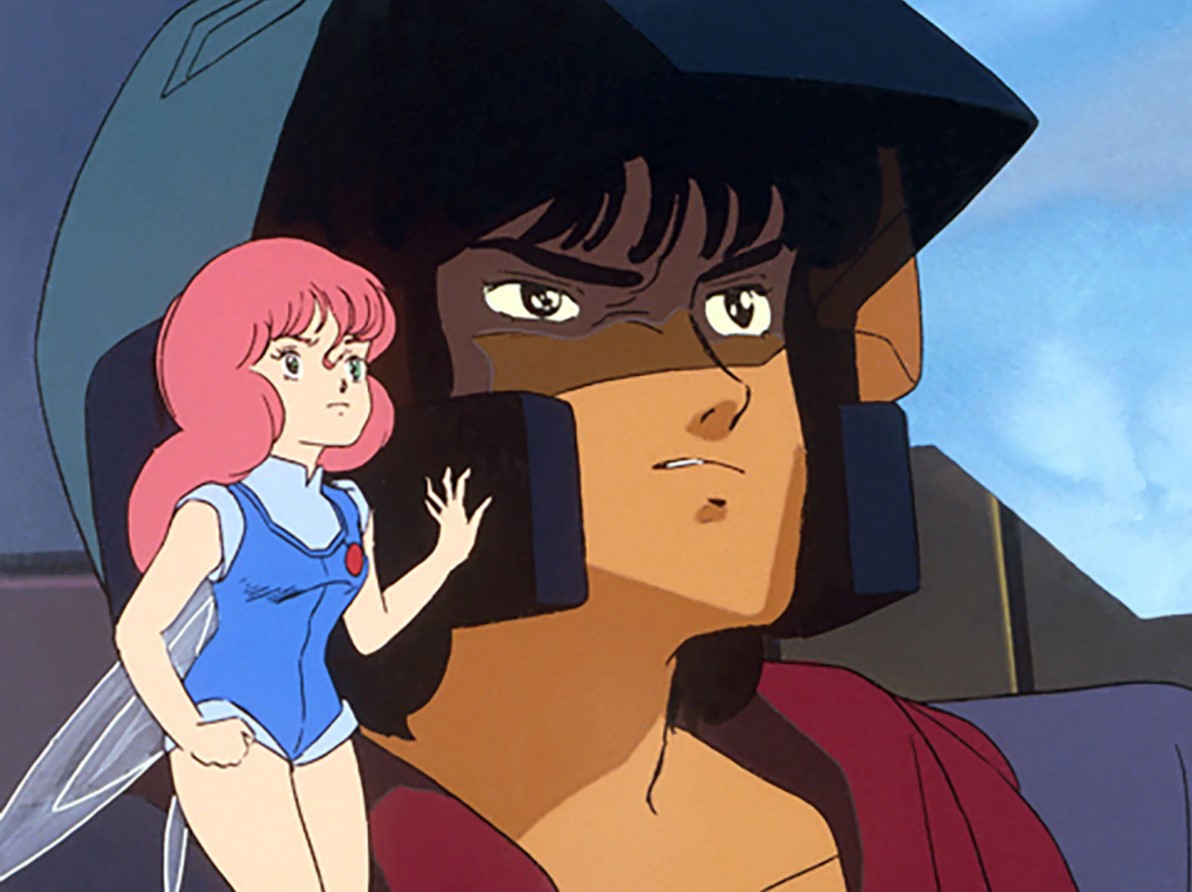はたして。映画版『人間の証明』は、原作に並び匹敵する名作になった。それは、佐藤監督の手腕に寄るところも大きいだろう。また、当時から評論家筋で批判されていた「ラストのパーティの受賞コメントで、いきなり犯人が長台詞で動機やら犯行を、自発的に延々と語るのは陳腐だ」「主人公刑事コンビが、西條八十詩集の意味に気づくきっかけが、あまりにも唐突で陳腐過ぎる」というツッコミも、理解はしよう。
ラスト、夜明け朝焼けの霧積で、崖の上で空を見ていた犯人が、最後の告白をするのも、その後延々とお約束になる「2時間サスペンスのクライマックスの先駆け」というのは、これは先見の明があったと評価すべきだろう。
そういった問題は諸々抱えつつも、森村氏と佐藤監督の視点は「戦後30年」(執筆当時)に向けて、虫眼鏡で太陽の光を受け、集約させながら焼き尽くすように集中しており、そこへ向けて、日本とアメリカ、老若男女の登場人物たちが、全て「親子と血」というテーマで、愛し合い、殺し合い、「戦争を起こしてしまった国家の原罪」を、永遠に背負い合うのである。
その視点の鋭さと集中力の高さは、松本清張氏がやがて『日本の黒い霧』を書いたように、森村氏も『悪魔の飽食』など、「実在した、社会の謎と悪」へ向けてペンを走らせるようになるのだが、それはまた別の話。「日本とアメリカ そして戦後」という壮大なテーマを「人間」という二文字に集約させた森村氏の気迫は、松山氏と佐藤監督によって、充分にスクリーンに投影できたと筆者は思いたい。
最後に余談であるが、この名作はその後も何度か映像化されているが、そもそも上でも書いたように「戦後すぐの闇市で、少年時代を過ごした刑事が主人公」である伏線は外せないので、もともと現代劇である以上、平成の時代に再現するにはかなりの無理があるが、個人的には近年の映像化では、竹野内豊氏が主演を務めた2004年フジテレビ版よりも、清水有生氏が脚本を書き、東京最弱の民放地上波・テレビ東京の『女と愛とミステリー』枠の第一弾で、棟居刑事を渡辺謙氏が演じた『人間の証明2001』(2001年)を推したい。
戦後GHQ占領下の東京を、2001年から逆算して、渡辺謙氏の年齢の主役が、実際に少年期を過ごせた、1970年代序盤の「アメリカ統治下の沖縄」に置き換えることで、ドラマの基本構造を変えないという、見事な手品のトリックのような手法を編み出したのはこのドラマ版が最初であり、テレ東作品の分際で(失礼!)しっかりニューヨークロケまで敢行し、そのNYロケ部分の完成度と本筋融合度は、角川映画版よりも高かったというのもポイントが高い。

なお、1977年の映画公開時、「母さん、僕のあの帽子、どうしたでせうね」という詩の冒頭が流行語になり、既刊だった角川書店の『西條八十詩集』が、爆発的に売れ行きを伸ばしたという事実も、とりあえずここに書き記しておこう。