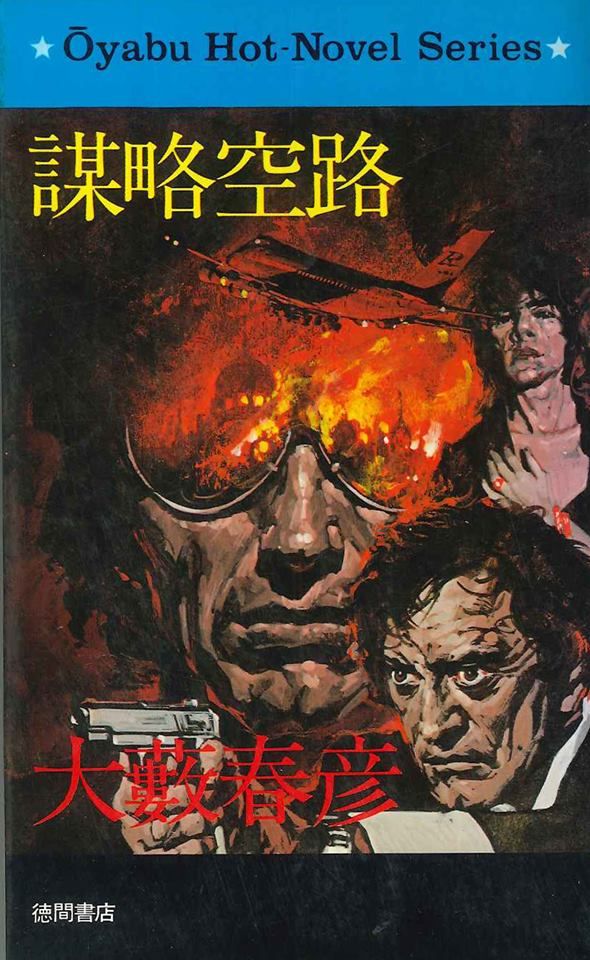このドラマはかつて早坂暁氏が1995年にNHKで脚本を書いた『刑事蛇に横切られる』のリメイクである。
早坂氏といえば勿論、社会派・ハード&人間派の脚本家として、主に70年代までのドラマシーンで『七人の刑事』(1963年)『鬼平犯科帳』(1969年)『斬り抜ける』(1974年)『夢千代日記』(1981年)等が代表作として挙げられる。早坂氏が直接執筆した1995年版を筆者は残念ながら観ていないが、その1995年版では高倉健氏が演じた「かつて愛妻を犯罪者に殺され、それを殺してしまった主人公刑事」を、『サラリーマン金太郎』(1999年)の高橋克典氏が演じて描かれた作品である事は前提の上でじっくり観てみる事にした。
高橋氏の脇を、大地康雄、柴俊夫、風間俊介等の「イマドキならでは」のバイプレイヤーで上手く囲むことで、あえて「現代に数字(視聴率)を取るには困難なテーマ・ハコ」のドラマを、硬質なまま夜のゴールデンタイムのコンテンツとして成り立たせていた。
テレビ東京はかつて2001年にも『女と愛とミステリー』枠のスタート時に、清水有生氏が脚本を担当した『人間の証明』で、シャープで硬質な社会派ドラマを放った功績が過去にもあり、むしろ昨今のTVコンテンツの惨状を前提にした時に、こういった「本当のドラマ」を送りだせるのは「NHKかテレビ東京か」の二択だけしか残っていないのかもしれないのが現状なのかもと思わせる「華はないが実がある」良い意味で現代的ではない作劇のドラマであった。
本作を観て思いださせられるのは、早坂氏が1975年に書いた『新・七人の刑事 永遠の少年』であろう。そこで描かれた「警察の銃を奪う犯人」「警察関係者が人質になって始まる立て籠もり犯罪」等が今回の作劇の根幹であり、それが過去のトラウマとして主人公に覆いかぶさるテクスチュアは、さすがの早坂節。
同時に「警察の人間として生きるが故の葛藤」や、「自分が殺したんだ」という自己批判が負のスパイラルを産んでしまい、他者と自己の境界線を越えてしまう作劇は、新シリーズの『七人の刑事』(1978年)で早坂氏が書いた『倉田平三巡査の夏』を想起させる。
こういった「早坂節」が(他者のリライトとはいえ)堪能できる企画がテレビ東京だという現実には、ある種の希望と危機感を同時に映像界は抱かなければいけないと強く思う。
一方。映像演出に目を移せば、パン屋や新聞屋での意味のない長回し1シーン1カットや、目的のないイマジナリーラインを割ったカッティング、同じアングル・カメラサイズのまま、急にカットが変わり時間が経過する、ドリーとパンニングの役割分担が明確化されていない等、基礎的な所で違和感が目立ち「気分を割られて」しまう演出が随所に見られた(クライマックス取調室での、いかにもなブラインドの照明演出のあざとさも含めて)。
監督は『プリズナー』(2008年)『レディ・ジョーカー』(2013年)の水谷俊之氏。
早坂氏の脚本をリライトしたのは、2001年にNHKで乃南アサ氏の『凍える牙』をドラマ化した坂上かつえ氏。物語展開的には、中盤での取調室での風間俊介君に(宛がわれた役自体は、少し「相変わらず」感は否めないが)その凄まじい演技力の頭角を初めて現した『3年B組金八先生』第5シリーズ(1999年)での、兼末健次郎役以来の凄味を見出す事が出来るし、それを受けて立ち回る大地康雄氏の演技もお見事で、そういう意味では十二分に芝居の裏打ちをする脚本と設定が光り輝く。