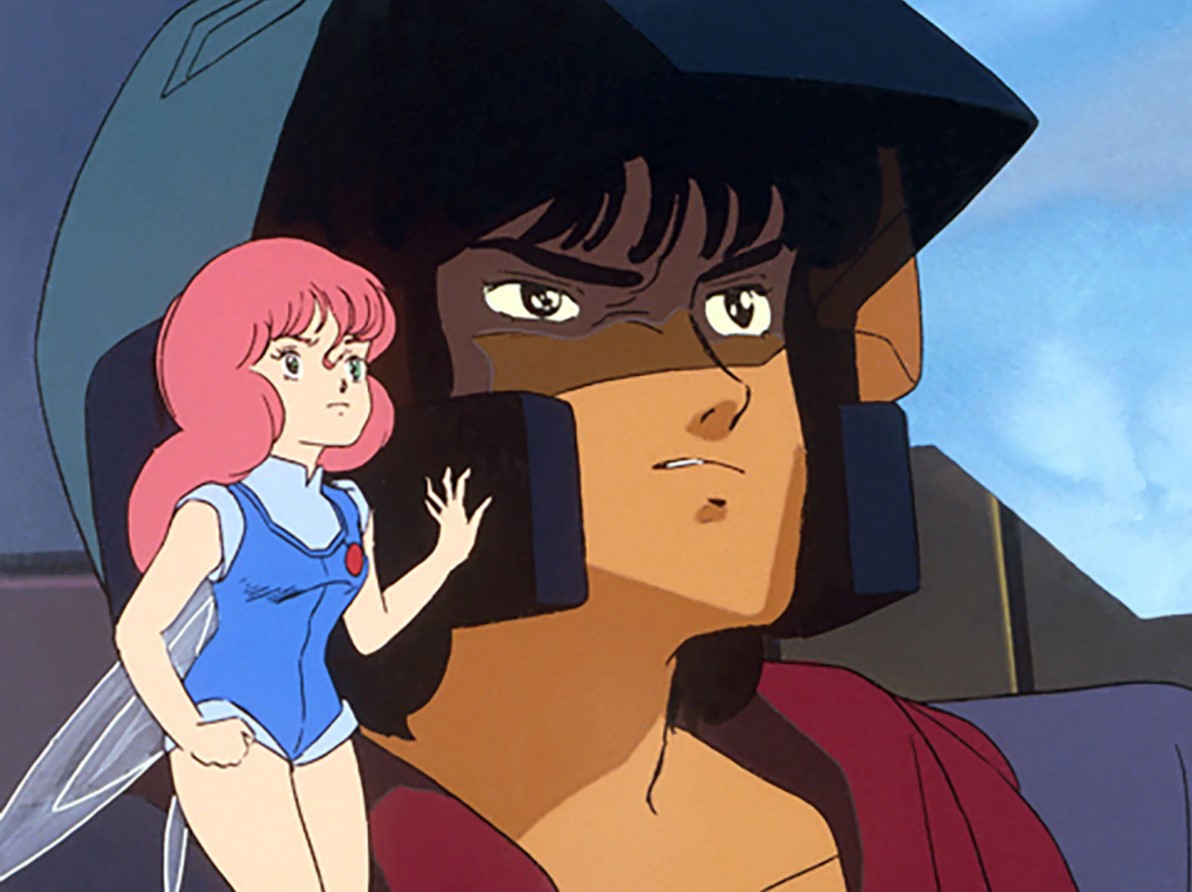しかし、脚本と演出の間に「妙な間合い」が感じられたのも確か。1995年から20年余りの間で、このテーマや作劇自体が現代的な表現と乖離したのか?
いや、筆者はむしろ「高倉健氏と高橋克典氏が、俳優として持ち合わせているポテンシャルとの相性」の問題ではなかったかと思わざるを得ない。
脇ではしっかりと、大地氏や風間氏が、求められたテクスチュア以上の能力を発揮しているだけにそう感じざるを得ない。
本作で感じた違和感を「現代で若い(という程高橋氏が若い訳ではないが)俳優でやる事に無理がある」というだけの問題には集約はさせたくないという気分はある。
むしろこの作品の作風やテーマ等は、近年では長坂秀佳氏辺りでしか拝めない方向性ではある(そう考えると本作での大地氏の役柄が『特捜最前線』(1977年)での大滝秀治氏にも思えてくる)。しかし、おそらく90年代に『刑事蛇に横切られる』での主人公の設定に触発されたのであろう、西荻弓絵女史の『ケイゾク』(1999年)で、渡部篤郎氏が演じた真山刑事の造形は、今見てもハッとさせられる説得力と重たさを持っている。
となれば、ここでの秋庭が抱えた人物像は、決して「現代には通用しない設定」でもなければ「若い俳優が演じても説得力が出ない設定」でもない。
要するに「過去に傷を持ち、その重たさに耐える日常を送りながらも、その魂と肉体には刑事としての闘犬の本能が染みついている」という、このドラマの主人公・秋庭はおそらく『刑事蛇に横切られる』では高倉健氏に対して「アテガキ」されていたものなのではないかと思われるのだ。
そういったキャラ造形は『野生の証明』(1978年)等以来、高倉健氏にとっては十八番の役柄とも言えたからだ。
そう考えると、今回主演を掴んだ高橋克典氏には「分が悪かったですね」としか慰めようもないのである。
「私は……妻を愛してた」
そう語り項垂れ、酒を煽る高橋氏のビジュアルから、これといった「重み」を受け取れなかったのも、むしろ当然であるといえる。
そもそもからして「あの早坂氏」が「あの高倉健氏」をアテガキした人物を、20年経って誰が演じようと、血肉を与える事など出来やしないという「壁」が、高橋氏にではなく「現代を生きる我々」に立ちはだかるのだ。
微妙な按配で「企画を組んだ意気込みと実行力には敬服する『が』」と「が」を付けざわざるを得ない出来に落ち着いた『刑事』。
願わくば、今の「TVコンテンツ冬の時代」に「こういった企画」を送り出した心意気と意欲性だけは、否定しないで邁進してほしいと願うのだった。
「君は三上だろう?」
そう言われた瞬間の風間俊介君の「凄味」の演技こそが、早坂暁氏の筆が生み出した『永遠の少年』という題に被り、ここに帰結を確認する事が出来たのである。