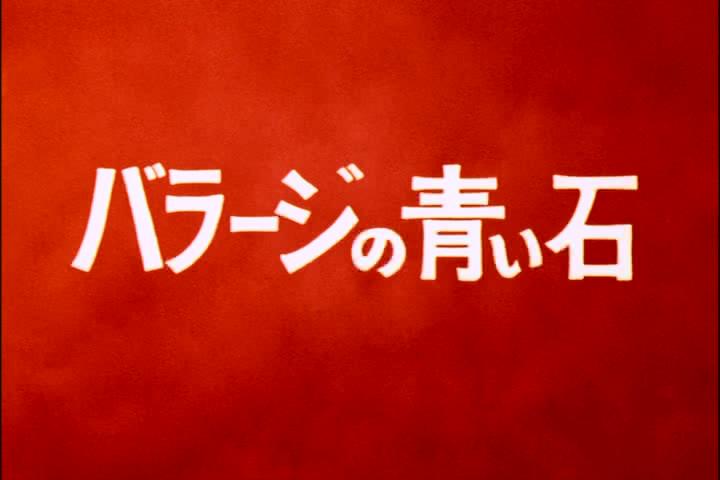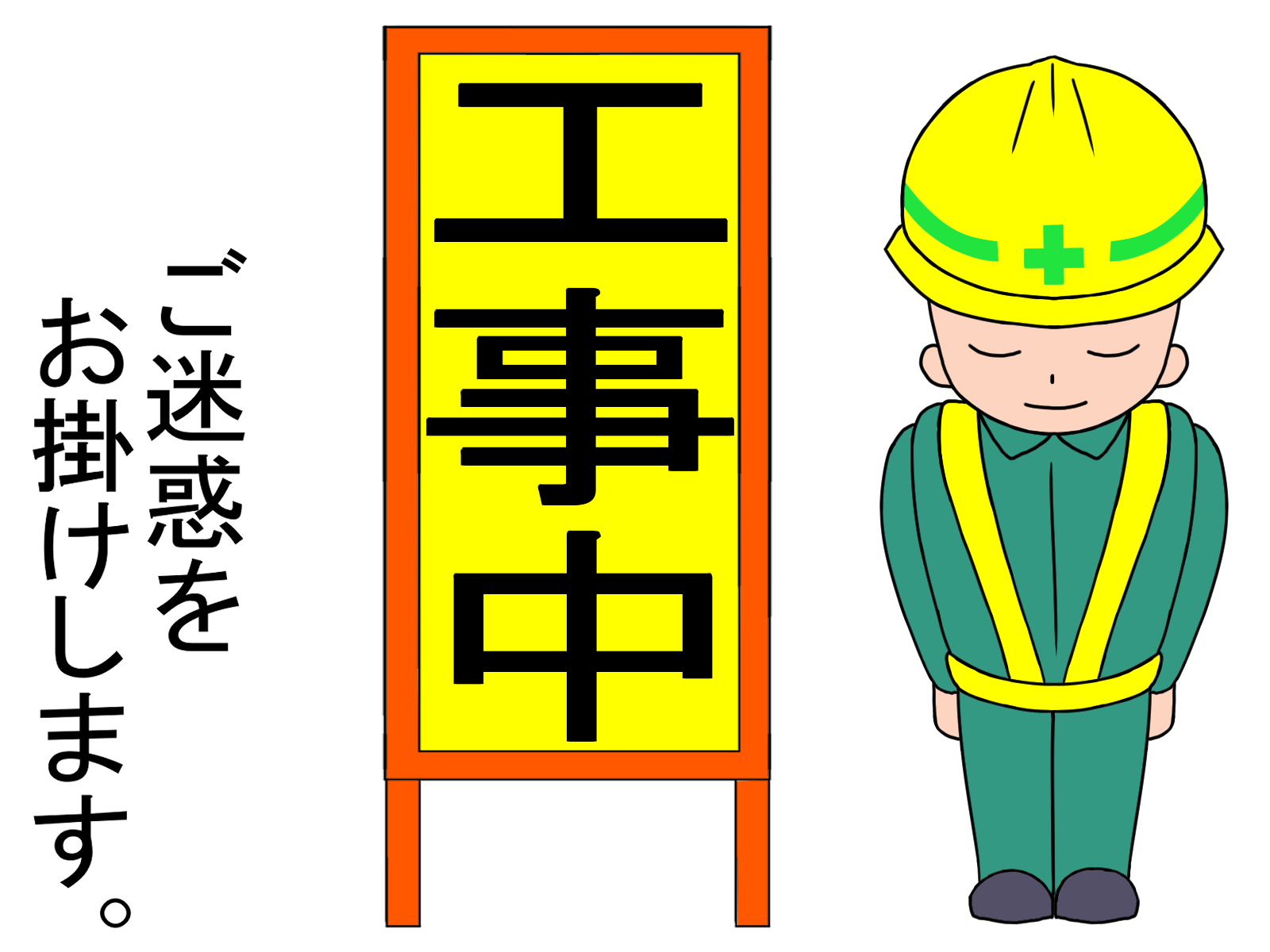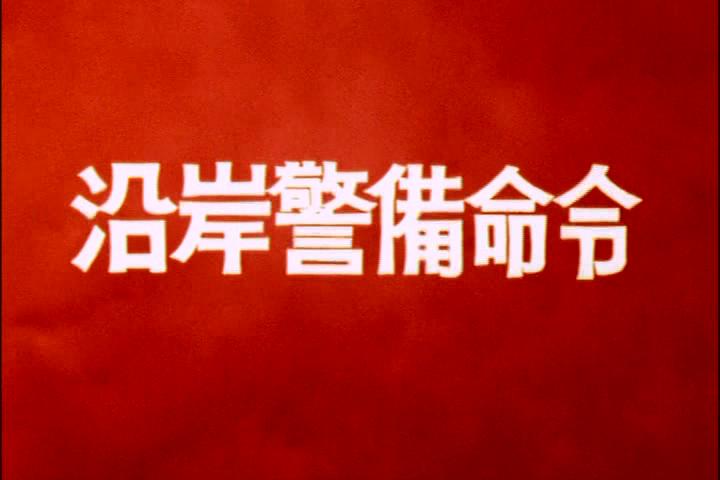そこでは徹底して、女性が生命力の源であり、生命の神秘の根源を理解できる存在であり、男はそれを守るのが務めなのだと、そこを軸にしてこの映画の人間ドラマは展開される。
(この部分は、明快な台詞や言葉等で安易に語られることはないが、シリーズを通じて、必ず怪獣と対になって女性キャラが配置されることで明確化する。
その際、新登場するレギオンやイリスに対しては個別に新たな女性キャラが設定されるが、三部作共通して、ガメラに対しては藤谷文子が、ギャオスに対しては中山忍が、それぞれ、対応する怪獣が登場するたびに作品内に配置されている)
「その真理」が社会の縮図そのものであり、それを機能させていくことが本当の社会なのだと、この映画は、怪獣映画としてレベルが高いだけでなく、社会シミュレーション映画としてもその「本来社会はこうして機能していくのだ」を、高度な娯楽作品の枠の中で、冒頭からラストまで描き続けた。
「そんな原理原則論が崩れた社会だからこそ、『怪獣』などという未曾有の非現実的怪物が、襲い来るようになってしまったのだ」という、現実認識論まで含めて、この作品は、高次元で成り立っているのだろう。
ガメラとギャオスはそれぞれ、出現地点から福岡ドームで合流し、ギャオスはリアルタイム進化の恐怖を見せながら、ガメラは出自の神秘を段々にあらわにしながら、やがて対決地点を岐阜へと移し、最終的に(そこはやはりケレンミとして)首都・東京での最終決戦へとなだれ込んだ。
そのプロセスで、怪獣映画が好きで好きでたまらないことが、こぼれんばかりに見える、金子監督による「恐怖と正義の、それぞれの象徴である怪獣を前にした人間」が、明確な演出テーマとして、絞り込まれたために、雑然とした「怪獣映画の膨大な情報量」に、物語が飲み込まれなかった力強さを持つ。
一方脚本では、本シリーズ担当の伊藤和典が『機動警察パトレイバーシリーズ』(1988年~)の初期OVA版第3話『4億5千万年の罠』や、同じく第5話・第6話『二課の一番長い日』や、特に劇場映画版『機動警察パトレイバー 2 the Movie』(1993年)で顕著に描いた「特定の状況下において、殆ど多くの一般市民はその状況に対しては、テレビ報道等のメディアを通じて認知を行うものであり、むしろ、メディアがどのように状況を報道するのかを描くことがリアリティに繋がる」を、この作品はおそらく実写で初めて、徹底してやってみせた映画でもある。
そこで、あえてアニメ畑の樋口監督が招かれて、担当してみせた特撮演出もまた(これは公開当時からよく言われたことだが)自衛隊の発射火器や怪獣の描写で、アニメ的な構図や絵コンテ演出を持ち込んだことや、オープンセットの不利さ加減を、あえて低いカメラアングルに徹底することで、リアリズムへ転換する手法の潔さなどで、むしろゴジラシリーズにはない、リアリズムや独自性を打ち出すことに成功した。
結果、その金子&伊藤&樋口トリオが産み落とした「ガメラならではの独自性」は、まだまだ「この時点」では「平成の日本映画界において、特撮怪獣映画を作る際のコロンブスの卵」に溢れていて、それらは(当時の)「怪獣映画の限界と現状」だと(作る側にも観る側にも)受け止められていた、平成ゴジラシリーズへの、良い意味でのカウンタウェイトとして、アンチテーゼとして働きかけ、結果として、当時既に途方もない現実(平成ゴジラ)の前に諦めかけていた「本格怪獣映画ファン」をして「コレですよ、コレコレ(『孤独のグルメ』調)」と、喜ばせ、唸らせたのである。
今回前半部分でも書いたように、年を同じくして円谷プロもまた、『ウルトラマンティガ』(1996年)を製作開始。後の2000年になる東映・石森プロ『仮面ライダークウガ』におけるライダー復活も含めて、特撮ファンは、文字通り華の時代を迎えようとしていた。
この、時ならぬ「往年の百花繚乱特撮黄金時代の再現」に、特撮ファンは浮かれまくり、『宇宙からのメッセージ』(1978年)も『さよならジュピター』(1984年)も忘れたかのように、ようやく訪れた「安堵と至福の時」に浸ることになった。
しかし、歴史は常に縦軸に沿って歩まされているわけであり、決してそこで、何か奇特な傑作が突然変異のように登場したからといって、数十年の歴史の積み重ねが遡って上書き変更されるわけではない。
いつの世も、歴史は常に「必然」で」埋め尽くされているのだ。
確かにこの『ガメラ 大怪獣空中決戦』は、マニアもオタクものみならず、大人も子どももお姉さんも(by糸井重里)魅了するだけのエネルギーと普遍性を持った「誰もが思う『怪獣映画』の魅力」に溢れていた。それは一級の娯楽作だった。
しかしその一方で、金子&伊藤&樋口のガメラトリオが、「これが第一作だから」「これで失敗するわけには絶対にいかないのだから」と、それぞれのやりたいことの「個」を抑え、プロに徹していたことも確かだった。
確かに、金子も伊藤も既にプロの監督・脚本家であったし、樋口もまた、アニメの演出でプロ現場の経験は積んでいた。
しかし「怪獣映画」という企画に、本格的に参加するのは三人とも初めてであった。
そうなると、三人が三人三様に息を合わせるためには、三人が既に既知として共有している「これぞ怪獣映画」という概念論が前提として、機能しなくてはいけなかったわけだし、それゆえこの作品は大傑作となった。
しかし、古今東西を問わず、一つの映画が大ヒットすれば、資本家や関係者は当然「続編を」と望むし、挑もうとする。
そうなれば、シリーズとして独自に存続させていくことが次のミッションになれば、そこでトリオが考える、いや考えるべきは「ガメラシリーズならでは」の配置だった。
エンドユーザーが『ゴジラ』ではなく『ガメラ』を選ぶエクスキューズ。
選ばせるための魅力の誘導。
そう考えていった先で、このガメラトリオがそれぞれに、その特色・独自性として抱くことになった三大要素が「少女と怪獣(「怪獣と少女」では決してない)」「リアルではあるが、有能過ぎて粋にかっこ良過ぎる自衛隊」「『ガメラが真に守るのはあくまで地球であって、それは決して人類ではなく、人類が地球の環境の敵になったときは、ガメラは人類を滅ぼすかもしれない』というガイア思想のテーマ」以上の三つなのだが、実はそれらのバランスが高次元で融合していたのは、実はこの初作だけであったりするのも事実なのである。
もう少しダイレクトに語ってしまえば、金子も伊藤も樋口も、それぞれに「なぜ『ガメラ 大怪獣空中決戦』という、マイナーなB級作品のリメイク低予算バジェット映画が、このタイミングで、一般社会にまで名を響かせる娯楽作品として評価されたのか」そこへの自己検証が、とてもおざなりで我田引水で、むしろ「それ」をやったように見せつつも、実際は「自分が次に何をしたいのか。本当は『怪獣映画』という企画を与えられたのなら、何がしたかったのか」にしか、目を向けていなかったからではないだろうか。
そして「それ」は、個々にコラボレートを目指さずに構築されていった結果、むしろ平成ゴジラシリーズよりも早い段階で、醜い形で「不協和音」を露にすることになるのだ。
次作『ガメラ2 レギオン襲来』(1996年)では、まだ徐々にではあるが、その「不協和音の正体」が、見え始めるのである。