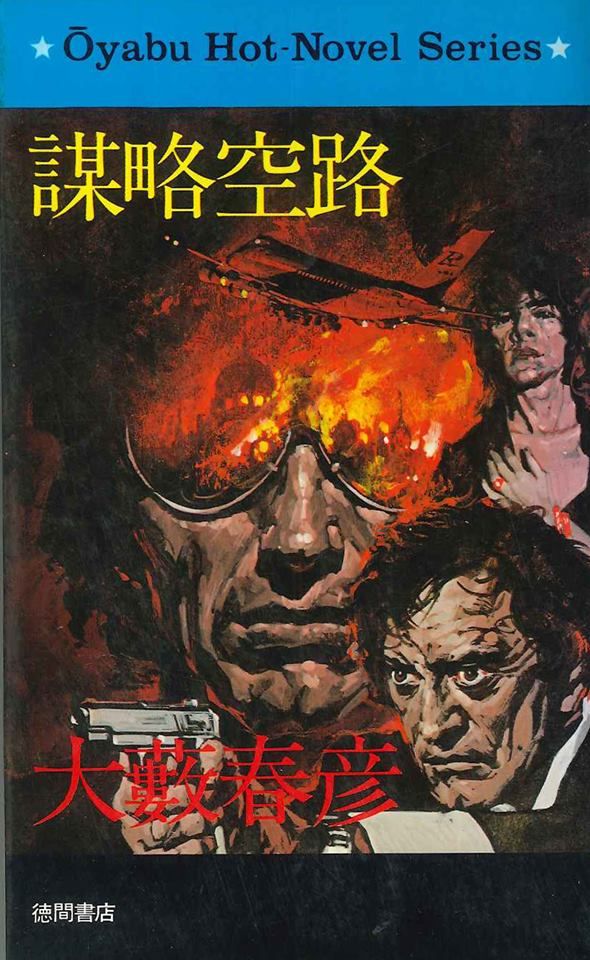『虐殺器官』の巻末に寄せられた大森望氏による解説文の、伊藤氏闘病の記録では、その最後において、それまでどんな病状でも茶化してミクシィ日記で書いていた伊藤氏が、あらん限りの醜さと、なりふり構わない物言いで綴った「泣き言」が転載されていた。
それをどう受け止めるか、それはそれで、読んだ人全てがそれぞれに違うだろう。
現実は『世界の中心で愛をさけぶ』や『余命一ヶ月の花嫁』『100日後に死ぬワニ』とは違う。
人は、自分の死を目前に実感してまで、スタイリッシュにはそうそう生きられない。
亡くなった方々を愚弄する気はさらさらないが、僕が尊敬してやまず、しかし闘病の末に逝去された方々がいる。
松田優作、佐々木守、筑紫哲也、忌野清志郎、市川森一、上原正三。
彼らはとても凛として、スタイリッシュにその最期を生き抜いたとされているが、それはおそらく、故人の名誉を守るべき家族や周囲によってひっそり仕舞われているだけで、病気の発覚から最期の瞬間までを、全てコンセントレーションを保ち生き抜いたわけではないと思う。
死という「おぼろげに予測し、免れないものだと頭では理解しながらも、現実の毎日ではリアリズムを持って向き合いはしなかったもの」が、ある日を境に、自らにとって(ある種のタイムリミットを伴って)切迫した「現実」になる。
この不安と恐怖は、今その立ち位置にいない人には分かれというのは無茶があるし、それを共感できないからこそ、人が狂わずに生きていられるというメカニズムもあるのだ。
伊藤氏の、死の間際のミクシィ日記(正確にはその一説)を読んだとき、自分よりも一回り下の年齢で、この世を去らねばならない天才の、口惜しさと不条理さを感じざるを得なかった。
そしてまた、まだまだ自分は甘い環境にいるのだろうと感じた。
世に言われる天才の中には、没後はじめてその才能や作品を評価された芸術家もいるが、伊藤氏の場合、まだしっかりと、自分が生きている最中に『虐殺器官』が評価されたことは、極めて僥倖だったことなのだろう。
しかし、幸か不幸か、僕自身はまだ何も、文壇史に残るような、ベストセラーも受賞作品も出せていない(「単著を出したことがないプロの物書きなんているわけない。似非ライターだ」と、自称業界通の「厄介さん」が必死に叫んでいたことがあったが、アレを読んだ僕の周りの「普通にプロのライター」は、皆声に出して笑っていたが、2020年ようやく単著を上梓した。しかしその「厄介さん」は僕を「似非ライター」と呼び続けている)。
だから僕自身は、自分の死後に自分の仕事や表現が再評価されるようなことなど、ゆめゆめないのだろうと、それぐらいを察する程度には「急性心筋梗塞一つで、死線をくぐった自称英雄」よりかは、現実が見えているつもりである。
だとすれば。
今現在から、明日か、来週か、来年か、数年後か、「その時」が来るまでの間に、僕はなんとしてでも「僕にとっての『虐殺器官』」を、書き残しておかなければいけない。
そのためには、僕が守り続けてきた、貫いてきた僕の生き方を、今更まげて修正して、微調整してチューニングしているインターミッションの暇など、どこにもないのだよ。
だから今は、自分で自分に言い聞かせるしかない、伊藤氏への想いも込めて。
不撓不屈。