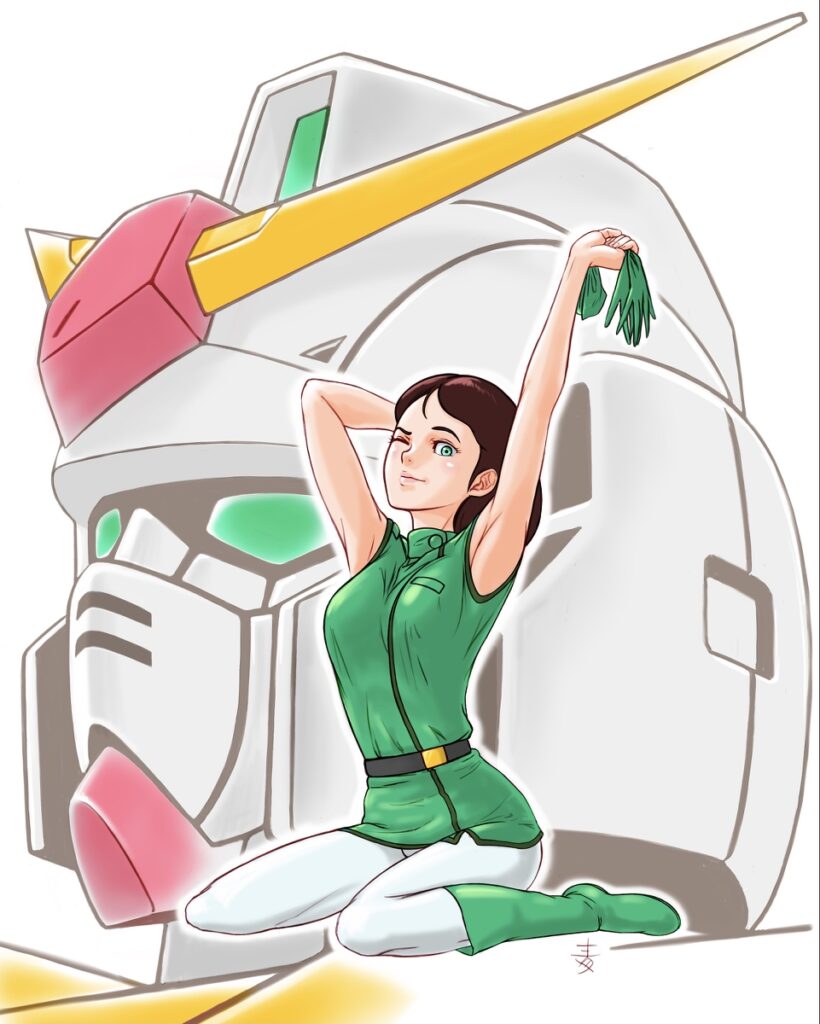続く、第3話『さらば愛しき魔女』評論では、いくつも「言われなければ視聴者は気が付かなかったが、確かに言われてみればおかしなことばかり」の展開の中、「なぜ謎の研究は“第三の太陽”と呼ばれたのか」「そもそも、その力を宿したというリンダは、なぜ魔女と呼ばれなければならなかったのか」「というか、魔女が魔女たるエクスキューズが劇中に一つも描かれていない」という謎の中を
この『さらば愛しき魔女』と名付けられた物語が、チャンドラーではなくフレミングの世界の模倣であることだ。もっと正確に言うと、原作ではなく、映画『007/サンダーボール作戦』に酷似している。共に南海の孤島を舞台とし、無国籍の犯罪組織が登場し、潜水姿での水中白兵戦が行われ、ルパンの色事師ぶりが強調されること、ルパンの銃を撃つポーズがボンドのそれを真似ていることなどでそれは証明される。脚本では、今回のみルパンの愛車がボンドと同じアストン・マーティンになっているのだ。
『まぼろしのルパン帝国』高橋実
と、鮮やかに読み解かれれば、ウムと頷かざるを得ない。
『007/サンダーボール作戦』(1965年)をパスティーシュ元に求めるのであれば、そこで争奪戦が起きるアイテムはただ一つしかないのだ。
だから、そういった説得力と、実証された裏付けがある上で「第三の太陽」=リンダの存在を
つまり、<第三の太陽>の“太陽”とはエネルギーを意味する。第一の太陽が人力をさすとすれば、第二は火力、そして、第三が原子力である。ここで“魔女”はそのエネルギーの肉体化である。魔女が白魔術と黒魔術という正邪の二つの顔を持つように、原子力も原子爆弾と原子力発電という明暗二つの顔を持つ。
『まぼろしのルパン帝国』高橋実
と解き明かされても、もはや何一つ反論できないレベルの鮮やかさと明確さを本書は示してくれる。
それは本書のサブタイトルにもなった「まぼろしのルパン帝国」という存在への言及にも顕著で、そもそも大隅監督が創造した当初の『ルパン三世』とは、アルセーヌ・ルパンの孫であり、先祖から託された「ルパン帝国」を率いざるを得なくなった、新宿のブルジョワフーテンだったルパン三世が、その天才ぶりと、組織の恐れ多さと巨大さゆえに、毎回送られてくる様々な刺客や暗殺謀略相手に、「粋にやろうぜ。粋によう」とばかり(この台詞は大隅監督版ではないが)、相棒の次元と共に、シラけたモチベーションでどんな危機も潜り抜ける主人公として想定されている(DVDか録画映像をお持ちであれば、第1話『ルパンは燃えているか』をご覧になるといい。その企画の名残として、ルパンと次元の「起死回生をもくろむ作戦会議通話」の出だしからして、なんとものんびりしたBGMが流されている)。
本書で高橋氏は、そんな大隅ルパンを
「夢を見ないルパン三世」「ピカレスク・ヒーローとしてのルパン三世」「ハード・ボイルドヒーローとしてのルパン三世」「“アンニュイ”なるルパン三世」「“意味のない”“無思想の”ルパン三世」
『まぼろしのルパン帝国』高橋実
こう、因数分解して解析している。
安保闘争が敗退に終わった70年代初頭。大隅監督は自分がやはり前半だけ手掛けた『ムーミン』(1969年)のスナフキンのような存在として、浮世の全ての憂さやストレスを嘲笑する、究極のAnarchistであり、無気力の天才を描くことで、子ども向けとしてしか認知されていなかったテレビアニメの世界に、風穴を開けたかったのだ。
初動では、ルパンは上に挙げたような存在だった。次元はルパンの傍に寄り添う同性愛者的な女房役であり、五右衛門は保守文化とアメリカ文化の融合によって生まれた(本書第5話『十三代五右衛門登場』解析より)戦後世代、アプレゲールの象徴であり、俗物的な日本人像の典型であった。銭形は民衆の自由を監視して権力で奪い去ろうとする、公権力の象徴だったし、不二子は、ルパンにとっての純愛の対象でありながら、女性原理で生きる「絶対悪」の存在だった。
しかし、斬新すぎる天才(大隅監督)のアンニュイさは、社会という権力者の構造からは排斥される。
TV版『ルパン三世』は、初動で大きくヘマをやらかした。数字が全く取れなかったのだ。
その結果、シリーズの全ての権限を握る監督が、Anarchist(大隅正秋)から左傾派文化人(宮崎駿)へとバトンタッチされた。
高橋氏の著書の中で、宮崎駿氏の記述が引用されている。
旧ルパン路線の変更は、スタッフのあずかり知らぬところから強要されたものだったが、演出を入れかわるハメになったぼくら(高畑勲と私)は、まずなにより“シラケ”を払拭したかった。命ぜられたのではない。(中略)快活で陽気、まぎれもなく貧乏人のせがれ、ルパン。祖父の財産など、先代がぜんぶ使っちまって、何も残っちゃいない。ルパンはクルクル走り回り逃げ回り、カナブンのような銭形が追う。何百万丁も生産された軍用拳銃(ワルサーP38)をもってイキがったりしない。知恵と体術だけで、あくことなく目的を追うルパン。次元は気のいい朗らかな男になり、五右衛門はアナクロこっけい男になり、不二子は安っぽい色気を売り物にしない。
『まぼろしのルパン帝国』高橋実
その好悪は別にして、ベンツSSKに乗るルパンと、イタリアの貧乏人の車・フィアット500に乗る二人のルパンが、あのシリーズの中で対立し、せめぎあい、影響しあって、結果として活力を作品にもたらすことになった。(引用者註・宮崎駿談)
そう。確かに『カリ城』のルパンは、フィアット500を乗り回し、ワルサーP38を一発も撃つことなく(撃とうとしてわざとレーザーで焼かれて終わっている)、娘のような少女を助ける義賊としてのみ描かれていた。
本書では、第13話『タイムマシンに気をつけろ!』から最終回『黄金の大勝負!』までを、アンソロジー以外の部分として、不二子とルパンの結婚、そして新婚旅行から、夫を尻に敷く気丈夫嫁さんになるまでとも読み解いているが、その読み解きの延長で行くのであれば、『カリ城』での不二子は「娘を救おうと必死に手を焼く夫を、影で支えながら、子離れできない夫に冷や水を浴びせるマダム」といった、まさに「古女房」の役どころではないか。
もっとも『ルパン三世 カリオストロの城』は、監督自身も、これを評するほとんどのアニメ評論家もマニア諸氏も、口を揃えて言うように、これは宮崎監督が、職人として自身の過去の東映動画時代の仕事や、1st『ルパン三世』の設定やギミックのリファインで練られた仕事であって、なんらクリエイティブな部分は見当たらないのであるが。
それでもコンテンツの出資者やテレビ局や資本家は、「ルパンといえば『カリ城』」幻想にしがみついたまま30年を過ごしてきた。
ひょっとすると、80年代以降、日本人がテレビやスクリーンで見させられてきたルパン一家は、宮崎監督がTV第2シリーズ『ルパン三世』(1979年)最終回『さらば愛しきルパンよ』で当初やってみせようとしたように、「赤い背広を着せられた、ルパンと似て非なる偽物」なのかもしれない。
1stシリーズ最終回。永遠の追いかけイタチゴッコを続け、とうとう海での大遠泳にまで突入したラスト。逃げ泳ぐルパンたちを追って泳ぐ銭形が「馬鹿め! そっちはアメリカだぞ!」と高笑いすると、ルパンはしれっと言ってのけた。
「ほんじゃあ、中国へでも行きますかねぇ?」
『ルパン三世』『黄金の大勝負』
ある意味、フランス映画的・フィルム・ノワール風味で始まった1stの『ルパン三世』が、第2シリーズからは、ド派手なアクション重視、サスペンスジェットコースタームービー嗜好のハリウッド映画的へと変貌していった流れは、やはり1st最終回の台詞を深読みすれば「アメリカナイズされて戻って来た第2シリーズ以降は偽物で、本物はもしかしたら中国へ去ったのかもしれない」と思い起こさせてくれる。
“中華思想”っていうのがあるでしょう。すべての源泉は中国にあるんですよ。なんでも、ロケットも天文学もすべて中国で作った。だから中国は、なにも外国のまねをする必要はないし、メンタルには非常に誇りの高い人たちですからね。それにくらべると、日本は民衆レベルで外国に非常に関心をもってきたといえるんじゃないかな。(引用者註・大塚康生氏 談)
『まぼろしのルパン帝国』高橋実
だからこそ、大隅正秋監督が産み落とし、宮崎駿監督が受け継いだ「ルパン三世の粋」は、日本を飛び出ていった先で、アメリカではなく中国を選んだのかもしれない。
筆者が紹介させていただくのはここまでにするが、本書はかように、1971年に23本作られた、映像作品としての『ルパン三世』を、多少行き過ぎに前のめりになりながらも、かつてない、今のネットのお行儀のよい立証主義にはない、熱意と探求力と推理力で、様々な「作品の奥に存在する核を、切り取り分析して、論として改めて組み立てる」を実践した一冊である。
『ルパン三世』はなぜ面白かったのか。なぜ1stだけが今もなお輝き続けているのか。そこでの“なぜ”が全て、1971年という時代の瞬間と、二人の偉大な演出家の対立に起因していたのだという事実を、知れる一冊である。