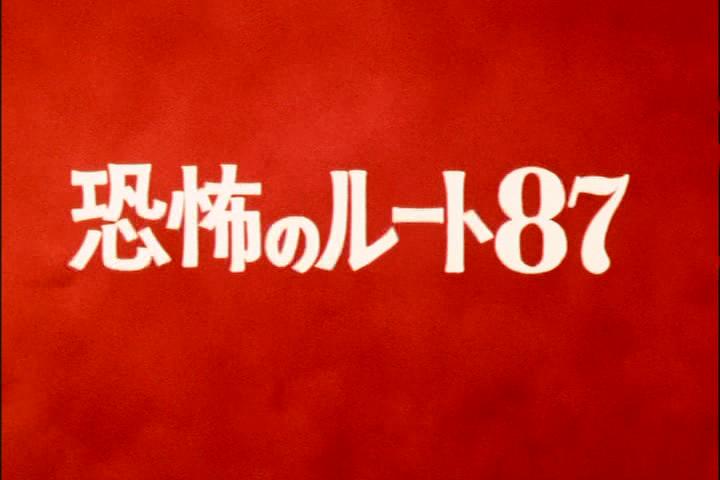余談になるが、これの前例を上げるのに、ちょうど良い実際のコンテンツ例がある。共に東映アニメと雑誌連載漫画で男児、女児にとって社会現象的大ヒットを生んだ、『聖闘士星矢』と『美少女戦士セーラームーン』の対比だ。
企画とヒットは『聖闘士星矢』の方が先だが、そちらをモチーフ元にして「原作は少年漫画雑誌で連載中の漫画作品。天空の星々を象徴とする戦う少年たちが、まずは5人で集まる(当然、主人公はその真ん中。しかし、主人公と同格、もしくは別格と見える戦士が、5人の中にもう一人配置されている)。その中心には、逆に一人の美少女がいる。5人はそれぞれ、自分が象徴とする天空の星ごとに属性の違う技を使って、次々と襲い来る悪と戦い、互いに助け合い、友情の下で力を合わせて敵を打ち砕く。主人公少年と美少女は、運命で惹かれ合う。シリーズが進むたびに、どんどんサブキャラが追加されていき、敵もインフレーションを起こしていくが、毎回ここぞという時には、戦う時に身にまとうコスチュームが奇跡を起こし、主人公はどんな状況からも大勝利に持ち込める」と、骨子を抽出すると、それをそのまま「少年」を「少女」に、「美少女」を「美少年」に置き換えるだけで、『美少女戦士セーラームーン』の企画はほぼ(大まかな骨子部分では)出来上がってしまう。
これを、見立て元を『聖闘士星矢』から大藪晴彦ピカレスクロマンに置き換えて、同じように性別を入れ替えた実験を、東野氏が行った結果が、『白夜行』なのだ。
あえて論を中断させ、ここで再び『白夜行』本編の解説に戻れば。
主人公少女・雪穂の物語と、関係が全くつかめない「影」の少年・亮司の物語は、まさに光と影のように交わることがなく進んでいくが、その先で雪穂が社会的成功を求め動くようになると、資金調達、人間関係、恋愛、結婚、離婚、DV、レイプ。様々な事件や僥倖が、毎回奇跡のように雪穂の身に起き、そのたびに雪穂は「社会的成功」へ向けて、ステップアップしていく。なぜ、そんな事が起き得るのか? 偶然なのか? それとも、雪穂が何かをしでかしているのか? それとも「影」の少年がそのまま大人になって、雪穂の為に暗躍しているのか? だとしたら何のため? しかも、次々に起きる事件は、雪穂一人でも亮司一人でも、出来るレベルのことではない。物語は、二人のそれぞれの歩みと行動の描写を行き交い、接点があるように見えつつ、しかし明確にはつながらないあやふやさを演出しながらも、クライマックスへ向かっていく。
その中で、二人を追いかける刑事・笹垣がいた。
笹垣は、物語の冒頭の事件から関わっていて、その中で、二人の少年少女に対して、奇妙な違和感を抱いていた。
ここでも、ミステリーという枠で読み解くのであれば、彼が名探偵役を仰せつかるわけなので、そういった外枠部分では、きっかけの事件があって、密室トリックをはじめとして、物語が進むうちにどんどん謎が蓄積していき、伏線が張り巡らされて、それを事件当初から追いかけてきた人物が、名探偵役として全ての謎を解き、クライマックスに全貌を読み解いてみせるという構造においても、東野氏は律儀にミステリーの条件の中で、この物語を収めようとはしている。
しかし、仮に物語の全てが幕を閉じても、表側で散りばめられた謎の全てが、名探偵によって解き明かされようとも、東野文学は「あえて」すっきりしない後味を残し、完全な着地を見せようとはしない(この辺りは、デビュー作『放課後』から変わらない作風)。
結局、雪穂と亮司はどういう絆で結ばれていた関係だったのか? 白夜とはなんの意味があったのか? 雪穂はその時々に、何を考えて、何を求めていたのか? 読後も膨大な謎が、読者を包み込み続ける、『白夜行』とは、一言で言えば「そんな物語を、あえて目指した作品」なのだ。
まず一つ、それらを解くキーワードになるのは、筆者がこれまで、東野文学について散々語ってきた、東野小説の最大の欠点であると同時に、最大の魅力でもある点。「オンナノコッテワカラナイ」。これがまずベースにあるのだ。
だから、劇中で雪穂が、こちらからは理解不能な行動や策略をとっても、その「こちら」は、書いている東野氏視点で固定されているのだから、どう頑張ってカメラを覗き込んでも「うん、雪穂の考えがよくわからない」になるのは道理なのだ。
加えて、ここまでの書評やコラムで何度も主張してきた通り(大藪晴彦文学がそもそもベースにしていた)hard-boiledという文芸手法は、「いちいち主人公の心情や本音を、自分から語らせない」が鉄則なのである。
作者からしてみて、最初っから「分かるわけないよね。だって僕はオトコノコなんだもん」で割り切られてしまっている「少女主人公」が、「hard-boiledというカテゴリへの帰属性」のために、何があっても心情を吐露しない、本音を見せないという前提で、冷徹に、ロジカルに、ただただ(大藪ヒーローのように)社会的名声と地位と金だけを求めて動いた場合、果たしてその「少女の姿をしたモンスター」は、読者の共感などを得られる存在として、受け入れられるのであろうか?
そこにはそもそも「屈強で拳銃やメカに詳しい、60年代のタフガイ」ならともかく、いくら鋼のメンタルを兼ね備えているからといって、イマドキの若いお嬢さんが、大藪ヒーローレベルの、カタルシスとクレバーさを併せ持った、社会を真っ向相手にした時の戦いなど、出来るのであろうかという部分への懐疑は、これはもっともな疑問なのである。
しかしそこでも、筆者などからしてみれば、ここまでの東野小説文学の核として認知していたのは、彼は「オンナノコッテワカラナイ」でブラックボックス化させるだけではなく、そこで「なぜ男はそれを、分かってあげられないのか」への、エクスキューズとして、「男の弱さ。脆さ。ダメなところ。間が抜けているところ」を、これは流石に、当代きってのベストセラー推理作家だけあって、とことん知り尽くしているのだ(だからだろう。hard-boiledとピカレスクロマンの両立を目指して、周到に「理解不能な存在」としての装飾を配置していった中で「それでも、雪穂が抱いた白夜への想い」だけはかなえてやらんと、ただひたむきなまでに、自己犠牲で生き抜ける、亮司という「オトコノコ」という存在を、読者に共感させるための、要石として配置しておいたのが、東野氏の計算力であり、その限界であったのだろう)。
そう考えれば、全ての野望達成は、それだけであれば最初から最後まで、雪穂一人で達成できていた可能性だって高い。
それなりの、魅力を持った女性が、自身の身体とセックスと「恋愛心」をカードとして切って、目的やミッションを果たそうと思えば、昭和を席巻した大藪ヒーロー達が、苦しみ鍛え、磨きぬいたどんな「暴力」よりも「詐術」よりも、いとも簡単に、男性(に限る、この場合では)ごときは、傀儡のように意のままに操れ、自由に出来るのだという法則性に関しては、最近は筆者も実生活の中で、巻き込まれないように気を付けながら、冷静に目の当たりにしていたりはする「浮世の因果」であったりはする(笑)
しかし「その実験手法」だけでは、「作品」は「文学」にならない。
考えてみよう。
「理解不能な生物」が「理解不能な感情と動機」で「謎に包まれたアクション」を起こし、それがいつの間にか「次々と成功への階段を昇っていく物語」など、これははたして、もはや文学と呼べるものではない。
重ねて言うなら、もちろん東野氏は一流の作家でもあるので「hard-boiledとは文体ではなく『主人公の心情を描かないスタイル』のこと」など分かった上での執筆であり、それを貫くだけの判断力と技量があったのだ。
「理解不能な生物の感情と心情を描かない」では、ピカソの抽象画以上に、なにもかもが難解過ぎて、文学も娯楽もその要素を満たせない。
かといって、それら全ての発端となった事件。
アレを先にネタバレしておけば、その後の雪穂と亮司の生き様も、心情を描写せずとも文学たり得ていたのかもしれないが、それではミステリーの様相を保てない。
皆さんも聞いたことがあるだろう。「誰が思いついても当然で、しかし誰もやったことがない斬新なアイディアとは、既に誰かがとっくに気が付いていて、しかし上手くいかないことを、分かっていたからだ」という定番の法則を。