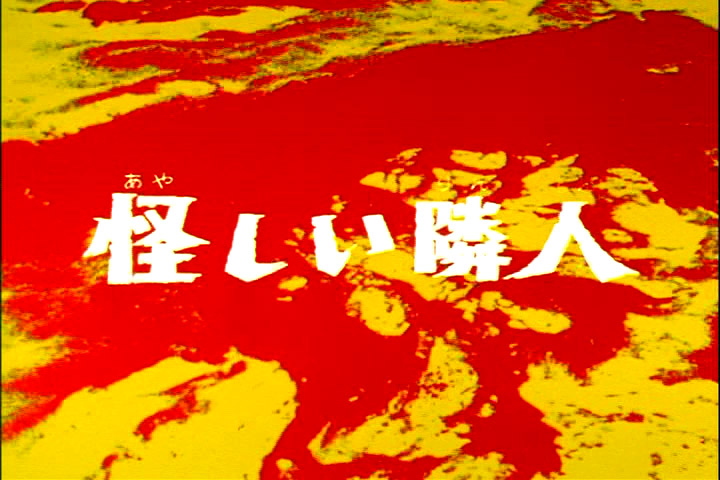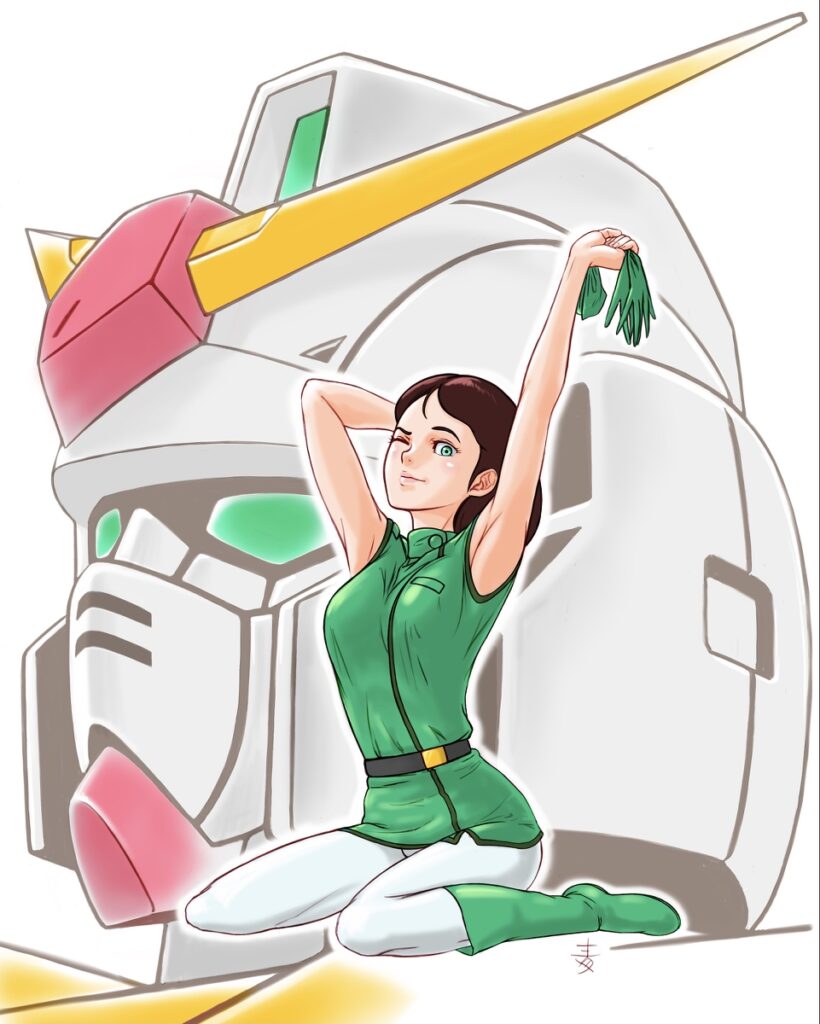「この場合」も、そうであったのだ。
「女性で大藪ピカレスクロマンでhard-boiledを」は、その着想自体が素晴らしいものの、労力をかけてやってみせても、あまり期待する仕上がりにはならないと、分かっているからこそ、過去に誰も表立ってはやってこなかったのだ(皆無だったとは言わないが、無理がある着想だっただけに、今ここで例示できるほどには、ヒットした前例がないということである)。
しかし、東野氏はこの作品を「まず、ミステリーであること」を、自分に律して構築していった。
「小説の中で頻出する謎は、全てはこれは、雪穂と亮司の、白夜の中でしか成立しない“愛”の帰結なのだという回答まで、読者が辿り着いてくれる」と信じて。「オンナノコッテワカラナイであったとしても、その分、亮司という『白夜に晒された影』の念や愛、行動を伏線にすることで、最後に全てが結びつくように」と。
東野氏が、ここで掲げた挑戦は、むしろミステリーとしての体裁をもっと明瞭にして、hard-boiledでもピカレスクロマンでもない、本格推理にジャンルを移行して書かれた『容疑者Xの献身』で、完全無欠な作品として、その実験の完成形を見ることが出来るのである。
一方、少なくとも『白夜行』はベストセラーにはなった。2000年には第122回直木三十五賞候補にも挙がり、発行部数も2005年時点では55万部に達していた。
しかし、その時点ではまだまだ「普通のベストセラー作品」でしかなかった。
その「多少細部の調整が失敗したかもしれない、しかし充分な認知度を上げた実験作品」が「2000年代最高峰の純愛ロマン」と、呼ばれるようになったのは、実は2006年1月から、TBS系列で放映された、ドラマ版からフィードバックされた大衆の反応と、感動によるものであった。
当時、石丸彰彦プロデューサー、脚本・森下佳子、演出・平川雄一郎、といったトリオと、制作協力のオフィスクレッシェンド、主演の綾瀬はるかと山田孝之というコンビは、そのまま2004年にやはりTBSで放映されて、社会現象を起こした純愛ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』のメンバーだった。
要するに「『世界の中心で、愛をさけぶ』メンバーで、もう一度純愛大作を、今度はピカレスクロマンを題材に、挑戦してみる」がTBSサイドの根幹にあったのだ。
「善良で純粋な少年と少女、難病、死」という、正統派純愛ドラマからのステップとして、ピカレスクロマンを選ぶことは確かに挑戦的であるが、逆を言えばコンテンツプロダクションにおいては、真逆の素材を使っても、同じ視聴者層や、結果を招き入れなければいけない。
原作のままでは、本当に「法も破り罪を重ねて、モラルも倫理も、最後の人としてのプライドも捨てて、互いを照らし合う陽になろうとするだけの、あまりにも悲惨すぎるカップルの物語」としてでか成立しない。しかも、その構造が完結するのは、最終回で全ての謎が解けた後になってしまい、毎回視聴率に一喜一憂するテレビコンテンツとしては、リスクヘッジ的にも倫理的にも、原作そのままにドラマ化するのではいろいろ禁忌が多すぎてしまう(実際、ドラマ化においては、家庭用化学用品メーカーの花王が、表向きのスポンサー表明から降りている)。
かといって、既に50万部を超えたベストセラーの枝葉を半端に、甘い考えで変えてしまえば、今度は原作や前作のファンからも信用を失うことになる。
「難病悲恋ドラマの次に、それを超える純愛大作ドラマを。しかし原作題材はピカレスクロマンで」
この、とんちのような課題に対して、石丸プロデューサーと脚本の森下佳子は、一つの大きな賭けに出た。
「まずは、ミステリーであること」を捨て去る。
それは、原作で東野氏が最後まで拘った部分であり、本作をミステリージャンルとする、唯一の方便であったが、逆を言えばドラマ版は、基本構造をミステリーに徹する義務を負わない。
むしろ、ミステリーには「倒叙」という概念があるので、先に雪穂と亮司の、原作では描かれなかった、淡く儚く、無垢で懸命な「魂」を、視聴者が抱きしめたくなるほどに描き切って、その後に起きるピカレスクロマン展開の全てに対し、予めエクスキューズを与えていくという手法をとった。
石丸彰彦プロデューサーは雑誌のインタビューで、主人公の2人の関係を可視化するなど、原作から大幅に手を加えたことについて「亮司と雪穂をモンスターにしたくなかった」と語っており(『ザテレビジョン』より)、その製作意図が第10話での、笹垣潤三と谷口真文とのビジネスホテルでのやり取りのシーンの中に表れている。
Wikipedia