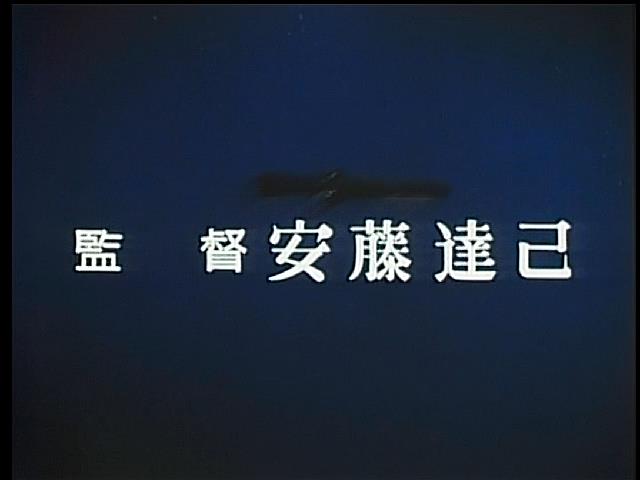「田口&白鳥シリーズ」だけに言及するならば、そこで現在刊行されている4作品において「許しがたい悪人」が登場するのは、実は初作『チーム・バチスタの栄光』の犯人と、二作目『ナイチンゲールの沈黙』の「被害者」だけである。
しかも、前者こそ医療成就者であるが、後者はただの「親失格のダメ人間」でしかない。
そう、マンモス大学病院を舞台にして、右も左も医療成就者というクローズドサークルの世界観を構築した海堂氏は、自分が医療世界の住人ゆえに、その医療の世界に悪人を配置できないという(決してただの弱さではない)ジレンマを抱えていたのである。
例えば『ジェネラル・ルージュの凱旋』で、速水と対立しドクター・ヘリ導入を拒む立場の沼田(映画版で演ずるは高嶋政伸)とて、その冷徹さや経営至上主義っぷりは、あくまで病院を経営面から支えようとする、愛ゆえであるという描かれ方をされており、それが「海堂氏が現役の勤務医」だから「描かない」のか、それとも「描けない」のかまでは判別できないが、シリーズを通じて「医療の場に身をおきながらも許すまじき悪人」というのは、初作の犯人一人くらいしか見当たらないのは事実だろう。
そこでの海堂氏の心情は計りかねるが、結果として「悪人が描けない」作家と世界観で、ミステリー小説をメインジャンルとするのは無理があったというのが真相だろう。
そこでの『チーム・バチスタの栄光』の犯人像こそ、医療システムが抱える矛盾と倫理が根底にあって「その悪人が存在してしまった事実」による問題提起は構築されていたのだが、そもそも、海堂氏の「本当のきっかけ」はその問題提起ではなく、医師ならではの「他に誰も思いつかないトリック」と、それを解き明かす劇的な存在としての「オートプシー・イメージング(Autopsy imaging、以下Ai、死亡時画像病理診断)」の提唱という、二つのポイントをして、海堂氏がその発表ステージに、ミステリー界を選んだのではないかと推察される。
Aiについては、この論ではその詳細な解説は省くが、簡単に言ってしまえば「死後、遺体をCTスキャンなどで診断することで、遺体に損傷を与えず、解剖のコストもかからずに、死因を判別できる」技術論であり、海堂氏は、医師としてその技術に着目し、それを医学会よりも一足先に、一般社会にプレゼンすべく、娯楽文学の推理小説における名探偵役として、Aiそのものを活用したという見方もできる。
そう、少なくとも海堂氏のデビュー作『チーム・バチスタの栄光』においては、そこで名探偵役を勤めるのは、田口でも白鳥でもなく、Aiという技術であり、機能システムであり、海堂氏が本作で主張したかったのは「Ai技術が普遍化されて、通常現場にも導入されれば、医療過誤ももちろん、医療過誤のふりをして起こされた意図的殺人をも、防ぎ、暴き、患者や医療システムを守ることができるのだ」という、理想主義であり、アジテーションであったのだ、という解釈もまた可能なのである。
本作はミステリー小説としてみた時に、優れたフーダニット・ハウダニット小説として「マンモス大学病院の内側」を覗いた気分にさせてもらいながら、それらの本格推理小説要素も充分に満喫できる、優れたミステリー小説として評価も高いし、筆者も当然評価する。
そこでのフーダニット・ハウダニットには、医学的専門知識が巧みに使われつつも「専門知識がないのが当然の読者を、専門知識がないからこそ騙す」構造ではなく、「登場人物の専門家同士のやり取りで、充分に謎解き条件を提示しながら、読者にもフェアに情報を開示しつつ、田口・白鳥が読者よりほんの数歩だけ、先取りした解釈と洞察で、事件を暴く」という手法に徹しており、そのバランス感覚は、理系医学系の専門家らしからぬほどに高度で、本作を、質の高い本格ミステリーとして完成させていた。
ただ海堂尊氏が文学者でない点が露呈してしまったのが、そこでの白鳥圭輔というキャラクター造形だったのではないだろうか。
白鳥は『海堂尊の「メディカルエンターテイメント小説」群の、概要と本質』でも書いたとおり、原作小説では「成金センスの高級ブランドを下品に着こなし、他者からは、ゴキブリのような印象に見える、小太りのさえない厚生省の中年役人。しかしひとたび口を開けば、超高等ロジックテクニックと、子どもじみた感情的な物言いで周囲を振り回し、気がつけば、その超絶論理的なコミュニケーション能力と洞察力で、常に困難や謎が打ち砕かれている」というキャラである。
これはこれでなかなか興味深いのだが、実は海堂氏は人物描写の根底で、癖というかスタイルがあり過ぎるのだ。
それは、白鳥に限った話ではなく、むしろ「白鳥以外」に共通した要素である。