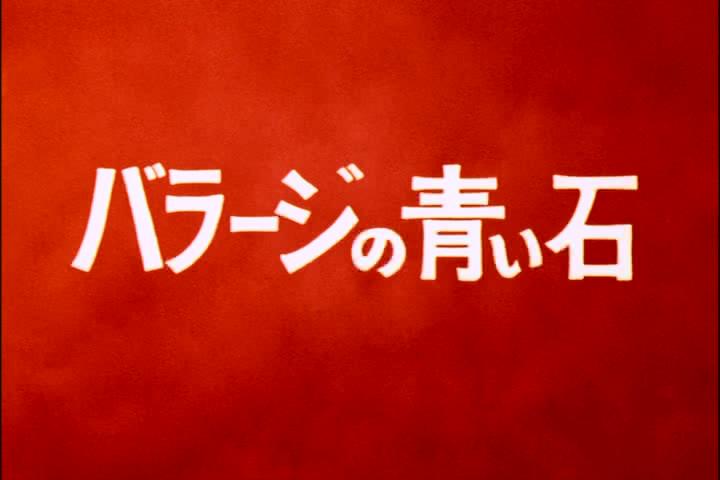本作『こちらニッポン…』は、1973年に社会現象を起こしたベストセラー『日本沈没』を書いて、世間に幅広く認知された小松左京氏が、1976年1月から、朝日新聞に一年間かけて連載した、シミュレーションに特化した現代社会SF長編小説である。

その三年の間も、小松左京氏は『虚空の足音』『時間エージェント』などの珠玉小説を精力的に執筆しており、既にこの頃、その筆の速さとクオリティ、日本SF界を牽引するパワーもバイタリティも、2度目のピークに達していただけに、一概にこの書評一つをとって、小松氏の全てを語るには無理があり過ぎるが、長年の日本SF研究や論文。評論等で語りつくされてきただろう概要の部分だけでも、少しここで記してみたい。
小松氏が、主に長編で展開するSF小説には、大きく分けて三種類がある。
一つは『果てしなき流れの果に』『ゴルディアスの結び目』等に代表される、本格西欧テイストのSFでありながら、そこに壮大な哲学や世界観(SFとしての世界観という意味ではなく、文字通り「世界」に対する「観」)が組み合わさり、壮大な抒情詩のような読後感を残す作品。悠久の歴史に対する、人という存在が介在することによる自我的変換に関しては、『結晶星団』等もそこに含まれる。
二つ目は、『復活の日』『日本沈没』『さよならジュピター』『首都消失』のように(一般的には、このジャンルが一番「小松左京氏っぽい」と幅広く認知されている)、人類史上経験のない、存亡未曽有の危機に対して、如何に人類がその英知と、人種等の壁を乗り越えた結集で、それを乗り越えるのかへのシミュレーションSFである。小松氏がまず、『復活の日』を書くためにいろいろな分野を学んでいった先で、地震学のジャンルで太平洋プレートの存在に気づき、そこをフックにして『日本沈没』を書いたのは有名な話。このジャンルにおいて小松氏は、物語の舞台を現代、近未来、宇宙時代と、自在に描き分けながらも、その舞台設定に見合って「人類」に与えられた科学と手段で、いかにしてクライシスを具体的に受け止めるかという部分における精査と取材が完璧で、『日本沈没』発表当時などは、これをしてそのまま地震学の教科書としても通用する(作中で唯一、疑似科学の範疇として用いられた「ナカタ過程」という理論が登場したが、逆を言えばそこでその、「ナカタ過程」なる「小さな嘘を一つ混ぜるだけ」で、日本が沈没する可能性が、学説的にも証明されたという背景を持った)出来栄えに達している。
小松SFの醍醐味の一つに、この「物語のメインストリームで与えられたクライシスが、かつてまだ、誰も思いついたことがないようなシチュエーションであるにもかかわらず、その物語内で、クライシス自体を成立させるロジックや科学考証が、完璧なまでに練りこまれているため、ともするとそのジャンルがSFだとさえ気づかれにくい」という特徴がある。
その代わり(これは意外と認知されていない概念だが)映画化の影響があるからか、『さよならジュピター』は、SFファンからは軽んじてみられがちだが、小松作品、ひいては日本SFにおいては、当時前例を見ないレベルの、ハードSF小説としても分類される、未来宇宙科学SFとしての完成度を誇っていた。