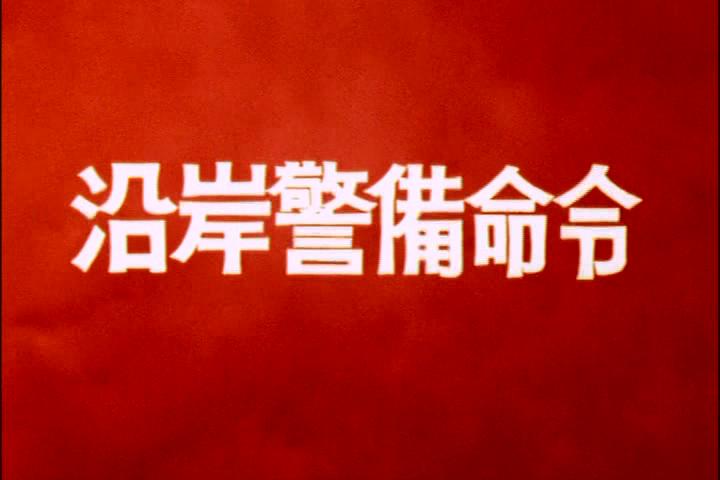儚げな魂が「そこ」にあった。
作品の世界観は、当時今で言う「萌え」界隈や少女漫画界でジャンル化していた「猫耳漫画」。
しかし、この作品はアニメ版『銀河鉄道の夜』(1985年 原作・宮沢賢治 監督・杉井ギサブロー)のように、悲痛なまでの現実の厳しさを描く。ほんの些細な「儚げな魂」を描く。
主人公はネム。
女子高に通う、ラーメン屋の娘で、無口で地味。内面の全てを「漫画を描くこと」に注ぎ込んで、鬱屈の日々を過ごしている。
漫画を描く内気な少女、といっても、イマドキのステレオタイプの「オタク」でなければ、エヴァ風味の「メンヘラかまってちゃん」でもない。
内面におそらく。これは「おそらく」で終っているが、燃え滾るような「表現への渇望」があり、しかしそれを「描く」こと以外の、いかなる手段でもアウトプットできないがために、その存在すら、クラスメイトや周囲に認知されにくい。
「フン、物書きなんてのはな どこか根性がねじくれた 救い難い人種の 最終職業にすぎねえ」
別の狩撫麻礼作品で、主人公が語った台詞だが、それは本作品では、もっと狩撫麻礼氏の現状を重ね合わせたように「漫画」へ集約されていく。
物語序盤から、キーキャラとして登場する「木村ゴロー」は、元漫画家のアウトローで、酒と女びたりだった東京からドロップアウトしてきたという背景を持つ、狩撫麻礼漫画ならではの「いつものキャラ」だ。特にこれといった大きな戯作的変化はない。
しかし、「猫耳漫画」というジャンルの持つ視覚効果と、木崎ひろすけ氏の柔らかい描線がコラボレートを起こし、主人公少女ネムの心情と、ギリギリ砕け散りそうなまでの「たおやかなコミュニケート」がそこで描かれる。
「漫画家になる」という夢を作劇的テーマに持ちながら、各話は、ネムの葛藤と日常のクロッキーを繰り返し、それはどんなジェットコースタームービーよりも危うく脆く、そして儚げであった。
人が人と触れ合おうとする時に、感じる恐怖と期待と、そして淡い未来感。
ネムは、自分の描く漫画の「感想」が欲しいのではない。承認欲求はほぼないに等しいこの少女が願うこと。
――誰かに届け