
えぇ、哀しい訃報です。
皆さんご存知のように、ジャーナリスト・評論家の立花隆さんが、4月30日、80歳で亡くなりました。
立花さんは、私にとっても、筑紫哲也氏に匹敵する、尊敬すべきジャーナリストであり、誰もが知るその最大の功績としては、田中角栄という、70年代日本を牛耳っていた最高級の政治家の、裏を暴き、真実を導き出し、最終的には法廷にまで突き出した、そのきっかけを作った人物であったということで、私達の世代であれば納得できるでしょう。
私自身、田中角栄という政治家に関しては、いろいろ含む感慨があります。
ロッキード疑獄は、これは全面的に田中氏の悪行であると認める一方、亡妻さんの故郷でもあった新潟が、田中角栄氏が国会議員に上り詰めてから数十年の間で「豪雪季に『雪に埋もれない県』にした」ことは、これは偉業であり、私も実際、亡妻さんと共に新潟に訪れて、そこに注ぎ込まれた技術やシステムの規模を見た時に、政治家がことあらば口走る「まずは全ては選挙区のために」を、究極の形で目の当たりにした気にさせられ、感服するしかありませんでした。
しかし、立花氏は、持ち前のジャーナリスト精神で、そんな田中角栄の表と裏を全て暴き、戦後最大と(当時)言われた疑獄事件を陽の当たる社会の表に全てを引きずり出したのです。
それは、思春期になって、改めてロッキード疑獄事件を調べた時に、再認識させられた偉大さなのですが、その立花氏が、生前、晩年になるにつれ、改めていった考え方があったと聞きました。
それは、自身の年代についてです。
2010年6月に、立花氏は、東大で講演を行い、このような発言をされておりました。
君たちはまだ二十歳前後だから、70歳になるまでに、あと半世紀はかかるわけです。当然のことながら60歳、70歳という年齢を実感を伴って想像することは、できないでしょう。
今、60歳、70歳と一口に言ってしまいましたが、60代と70代は全然違うものだということが、自分が実際に70歳になってみてはじめて分かりました。何がそんなに違うのかというと、肉体的には大した変化はありません。変わったのは心理です。自分の死が見えてきたなという思いが急に出てきたのです。70歳の誕生日、60代に別れを告げて70代に入ったまさにその日、とうとう最後の一山を越えたんだなという思いがしました。そして今、目の前には70代という地平が広がっていますが、その向こう側に、自分の80代、90代という未来平面が広がっているかといったら、いません。70代の向こう側は、いつ来るか分からない不定型の死が広がっているだけという感じなのです。
そうなってみてはじめて、20代の若者に何か言い残しておこうかという気持ちになりました。実はそれまでは、自分が生きることに忙しくて、若者を思いやって何かを語っておこうなどという気持ちにはなれなかったのです。
実際に70を迎えてみると、二十歳の人間と自分とは相当違うところに来ているな、という実感があります。だけど、二十歳の君たちには想像もできないことだろうけど、70歳になるということはそれはそれで面白いものです。パッと振り返ってみると、そこに自分の70年の人生がある。それが一目で見渡せるんですよ。
(中略)
というわけで、自分の70年に渡る人生全体をパッと振り返ってみるなんてことをあらためてしてみたのは、つい最近のことなんです。それはやってみると面白いものです。自分の人生のいろんな年代の持っていた意味があらためて見えてきます。20代半ばで社会に出るまでは、すべてが社会に出るまでの準備段階だったんだな、とか、社会に出ても最初の10年間は見習い期間みたいなものだったな、とか、大づかみな人生のスペクトル分析ができるわけです。
『二十歳の君へ』(文藝春秋)
確かに、私も今にして思えば、30歳の誕生日を迎える時、「これでもう、自分は死ぬまで『青春時代』とは無縁の存在になるのだ」とあきらめの境地に至る一方で「さて、ではどう、40代に素敵に繋がる30代を生きるか」というポジティヴさにも、切り替えられたものです。
その「切り替え」を、その後40代、50代で行えて来たものの、確かにあと二回、70代を迎えた時に、「その先」を見据えた展望を抱けるかというと、疑問が残ることは事実です。
それでも、私の場合は、この「50代」というステージで、初の単著を上梓させていただき、今年はこうして公式サイトも用意していただいた恩もありますので、まだまだこれから、という気概は失ってはおりませんが、この先20年と言われた時に、その時自分が何を見据えて、何を目的に生きているかは定かではありません。さらに私の場合、体の難病とも向き合って今を生きているわけですから、ますます立花氏が遺されたメッセージが響きます。
筑紫哲也氏は、看板番組だった『筑紫哲也のNEWS23』での、最期の『多事争論』の中で、「この国は今、癌に侵されています」と、自身の闘病と重ねて社会を批判しました。筑紫氏曰く「本来、政治というのは、老人(過去)に投資するのか、子ども(未来)に投資するのか。それを争う場所のはずです。ところが、今この国のパイは、どちらにも回っていない。つまり、この国はそういう意味では、癌に侵されているのと同じ状態ではないのか」と危機提唱したのです。
同じように、立花氏は、この国の少子高齢化や技術分野への投資の大幅減少等を踏まえて、「日本は今、敗戦への道を歩んでいる」とアジテーションしました。
「今、私達は『戦後』ではなく、『戦前』を生きているのではないか」に関しては、私も、この『web多事争論』で何度も発信し、それは拙著『スマホ・SNS時代の多事争論 令和日本のゆくえ』でも書いているメインテーマです。
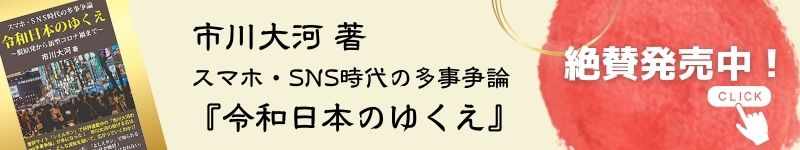
筑紫氏が準えた「日本の癌」、立花氏や私たちが唱える「敗戦への道」、これらをどうするかは、本来、政治家の手腕と生き様のはずです。
ですが、現在政権を握る与党内部からは、国民をどう国家主義に沿わせるかの提唱しか生まれていません。
いえ、それも過大評価でしょう。
コロナ禍の真っただ中で、カレンダーの休日を変更してまで強行される、東京五輪は、そこで利権が関わる者にとってのみ優先順位が高く、英国や米国のジャーナリズムからどれだけ批判を受けても開催される予定らしいです。
もはや、田中角栄氏のように、自分を国政に送り出してくれた選挙区の為に利権を引っ張ろうという政治家すらいないのが、令和の政権党の現実なのです。
ほぼ全員、自分の利権と私利私欲、そして前時代への回帰願望だけの政策。
優秀なジャーナリストのWatchDogを失った我が国は、致命傷の癌を患ったまま、敗戦への道を歩み続けるのでしょうか。
筑紫氏や立花氏が遺した言葉に、私達は今一度、立ち戻るべきかもしれません。
さて、今日はそんなところです。

















