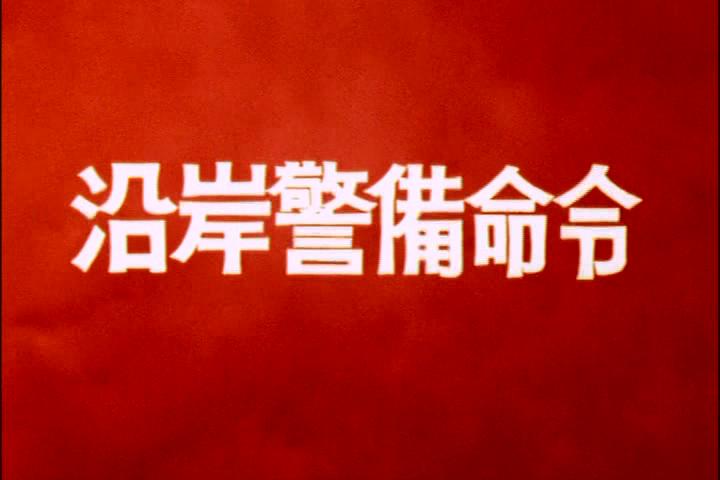筆者が以前から主張している「怪獣映画は恐怖映画だ」「怪獣映画は戦争映画だ」「怪獣映画はシミュレーション映画だ」を、この作品はしっかりとしたバランスで網羅し、その上で、昭和時代は「ゴジラと比較して幼稚だ」の一言で切り捨てられていた「ガメラならではの要素」に、リアリティ溢れたエクスキューズを付加している。
そもそも「怪獣が巨大な亀」なのはまだいいとしても、その怪獣が空を飛ぶときに「手足を引っ込めた穴からジェット噴射が噴き出し、回転しながら超高速で飛ぶ」なんて、どうトンデモな理屈を当てはめても、リアリティなんて感覚には程遠いはずである。
敵対するギャオスだって、生物なのに口から超音波光線を吐くわけで、昭和版では「ギャオスは首の骨が2本あって、それが音叉のような働きをするから」と、分かるような分からないような、昭和時代特有の微妙な科学考証で、理屈が捏ねられていたが、今回のリメイクでは昭和ガメラ時代に(ガメラに関してだけ)少しだけ触れられた「アトランティス大陸の生物」という、設定部分を継承して膨らませた「ガメラもギャオスも、既に滅んで海に沈んだ、太古の文明科学によって創造された、遺伝子操作生物」という、少なくとも、頭を痛ませないですむレベルの「なるほどロジック」をそこに用意。
怪獣の存在と能力と生態だけを、そのアクロバティックなバックボーンでアリバイを作り、後は基本的にリアリズムとシミュレーション主義で、この映画は全編がデザインされた。
ギャオスは序盤では、その姿をカメラの前に姿を晒すことはないまま、そこでは徹底して、未知の人食生物の恐怖を演出している。
そしてギャオスの存在の立証と確認が、登場人物とドラマ世界内常識の合意を得てから、その姿の全貌や恐怖と、基本的な生態が徐々に暴かれる過程を描くという、本格的怪物映画の王道的手法が、現代的な演出(例えばそれは、主に脚本の伊藤氏が、押井守監督と組んだアニメ『機動警察パトレイバー the Movieシリーズ』で多用した「テレビで報道されるニュース画面」や「間接的なデータ画面上での認識」を、通常演出と連動させることで、逆に「状況と観客」の心理的距離感を縮めて「それ」を現実と錯覚して、疑似体験させる手法に顕著である)と交錯しながら、いやがうえにも「怪獣(ギャオス)が現実世界に存在し、我々の社会に襲い来る」という、臨場感を増幅させてくれて、その後の展開にも期待をもたせてくれるように機能する。
その行く先で、福岡ドームを利用しての、ギャオス捕獲作戦へと流れていくプロセスと並行する形で、ガメラの存在とバックボーンへの伏線、そして登場が、これもまた、臨場感を保持しながらも、満を持してギャオス目掛けて駆けつけるという、ハッタリも効いた演出と両立した形で、巧みに描かれる。
それまでの過程では、どちらも怪獣登場演出としては王道な流れを辿る両者だが、方やギャオスに関しては、惨殺スプラッター映画ギリギリ寸前レベルの惨劇が強調され、方やガメラに関しては、それとは対象的に「静かなる眠れる巨神」的な描かれ方をする。(ひょっとすると、この流れを創作した金子・伊藤コンビの中のガメラ像には、ガメラシリーズと同じく、昭和を飾った大映特撮の王道『大魔神』(1966年)のイメージも、被せてあったのかもしれない)
ここは余談になるが、本作でのガメラは物語冒頭では島の形で現れて、その島(ガメラ)に、伊原剛志らが上陸調査をするという描写があるのだが、これはおそらく昭和のガメラが「当時の大映・永田ラッパ社長が仕事で飛行機で移動する最中に、窓の下に丸い島を見て、亀の甲羅を連想し、亀の怪獣映画を思いついた」という(真偽の程は定かではないが)逸話へのリスペクトとして、物語の中に直接そのままの形で、投じられたシークエンスなのかもしれない。
ゴジラは元々悪役だった過去があるので、復活版『ゴジラ』(1984年版)でも単独で主演を飾り、だからその強さの描写も、街や都市や自衛隊をなぎ倒すという流れで充分描かれたが、元々が子どもの味方だったガメラの場合(こちらも悪役の過去が初作でだけあるものの)人類や街を恐怖に陥れる形で、強さを描くわけにもいかないし、だからこそ、一応敵役のギャオスとセットでリメイクされたわけである。
だがしかし、その敵を倒してみせないことには、観客にガメラの強さが伝わらず、だからといって、序盤で倒してしまうとクライマックスが成り立たなくなるという矛盾。
これに対して金子&伊藤が用意したプランニングは「ギャオスは単体ではなく、まずは幼体として数匹を一斉に出すことで、『エイリアン2』(1986年)のように、集団クリーチャーとしての恐怖を描きながら、その中の何体かをガメラに倒させることで、ガメラの強さと立ち位置や、ギャオスとの関係を描こう」であった。
このアプローチは明快で、ギャオスの「リアルタイム環境適応型進化設定」も盛り込みつつ、その恐怖と、そんなギャオスから人類を守ろうとするガメラの強さとを、双方充分に描きながら、物語はクライマックスへと流れ込んでいく仕組なのである。
その間に展開される人間ドラマも、平成ゴジラのように怪獣を置き去ったまま野放図に、行き当たりばったりと思いつきで配置されたキャラが、非現実的な世界観の中を、うろうろうろついて不協和音で奏でられるようなものではなく、登場キャラクターがそれぞれ個々に、そして有機的に、ガメラに、物語全体に対して絡んでいく協奏曲的構図を見せている。
冒頭からラストまで、残虐な生命体ギャオスと向き合うことになる、鳥類学者の中山忍。
そんな一方で、それと対比されるように、人類の守り神ともいえるガメラと運命を共にするかのようにシンクロして、ガメラの意思を汲み取り、見守る巫女のような役割の藤谷文子。
そして、その「それぞれの怪獣と向き合う二人の女性」を守るように配置された、海上保安庁の好青年・伊原剛志と、弱気でトボけた刑事・螢雪次朗と、父性愛の象徴のような藤谷文子の父・小野寺昭(そこは巧みに父子過程と設定されている)。