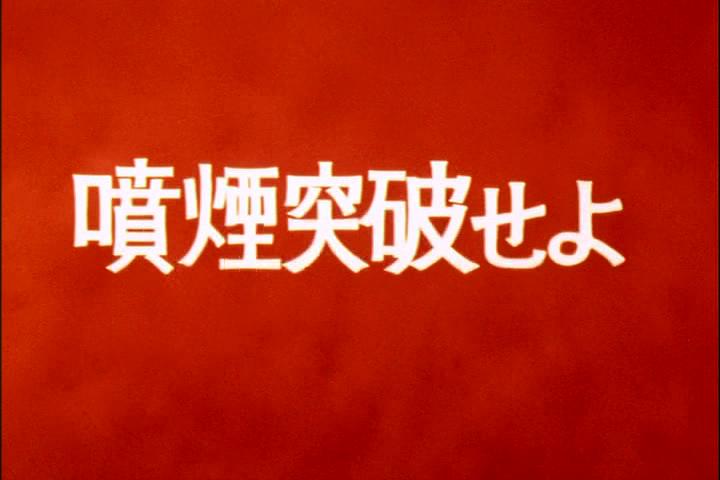それは例えば、この時期もっとティーンズにとって身近なメディアになっていたアニメの世界で、富野由悠季監督による『機動戦士ガンダム』(1979年)が、この映画作品と、同時多発のように用いてみせた「翔ぶ」というキーワードの一致が象徴しているように、この映画も、原作は漫画だからか「普通に考えたらありえない」設定を基本としながらも(それでもここ四半世紀の「ありえなさ過ぎる萌え漫画」と比較すれば、まだまだ充分、自身の身に置き換えて考えることが出来る環境設定ではあるが)そんな中で、実社会を「目の前に広がっていて、でも見えてない認識」のティーンズが、どう「翔んで」みせるのかが、この映画が指し示してくれた80年代だったのだと、今でもはっきり、そう断言できるのだ。
「オロカねぇ」「ほとんどビョーキ」それらの(丸山筆がでっち上げてみせた)架空のワカモノ言葉は、しかし言語レベルで慎重に価値観のすりあわせを行ってるように思わせ、世代間の視点の一致を、いくつもの生き様や生き方が目指していることを表現せしめた。
その「懸命さ」を裏付けるように(後年、若手俳優からは名指しで嫌われることになる)相米慎二監督特有の1シーン・1カット技法が必然的に招く「少年少女俳優イジメ」的表現が、この作品に集まった、薬師丸ひろ子、鶴見辰吾、石原真理子、尾美としのりという4人の「80年代の若きプロフェッショナル俳優」に帰結して、鮮やかに体現された。
本作品のクライマックスで、石原真理子の部屋において鶴見辰吾が、自分が薬師丸ひろ子と同棲している事実を明かすシーン。
そこで鶴見辰吾が、全く演技が出来なくなって、そこで撮影はストップし、相米監督と鶴見辰吾で、一晩中とことん納得がいくまで話し合ったという。
そんな鶴見辰吾が、家を飛び出した薬師丸ひろ子を捜して、雨でずぶ濡れになるシーンで、撮影の合間のたびに、必死に鶴見辰吾にタオルを差し出す助監督に対して、相米監督は、それを叱ることも出来なかったのだと、後々悔やんでいたのだ。
相米自身、この初監督作品の直前にチーフ助監督として仕事をした、長谷川和彦監督『太陽を盗んだ男』では、撮影班がゲリラ撮影をする際の「警察に見つかったときの、逮捕され要員」をさせられた経験もある。
薬師丸ひろ子だって、事実上のデビュー作『野性の証明』(1978年)では、高倉健に(劇内外含めて)守られた立場であって、真の主役を勤めるのはこれが初めて。
鶴見辰吾も、それまでテレビ出演は何度も経験したが、映画の仕事はこれが初めてで、「そこ」には誰も、頼れる先輩も先人もいないセカイで、全員が一つの映画の完成へ向けて、ひた走っていた状態なのだ。
脚本の丸山昇一含め、殆どの主要関係者が(キティフィルムも)「映画が初めて」経験で、だからこそ、この映画は「70年代まで」の何物にも縛られない、瑞々しさに溢れていた。
結果、この作品は第4回日本アカデミー賞作品賞部門で話題賞を受賞し、「邦画界の『アイドル映画』の概念を変えた」と賞賛される出来上がりになった。
それまでの、山口百恵映画やアイドル映画は、内容や質は二の次で、とにかくアイドルが可愛く、格好良く映っていて、物語が盛り上がればそれでOKという、そういうガジェットでしかなかったのが「アイドル映画」であったのだ。しかしこの作品で、4人の「アイドル」達は皆、笑って転んで感情をさらけ出して、反対に感情を押し殺し、自分の身の丈の足りなさに悔し涙まで流し、立ち小便をして、自転車で坂道をゴミ置き場にまで突っ込ませる勢いで走り抜いた。