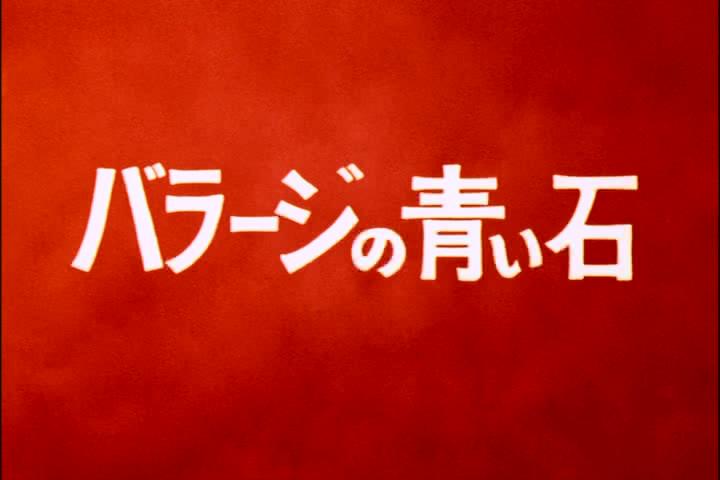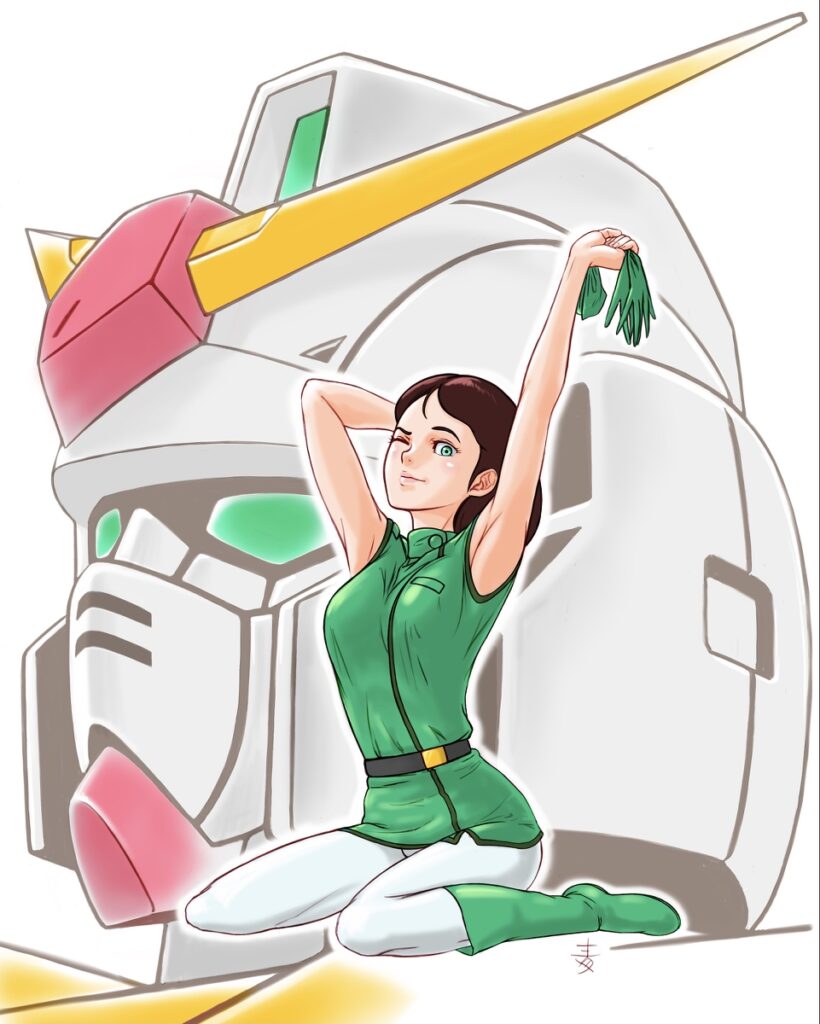それは「混沌と狂騒の70年代を強制終了させて、氾濫分子を駆逐して社会の大掃除も済み、整理整頓され尽くした、塵一つ落ちていない80年代という『全ての喧騒が収まった時代』の中に放り込まれた10代」としては、当たり前の姿ではあったが、それをクロッキーのように、フィルムに焼きこむ発想と体質が、それまでのアイドル映画製作体制にはまったくなかったからか、この映画はあらゆる意味で革新的な作品として、受け止められたのだ。(実際、この時期に並行して、東宝で制作されることになったたのきんトリオの『たのきんスーパーヒットシリーズ』(1981年~1983年)や『野菊の墓』(1981年)『プルメリアの伝説』(1983年)等の松田聖子主演映画群も、始まりからして既に時代遅れの感は強く、主演アイドルのファン層だけは呼び込めたが、その後の相米監督や80年代映画旗手の台頭によって、80年代半ばにはその役割を終えて、「アイドル映画」はやがて「あくまでアイドルを主演に据えた思春期映画」へと変貌する)
「アイドルを主役に据えて映画を撮るという行為は、カメラレンズとフィルムを通して、あくまで『その時代の思春期』と向き合う行為なのだ」と、ようやく認められたのだ。
この映画に出てくる「大人」は、通常映画では考えられない程に、驚くほど少ない。
ドラマに登場する4人の主役思春期に対してのゼロ座標点として機能してあげている大人といえば、せいせいが円広志演ずる学校の担任教師くらいだ。後は、特別ゲストの真田広之や原田美枝子も、双方ともまだまだ「若手俳優」の域を出ていなかったというのもあってか、いわゆる一般社会における大人というよりは、薬師丸や鶴見の視点位置から見える範囲の「オトナ」でしかない。(主に東映系の名バイプレイヤーでもある三谷昇氏などに至っては「声だけ」の出演だ)
つまり、この作品世界では大人社会はあくまでも「アドバルーンの鯨」でしかなく、彼等、彼女等はその存在をまだまだ、間近に居ながら実態として認知認識出来ない状態なのだ。
それは決して「自分以外の他人を、人間として認知できない」庵野秀明が監督をした『新世紀エヴァンゲリヲン』シリーズ(1995年~2021年)が、雑踏に人を描かないのとは違い、そこで描かれる4人各自の「未熟ゆえの視界の狭さと、視点の低さ」が大人なる存在をして、見えなくさせているからである。
「大人社会=自分達がやがて飛び出していくべき世界」を何かに象徴させて、それと向き合っていながら、実態を把握し切れていない若者や思春期達を主人公に「いかにして『そこ』へ翔んでいってみせるか」をテーマにすることは、この作品の他でも、同時代の映画作品の中にも散見されるテーマではある。
それを踏まえた上でだからこそ、それを前面に押し出して描き続けた70年代を、通過し終わった時代を感じたからこそ、今回冒頭で記した映画群はどれもこれも、「社会派」「社会論」とは縁遠い「個性による作風群雄割拠」に見えるかもしれないが、決してどれ一つとっても「社会の存在感と向き合い方」に関しては、それまでの「70年代式社会派映画」に、一歩も引けをとっていないのである。
今にして思えば、70年代は何かにつけ左傾化した作品や作劇が幅を利かせ、その反動から、この80年代は「シラケ世代」「空洞化」とレッテルを貼られてきた。
その後、90年代に入り、日本の作品文化はむしろ(国力の低下に比例して)右傾化していくのであるが、筆者の思春期はそういう意味で「子どもの頃を思い返してみれば、あぁ左翼文化隆盛の時代だったな」と思いを馳せ、一方で「五十路を過ぎて文化を見渡してみれば、あぁ愛国保守文化が元気だなぁ」と思う、その狭間で築かれ、基礎を作られてきたわけであって、その世代を代表して言わせて頂ければ、80年代は決してシラケでも空洞化現象でもなく、むしろ「真なる自由とは何か」「70年代の志士達が叫び求めてきた、『真なる自由』を本当に手に入れるためにするべきことは何なのか。手に入れられるということは、どういう状況を指すのか。そのとき、大人は、子どもは、思春期は、何と向き合ってどうするべきなのか」という、イデオロギーに左右されないリアリズムを飲み込んだ、本当の意味のリベラル時代であったと言いきってしまうのは、少し個人的な思い入れが過ぎるか(笑)。
少なくともこの作品は、キティフィルムという新興会社を発射台にして、相米慎二、丸山昇一、薬師丸ひろ子、鶴見辰吾、石原真理子、尾美としのり、そういったメンツを「翔ばせてみせた」映画ではある。(唯一、石原真理子だけは着地を誤ったようではあるが(笑))
僕個人にしてみれば、僕にとっての80年代は、ここから始まったのである。