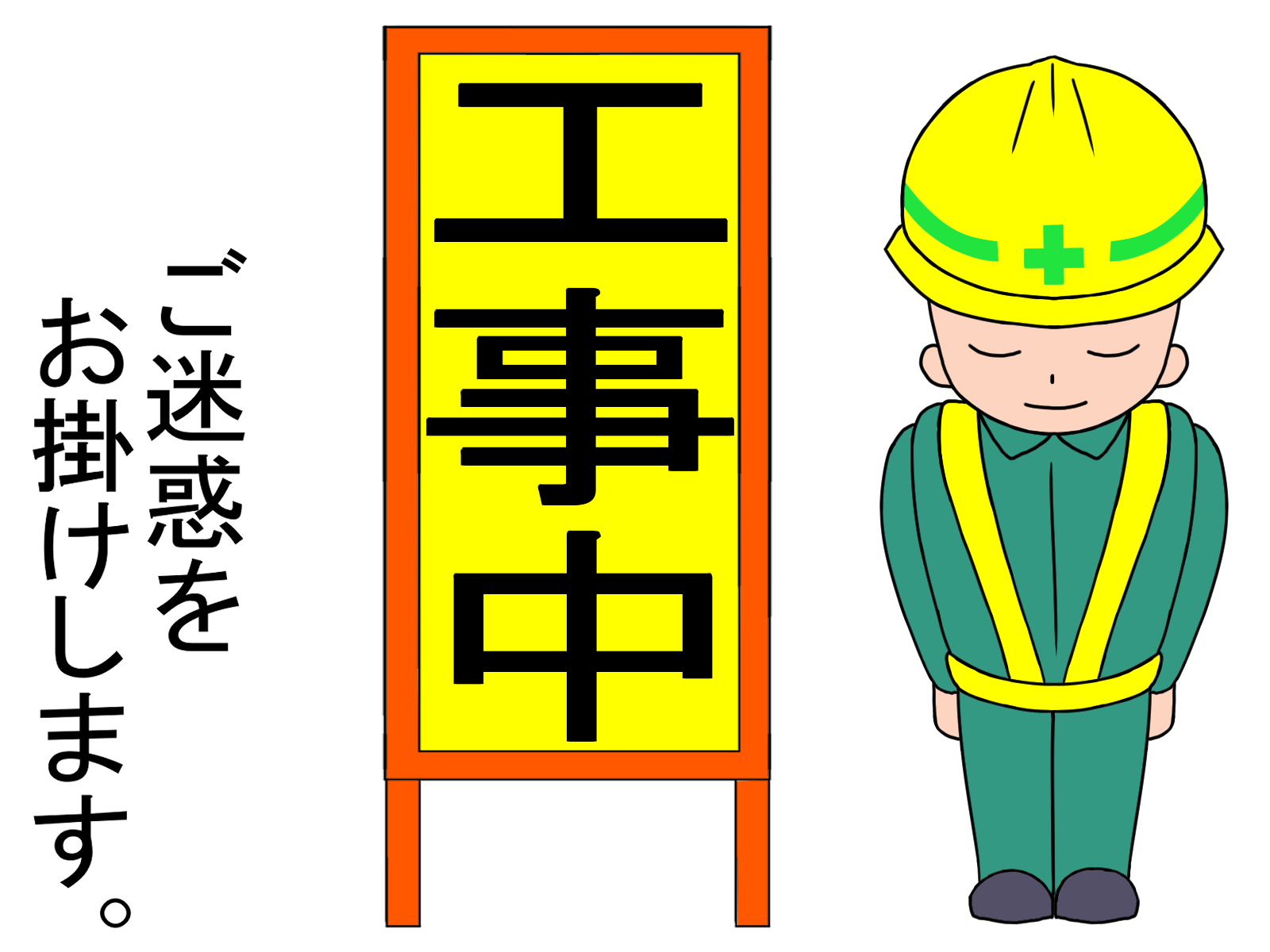そしてまた、本話はそのプロット段階においては「キュラソ星は、全体主義的な恐怖政治が統治する星であり、宇宙囚人303はその星から脱走してきた政治犯だった」という、明確なプランニングが存在している。
では、なぜ金城氏はこの作品執筆において、そういった明確にテーマを浮き上がらせるだろう要素を次々と排除し、むしろ「込めたテーマが理解されないように、慎重に」筆を進めたのだろうか。
本編では上記した、「恐怖政治のキュラソ星・政治犯の囚人303」という要素が省かれたばかりか、キュラソ星は徹底して、友好的な慇懃無礼さばかりが目立つように描写され、反対に、宇宙囚人303はその凶行さばかりが描写されるのである。
例えば、これを「初期のテーマ的プランニングを全て捨て去り、物語の骨子だけを再利用して、勧善懲悪話に換骨奪胎した」と理解することもできるだろうが、そうなると今度は、最終的に完成作品にて「数々の違和感」が浮き上がってくるのである。
その一つは、キュラソ星が慇懃無礼な無電でしか描写されず、勧善懲悪に変更されたのであれば描かれても良いだろうはずの、キュラソ星側の直接描写が一切なされていないということ。
また、宇宙囚人303が終始無言であること。
確かにセブンでは、同じように「夜の住宅街の恐怖」を描いた『緑の恐怖』などでも、ワイアール星人は無言であったように、「無言の宇宙人」自体は怪奇宇宙人描写としては王道ではある。
しかし、見返してみるとセブンでは、人間に擬態するタイプの宇宙人が、人間形態時に言葉を話すパターンも含めると、物語のラストまで徹頭徹尾無言であった宇宙人は極めて稀であり、少なくとも初期1クールにおいてはこのキュラソ星人しかいないのである。
この物語が、初期プランニングのテーマ性を排除して成り立っている、勧善懲悪の明快なストーリィに変質したのであれば、その「変質したルックス」を明快にするためには、むしろ「地球人を皆殺しにしてこの地球を奪ってやる!」くらいの台詞は、囚人303に言わせるはずではないだろうか?
ところが、物語中終始無言を貫き通した宇宙囚人303は、その最期の断末魔においてだけ、哀しみの泣き声を上げて爆死していくのだ。
そして、最終的な確信にいたる材料として挙げられるのは、物語中で一切セブンが活躍しないということ。
確かにセブンは、その初期企画案の中では、前作『ウルトラマン』(1966年)との差別化を図るために、むやみに巨大化して肉弾戦を行うのではなく、等身大でも活躍するヒーローとして企画されたというのは、筆者が『マックス号応答せよ』評論で書いた通りではあるが、それでもこのエピソードにおいてのセブンの活躍の無さは、少し異例すぎるほどに目立っている。
一応ダンは、そのクライマックスでセブンに変身するものの、キュラソ星人に攻撃を加えるまでもなく、ただ脱出するのみ。
それも、地上に降りた途端にカットは切り替わり、すぐにダンに戻っている。
セブンの登場シーンは、完成作品の尺では、トータルで10秒すらないのである。
これは一体、何を意味するのか。
つまり、金城氏は、様々な要素を振り切り捨て去って、本話を勧善懲悪物のルックスで仕上げたものの、それでもセブンだけは戦わせたくない心情があった。
セブンに、キュラソ星人を攻撃させたくない心情があったからこその、子ども番組としては異例すぎるほどの処置になったのではないだろうか。
そうでなければ、いくら「ウルトラマンとは違う路線を」と言いはしても、「変身して脱出するだけで、すぐに変身解除」では、もはやそれは、ヒーロー物としてのルックスや対面すら保てないのが現状。
そう、金城氏は、本話をヒーロー物として成立させたくなかったのではなかろうか。
そしてまた、円谷プロの他スタッフも、(市川森一氏が述べたように)皆共通意識として同じ思いがあり、本話にそのような共通意識が、テーマとして込められていることが、理解できたからこそ、脚本から撮影、編集に至るまでの間に、多数のスタッフが関わって携わる中であっても、誰も「セブンが何もしない」ことに異を唱えたり、横槍を入れはしなかったのではないか。
では、と逆に疑問が残る。
では、金城氏はなぜ本話を、まるで子どもの意地のように、勧善懲悪物として仕上げたのであろうか。
金城氏が、ベトナム戦争やその脱走兵問題に対して、無関心故にプランニングを変更したのではないことは、今までの検証でわかることであるのに。
それは多分、この頃の金城氏にはまだ、ウルトラのメインライターとしての責任感や、自身が沖縄出身の外国人であることへのコンプレックスが作用して、よりグローバルな世界観になった『ウルトラセブン』においては、自身の生の心情を、自作の脚本に込めていくことに対し、躊躇し、ためらっている部分があったからではないだろうか。
その上で、筆者が本評論で、何度か述べている「金城式コスモポリタニズム」。自身の個を捨て、そして個を捨てるということで、同時に故郷沖縄・琉球へのナショナリズムも捨て去った金城氏にとって、新たに帰属すべき国家・日本。
金城氏にとって、日本は憧れの国であり、そこに帰属するということは夢でもあり、日本の一員になることが金城氏を支えていたのは間違いない。
その彼が、日本人・ヤマトンチュに囲まれて、日本の国内の会社で、ヤマトンチュ達を率いて陣頭指揮を執ったときに、その日本人作家達がこぞって、日本国家批判をテーマに込めていた現状は、果たして金城氏の目にはどう映ったのであろうか。
そこで外国人である金城氏が、外国人であるが故に、意固地なメンタリティで日本肯定を強行したとしても、金城氏のナイーヴで繊細な魂を思えば、不思議でもなんでもないのである。
しかし、金城氏の故郷・沖縄は、米軍と、米軍が巻き起こしたベトナム戦争に対して、日本とは全く違う立脚点・視点を持つ国であって、その「沖縄」という視点から見たときに、見えてしまうベトナム戦争の真実は、日本を批判するヤマトンチュ作家の書く作品以上に、自らが書いた作品の中に、赤裸々に生臭く浮き彫りになってしまったのだ。