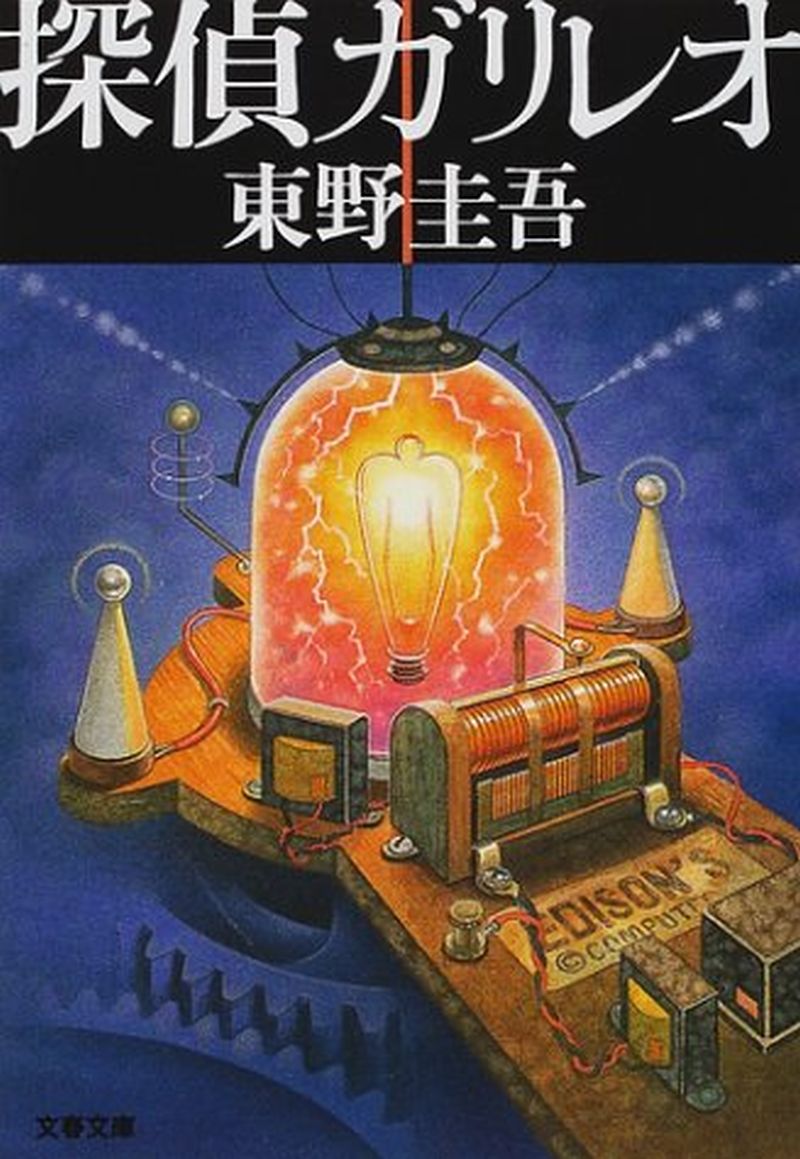『花冷え』敦子
主人公は特に決まっていない。
一応、いかにもなメインヒロインの敦子という少女は登場するが、彼女とて主人公を務めたのは第一話『花冷え』だけであり、第三話『花酔い』では、脇役に回っている。これは作劇的な演出というよりも、人生というのは誰もが自分が主人公の世界を歩むものであって、その当人にスポットが当たった作劇であれば当然主人公として機能するが、誰か違う人物をフィーチャリングした時には、自然に脇に回るという、橋田壽賀子ドラマや富野由悠季アニメに共通する、多層構造の概念なのだ。
後に改めて解説するが、1990年の映画化時には、敦子はむしろチョイ役で、原作ではその『花酔い』でスポットを浴びる、演劇部部長の由布子が、一番主役らしく機能していた。
そこで描かれるのは、全てが「刹那」であり「変わりゆく瞬間」の、ドキッとさせられる「青春の共感」。
女子高生が、付き合った彼氏と初めてのセックスに至るプロセスで抱く、葛藤のすれ違いと、その前と後の想いの(かすかな)段差。
男性には男性で、誰にでも村下孝蔵の『初恋』のような「封じ込められた想い」があるように、女性は女性で、常に封じ込めることをしないまま、前へ前へと、生きていこうとするがゆえに、フッと振り向いた時にもう、遥か遠くに見えてしまう「もう、戻れない自分。もう、あの場所にしかいない、あの時の愛した相手」に対し、佇んで途方にくれたまま、涙するしかないのだよと、吉田秋生女史は本作を読むだろう少女達に、優しく語りかける。
直後に結婚を控えている敦子の姉が、敦子頃の年齢の時に愛し合った恋人と、10年ぶりに再会した出来事を、敦子に語る。
「あれから10年たっちゃって……
吉田秋生『櫻の園』
もう、あたしも17の女の子じゃないし
あの人も16の男のコじゃない
もう あの頃のあたしたちじゃあないんだなぁ
10年たって……
あの人も そういうふうに昔の女を誘える男になったのね
あたしもサラッとかわせる女になっちゃった
もうあのぎこちないキスは 二度としてもらえないんだなあって思った……」
そこで涙したのは、姉ではなく「明日、ぎこちないキスをするのであろう」敦子だった。
「お姉ちゃん……
吉田秋生『櫻の園』
その人のこと ほんとに好きだったのね
ずっと忘れてなかったのね……」
涙の理由を言わない敦子に、窓の外の、夜桜を見つめながら姉が言う。
「そうよ……
吉田秋生『櫻の園』
忘れたことなんてなかった――
初めての男なのよ 忘れられるわけがないわ
忘れたら女じゃないわ……
本当に 好きで好きで たまらなかったのよ……」
『花紅』紀子
続く『花紅』では、不良を気取った、あどけない少女・紀子が主人公を務める。
紀子には、一応典型的な生真面目風眼鏡男子の彼氏がいるが、紀子自身は背伸びをし過ぎて10代を過ごしている。学校では、斜に構えて、周囲の女子たちをクラスタ分けしてため息をもらす一方で、幾人もの男性とデートしては、軽く、上手くあしらい、自分の自信に繋げている。
学校の周囲からは疎ましがられ、不良扱いをされているが、それは当人が望んだ立ち位置であり、屋上で煙草をふかして不良仲間とつるみながらも、どこか満たされない毎日を送っている。
“それ”がなぜ満たされなかったのか。
それは、紀子自身の万能感にあり、思春期の女子特有の「男性が馬鹿に見える」現象と相まって、自分自身が何を抱きしめて、どの道を歩けばいいのかが分からなくなっているからであり、だから、紀子は不良の中でも心理的に孤立して、自分で自分を孤独に追いやってしまう羽目になる。
けれど、『花紅』クライマックスで紀子は知る。
自分の器量の良さと度量と技術で、男性をあしらえていたのではなかったのだと。
自分が、まだまだ儚い年齢の少女だからゆえに、周囲の男性や大人たちは、優しく扱い、尊重してくれて、紀子が感じていた「どんな男もちょろいものさ」的な万能感は、決して自分が積み上げてきたものではなかったという「社会の構図」に気付く。
彼氏の性欲や願望を、冷静に察してしまいながらも、実は誰よりも幼い精神年齢を持つ紀子には、その構図がばかばかしく見えるだけである。
しかし、そんな紀子も夜桜を見つめて気付いた。
自分がまだ、子どもと大人の間の、一番不安定で、社会が置き場所に困る位置を生きている瞬間だと。
その上で「からかい過ぎた」彼氏が、セックスを迫ってこようとして、力では拒み切れなかったタイミングで、彼氏は手を止め、怒りどなった。
「しようとおもえば いつだってできちゃうんだよ こんなことは!
吉田秋生『櫻の園』
こっちのほうが 力はぜんぜん 強いんだからな
そうしないのは 嫌われたくないから!」
ここで、ここまでストレートに心情を口走らせてしまう吉田秋生女史を、男性を代表して思うのは「あ、男を分かっていてくれるんだな」という思いと同時に「けど、ごめん。本当にそう思ってる男子であれば、しかもハイティーン時期であればなおのこと、そこまで自分の憤りを、冷静に見つめることはできないし、それを口にしないだろう」と、「性の壁」を、やはりここでも感じながらも、しかし、ここで彼氏君に「その台詞」を言わせてしまえる吉田女史は、とても男子を、そして自らの「あの時代」を、大事に、愛してくれているのだと、それは素直に思えてしまうのだ。
今後も、ここシミルボンで書いていきたいテーマの一つに「80年代後半を彩った、思春期漫画の共感力」というのがあり、それはゆうきまさみ氏の『究極超人あ~る』かもしれないし、吉田聡氏の『湘南爆走族』かもしれないし、小林じんこ女史の『風呂上がりの夜空に』かもしれないのだが、荒唐無稽な設定や展開の中で、息をのむように、心が同期してしまう瞬間が、そこに描かれている作品と出会えるためには、良い作品、良い戯作者を探す審美眼と共に、自分が「良い思春期」を送っておかなければいけなかったのだと、ここは批評家としては冷静さを欠いた言説になるが、その分、その瞬間だけでも同期できる作品に触れることが出来る自分の人生や思春期を、ありがたかったのだと、その時代の自分を囲んでくれていた人たち全てに思うことが出来るのだ。
そして「それ」は、この台詞を受けて一晩経った紀子の中にも芽生えた想いであった。
「行きずりの男の子たち
吉田秋生『櫻の園』
いやだって言った時 許してくれてありがとう
みんな ほんとうは やさしかったんだね」
その瞬間を経た先で、紀子は自らの不平不満や背伸びから卒業していく。
吉田女史はそうして、この短編集に登場する少女たちの人生に、ほんの少しずつではあるが「あり得るリアリズムの奇跡」を起こしてあげることで、桜が咲いて散るまでの、ほんの一瞬のような時間を、一生の中で意味のある物に変えてみせて、その先を描かないであげる「優しさ」を持つのだ。