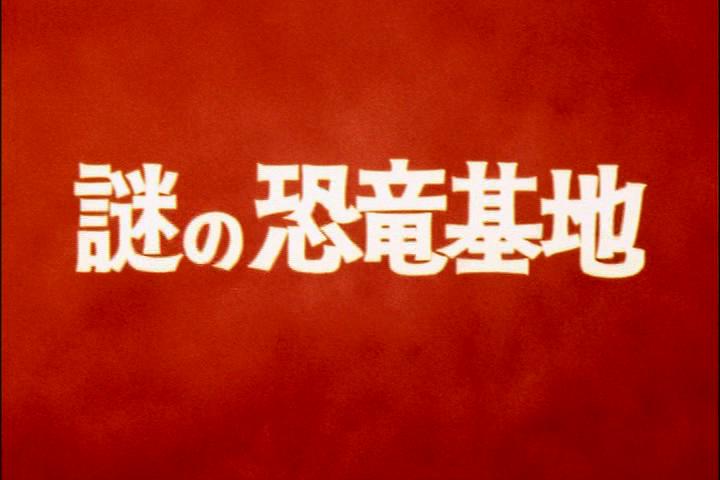しかし、面白いと思うのは、あとがきでもふれたがこの小説。「書籍としての形態」としては、大泉女史による挑戦的なインデザインと、表紙と挿絵を描いた春曄女史の、二人の力が重なってくれて、三位一体の状態で、読者の方々は手に取ってくださるのである。
それはある意味「実に面白い」の連続だった。
大泉女史とは、殆ど踏み込んだ打ち合わせはしなかった。僕との事務的やり取りは、漢字の開き方とか、固有名詞の確認とかその程度で、その中で大泉女史がぽつりと言い放った「私、大賀さんの小説を担当するにあたって、ちょっとやってみたいことがあるんですよね」と切り出してきた言葉に、ほうほうと乗っかってみた。「一度やってみたかったんですけれども、大賀さんのこの文章なら、やりたいことがやれるんじゃないかと思って」とまで仰ってくださった。いったいなにをなさるんで?とまでは聞くまい。所詮編集仕事は20年以上前に少し齧った程度の知識しかなく、デジタル時代になってからは手も足も出ないジャンルなのだ。プロとしてはかなりの実績を積んでいる大泉女史が「これなら」と、僕の小説を指してやってみたいことがあるのなら、『狼男だよ』初出版時の改竄事件までいかなければ、たいていのことは許せる信頼関係はもうできていた。
「よござんす。おまかせしましょう」
などと、夏目漱石的心意気で全てを任せて、今度は「商品としての顔」となる、表紙と挿絵担当の春曄女史との打ち合わせになった。
彼女とは付き合いが長いが、まさか再会したときに、向こうが賞をとった画家になってるなどと、夢にも思わなかったので、上野等で開催されてる展示会などへ直接画を見に行って、その時から(まだ書籍化決定以前)「『折口くんシリーズ』を書籍化するなら彼女にビジュアルは任せよう」と思っていた。
そして打ち合わせ。
事前に当然原稿を渡しておいたので、話はスムースに企みに進んだ(笑)
「これ、怪物とか画にするの?」
「するわけないじゃん、そんなんラノベになっちゃうじゃん」
「だよねぇ」
春曄女史のメインフィールドは和彩画である。
「風景でいいんだよ。壮大で厳かな。でも全登場人物の中から一人だけを、表紙と挿絵で描いて欲しい」
そんな僕の要望に、春曄女史はツーカーで
「あぁ〇ちゃんを描けばいいのね」
と返してくれた。
ここから先は打ち合わせは最低限しかしなかった。
春曄女史はあくまで昔ながらの方法で、日本画の画材と絵具で描く。ガンダムモドキの時なんかとは違い、デジタルなんか一切使わない。200%アナログだ。それは僕の今回の作品世界とも素敵に一致する。
彼女は風景だけを巨大な和紙サイズで描き、僕と意気投合して描いた登場人物の絵を別個に描いて、それを物理的に切り取って、背景画に糊で貼り付けて、境界線を均したのだ。
あっぱれだ。
フォトショやイラレじゃ相応しくない画にしかならない作品世界を、見事に一枚画で表現せしめてくれた。
ただし。
大泉女史の「やってみたいこと」と春曄女史の「描きたいように描いたこと」が、僕の思惑とほんのちょっとズレていた。
「想定外」だったのだ。
え? そこでページを区切りますか? とか、え? 和服なの? むしろ悠久の年月を生きる存在なんだから、現代は現代で現代にふさわしい服装でもいいんじゃないの? とか。
でもね。結果オーライ。
その「細かい違和感」が残存するからこそ、「一冊の本」全体に「多様性」という、表現エンタメに不可欠な、しかし僕一人ではまとめられない「雑感」を付加できたのだ。
ここで二人の女史との距離感は明確につかめた。
「あの頃のあの時」のような、不快感と不協和音しか残らない空回り感はもうそこにはなかった。
影でこそこそ不平を言い合いながら、新たな創造も出来ない愚かさのグループワークと今回は違う。
僕は今、改めて自著を手に取りながら、ようやく「僕の作品です」と胸を張って言える時を迎えた。
それはもちろん、大泉、春曄、お二人の女史の、技術と才能が支えてくれた発露であるからであろう。
まだ死にたくはないねと思わせてもらっている。