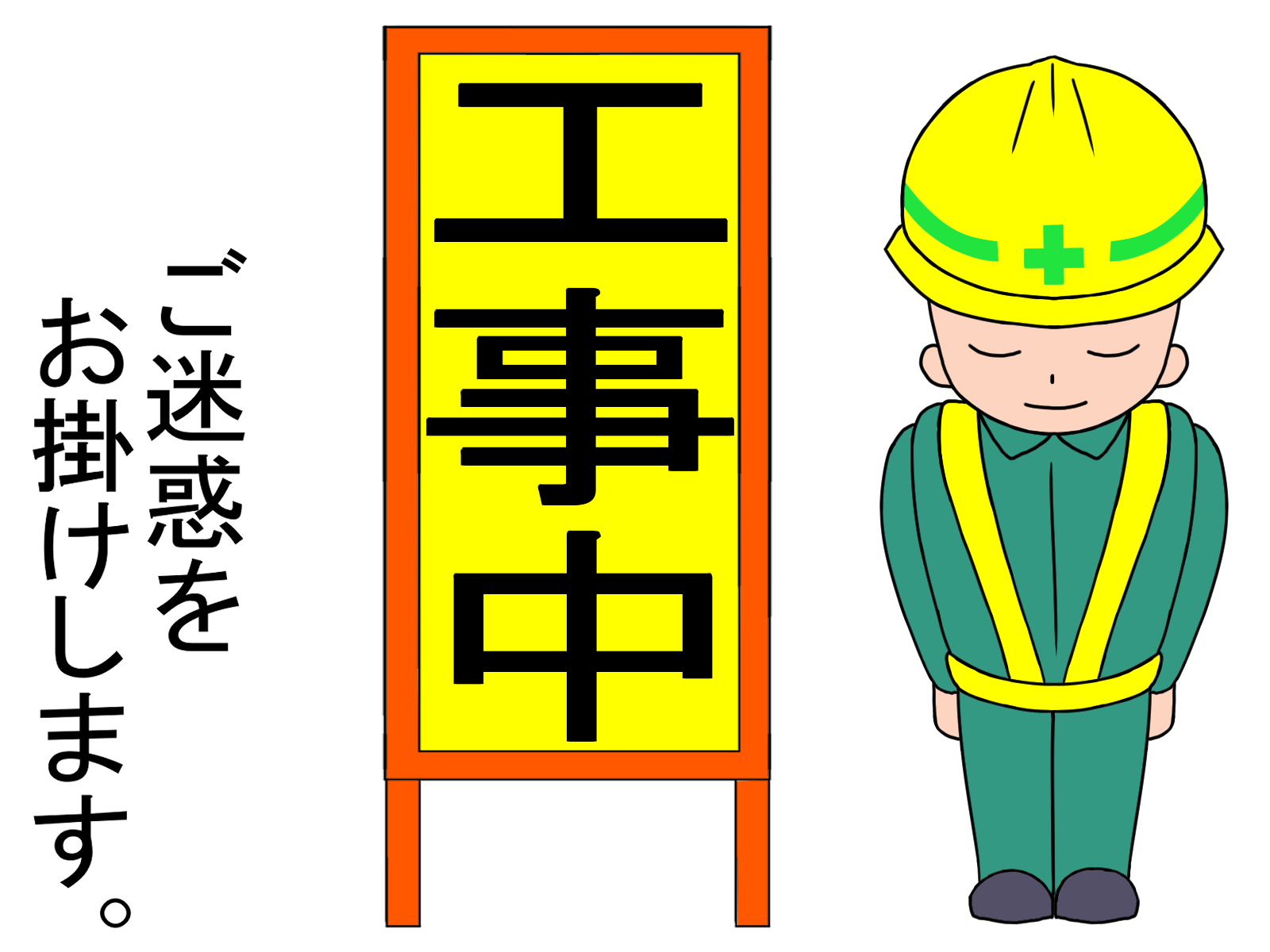怪獣という存在と向き合い続けた映画監督がとおした仁義

実相寺昭雄
佐々木守
山田高道
本書は、1970年代初頭に『無常』(1970年)『曼荼羅』(1971年)『哥』(1972年)等、ATG映画の監督として伝説になり、90年代に入る頃から、『帝都物語』(1988年)『ウルトラQ ザ・ムービー 星の伝説』(1990年)『姑獲鳥の夏』(2005年)等で娯楽大作映画の巨匠になった実相寺昭雄監督が、1987年に大和書房から書下ろしで発表した、回顧録的自伝小説である。
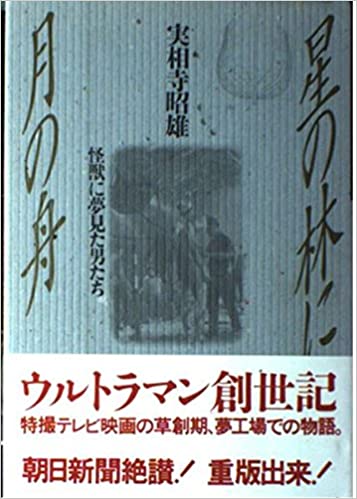
内容は、この頃の実相寺監督の知名度を支えていた『ウルトラマン』(1966年)『ウルトラセブン』(1967年)『怪奇大作戦』(1968年)時代を舞台にした、当時の円谷プロへの賛歌と、TBS映画部時代の回想で占められており、実相寺監督自身は、ごく軽い気分で筆を執ったと生前仰っていたが、ロングセラーになった本書は、その後頻出する「往年の子ども番組時代を回想して、自伝回顧録を書く」ビジネスのパイオニアになった。
内容は、筆者の分身である架空の若きテレビディレクター・吉良平治を主人公として、新進気鋭の芸術派ディレクターが、企業倫理の中でメインストリームから追い出され、当時まだゲテモノ番組扱いだった、子ども向けの怪獣番組へ出向させられるところからはじまり、そこで出会った人々や、起きた出来事を綴っていく展開になる。
他の登場人物は、金城哲夫と、円谷英二・円谷一を除いて、ほぼ全員が仮名で構成されているが、ウルトラや円谷プロに少しでも詳しい人であれば、誰もが個々のモデルを容易に理解できるアレンジの仕方ではある。
だが、小説の内容は、決して「子どもに向かって夢を見せようとする、志の高い、ウルトラマンプロダクションの物語」というわけではなく、筆を執った実相寺氏の、シャイな性格も手伝ってか、わざと自身を偽悪に描く方向でも物語は展開し、そのプロセスでも、不倫やスタッフ達の軋轢、個人観などバイアスとフィクションが織り交ぜられているので、これを実録的な作品として読み解くのは、様々な意味でやめておいた方が良いと言わざるを得ない。
自分も含めた「初期ウルトラの関係者」を、実名の三人以外ではとてもシニカルに描き、一方でタイトルにもなった柿本人麻呂の歌のような、絶妙なノスタルジィの透明感も全編に流れていて、純粋なフィクションの創作として、とても一級品に仕上がっている一冊である。
筆者は、僭越ながら、生前の実相寺監督と、多少の親交をもたせていただいた時期があるが、その頃の筆者では、恐れ多すぎて伺うこともままならなかったが、ひょっとしたら実相寺監督は本書を書いた時期、「ウルトラの実相寺」という神輿に対して、若干以上の鬱陶しさを感じていたのではないか。
本書執筆当時、実相寺監督はメジャーな舞台での創作発表はほとんどなく、それでも「ウルトラノジッソウジ」として、ファンやウルトラ媒体からもてはやされ続けていた時期。
常に未来を、次の作品を目指して生きる表現者にとっては、この状況が至福の時期であったとは、失礼だが思えない。
その実相寺監督を、本書執筆から1年後に、映画『帝都物語』でメジャー映画界に引き戻したのは、まさにウルトラの申し子で、自主映画で独自に『ウルトラQ 闇が来る』等を撮っていた、一瀬隆重氏であったりするところは、人生の複雑さであったりするのだが、人は誰も自分の未来を見通して今を生きることが出来ない以上、これといった新作映画も撮れず、ただただ「ウルトラノジッソウジ」として引っ張りだこでお座敷に呼ばれるだけであった実相寺監督が、どんな思いで本書を執筆したのかは、表現者の端くれとしては察するだけで胸がしめつけられるものも感じる。