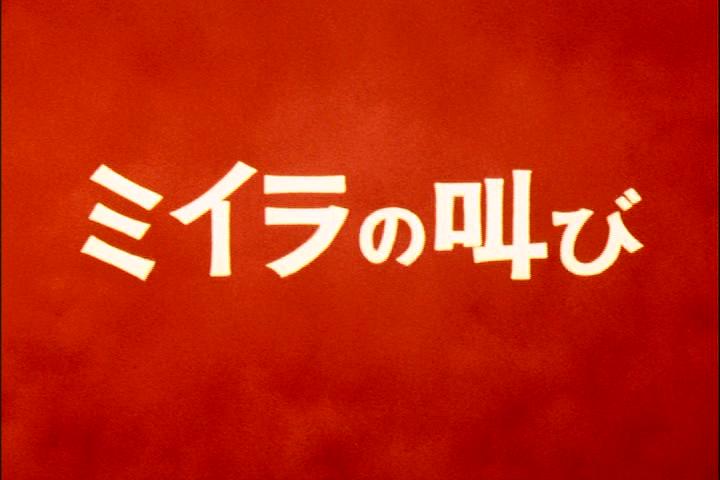それでも、『ウルトラマン』『ウルトラセブン』参加当時、TBS映画部からの出向で円谷プロへ出向いた時の、前衛芸術嗜好だったころと違い、この時期の実相寺氏は、改めてあの時代を振り返り、円谷親子や金城氏が偉大な存在であったことを自身の中でも認め、怪獣という存在に、新たな思いを抱いたのだろう。
本書のあとがきでも
私をはじめとするスタッフたちは、たしかに得体の知れないものにうつつをぬかしていたわけである。その馬鹿さ加減の匂いが、この小説から立ちのぼっているだろうか。
『星の林に月の舟』あとがき
と記述している。

この時期、社会ではレトロブームという現象が起き、バブルも調子を上げてきた頃合いでもあったので、過去をからかいながら懐かしむ風潮も生まれてきつつあった。ビデオデッキとレンタルビデオの普及も、一役買ったのかもしれない。
いずれにしても実相寺氏は、この時代、このタイミングで、どこへ行っても何度も聞かれる、ウルトラ時代の回想を「ならばこれを読んでくれ」という一冊に、したためてまとめておく意義を感じ取ったのであろう。
それはとても軽い動機の、自身のウルトラへの決別と、若かりし頃の自身の思い上がりに対する仁義だったのかもしれない。
実相寺氏自身、この直前期に、ATGで佐々木守氏と組んで挑もうとした野心作『ウルトラマン 怪獣聖書』が、諸々の事情でお蔵入りしてしまい、せめて没になったシナリオを出版でもしておかなければ、やりきれなかったという経緯がある。
ファンやマニアが喜んで担ぐ「ウルトラノジッソウジ」であっても、佐々木守氏と組んですら、本質的に撮りたい作品を撮らせてくれる環境ではないという実感は、表現者にとって絶望に近い感覚をもたらす。
この二つの現象の関係性が、決して筆者の思い込みではないことは、『ウルトラマン 怪獣聖書』を収録して、佐々木守×実相寺昭雄のロング対談が収録された書籍と本書が、共に大和書房から出版されたことでも、お分かりいただけると思う。
実相寺監督の人生を、最期まで見守ってその魂に思いを馳せる時、その後の「ウルトラノジッソウジ」だったからこその、後年の人気娯楽大作映画監督への流れを総括すると、本書はとても金字塔であると同時に「ウルトラノジッソウジ」への葛藤がピークだった時代の実相寺監督にとって、重要なターニングポイントであったともいえるだろう。
自身の青臭かった青年期と、若気の至りの記憶を、吉良平治という架空の存在に閉じ込めた上で、この先も求められるだろう「ウルトラノジッソウジの回顧録」を全て「思い出というフィクション」の中に閉じ込める儀式を終えた、実相寺昭雄監督。
筆者たちは厳粛に「それ」を、創作小説という前提で受け止めなければいけない。
全ては、星の林に去った、月の船のように、夢幻の時間の出来事であったのだと。
“そこ”に実在したのはむしろ、早逝した円谷英二氏、円谷一氏、金城哲夫氏だけで、後は虚構の存在達によって、怪獣という“得体の知れないもの”に入れ込んだ、大人たちが集まっていたあの時間こそが幻だったのだと。
そのテーマ、そのスタンスとスタイルは、おそらく本書に刺激を受けて、自身もと筆を執った、市川森一氏の『私が愛したウルトラセブン』(1993年)や、上原正三氏の『ウルトラマンティガ』(1996年)『ウルトラの星』にも通じている。
それら、本書を追ったテレビドラマが続く直前に、本書は『ウルトラマンをつくった男たち 星の林に月の船』というタイトルで、1989年にドラマ化されたが、夜の20時台、TBS開局記念ドラマ枠、ファミリー向けという前提があったため、ドラマ内容は小説とは劇的に変えられ「一人の熱血青年ディレクターが、『ウルトラマン』の現場に出向させられた先で、全てのウルトラマンのアイディアを生み出し、一生懸命がんばる」というストラクチュアになっていた。