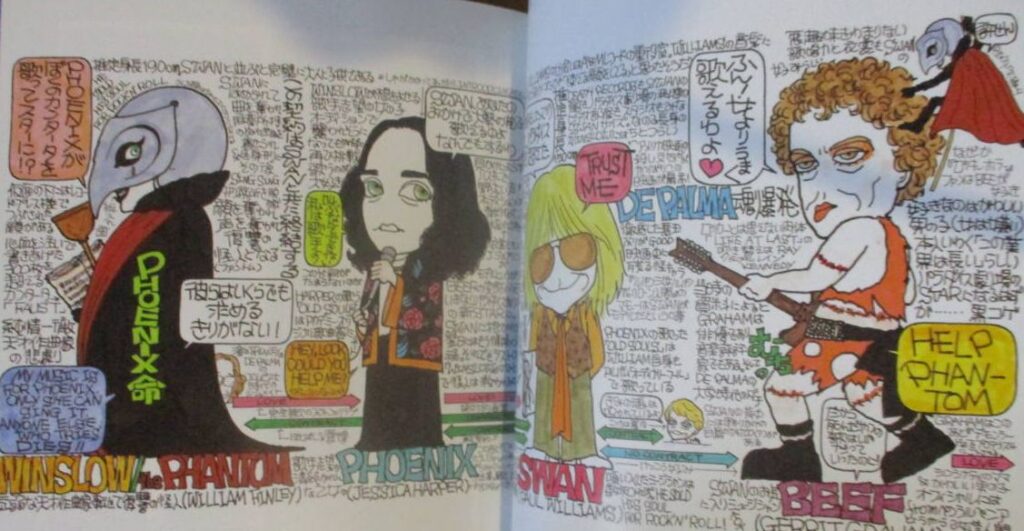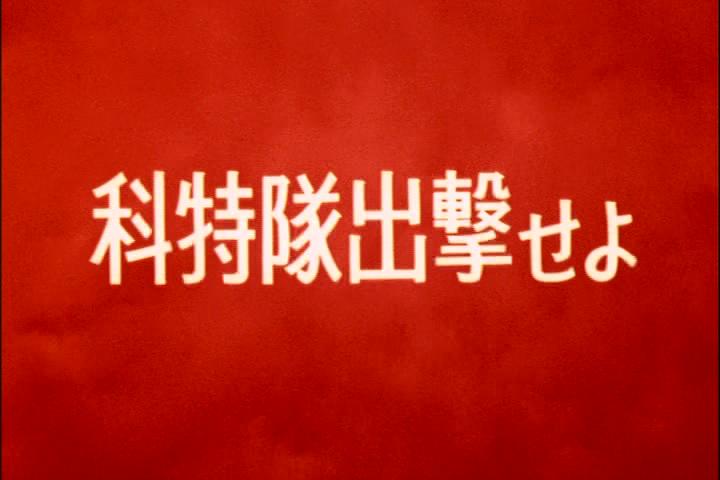しかし、その脚本を書いたのは、実相寺監督の盟友・佐々木守氏であり、そのドラマも、一見明瞭な青春熱血ドラマに見えながらも、よく読み解くと「テレビの世界なんてものは、しょせん数字(視聴率)が全てでしかなく、表現者としての拘りも成功も、視聴率だけが証明する」という、原作に勝るとも劣らない、シニカルなオチに落とし込まれていて痛快だった。
『アイアンキング』(1972年)『おくさまは18歳』(1970年)といい、佐々木ドラマの「ただ見ているだけでは、毒もない健全な明るい作品にしか見えないが、奥に詰まっているテーマは難解でイデーが詰まっている」が、健在であることを痛快に証明していた。

本書が人気を得て以降、「往年の子ども番組の主演俳優や関係者が、当時を思い出して書く回顧録本」がビジネスとして市場を持つようになり、ジャンルと化して今に至るが、それこそウルトラシリーズの元祖が『ウルトラQ』(1966年)であった事実を例に出すわけではないが、商売として成り立ち市場になると、当初のパイオニアの持った志は、遠く薄れてしまうという例に漏れない。
この書籍のロングセラー以降、実相寺監督の公的な発言も、ウルトラリスペクト、円谷プロリスペクトの側面が高くなっていくが、それは「切った仁義」が功を奏し過ぎたことへの再仁義であり、本書を書いた頃の実相寺氏の「本当の心境」は、小説という逃げ道を確保した本書の随所に見受けられる、シニカルで厭世的な視点にあったのではなかろうか。
“その視線”で仰いだ天空の、月の船に乗った金城哲夫氏が、星の林を分け進む光景を見つめながら。