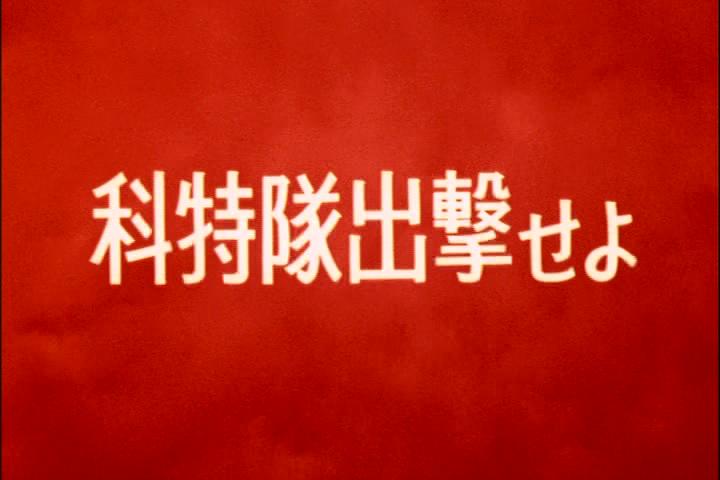あれは僕が19歳の、確か夏か秋だったと思う。そう、36年以上前のことだ。
当時、バイトをしていた店で知り合って、お約束の惚れたナンダで付き合い始めた彼女に、ある日一冊の漫画の単行本を差し出された。
「あなたを見てるとね。この漫画の主人公を連想してしまうの」
いやいや。笑うことなかれ。
なかなか実際の人生ってやつは、そういう「ドラマみたいな台詞」という奴が出てくるように出来上っている。戯作者は、意外とリアリズムというやつを持ち備えているものなのだ。
僕としても、そうと言われて差し出されてしまえば、嫌な気はせず、俄然興味は沸いてくる。
フム……と、その漫画の単行本を受け取り手にしてみると、80年代バブル期のハイセンスさと、どこかわざとらしいシックさを兼ね備えた装丁で、タイトルには『唇にブルース・ハープ』と書かれてある。
表紙には、ディフォルメされた海をバックに、洒落たショートカットの美女と、ボサボサ髪に無精ひげに、ヨレヨレのワイシャツを着こんで、銜え煙草の、目つきの険しいタフガイそうな男の横顔。
クレジットには、Vocal中村真理子 Piano狩撫麻礼 と書かれていたが、これがこの漫画の、作画と原作者のことだと知れば、なにやらニヤリとしたくもなるが。
まだまだその頃、中村真理子女史は代表作『ギャルボーイ!』を描く前であり、狩撫麻礼氏に至っては、僕はその名前を見るのも初めてであったので、読み方さえも分からず、タイトルクレジットの脇のローマ字表記で「かりぶまれい」と覚えたものだった。
歯が浮くような書き方だが、今現在(当時ね、当時の話)の僕を、好きだ、愛していると言ってくれている異性が、あなたのようだと勧めてくれたということは、すなわちこの漫画が、その異性から僕自身がどういう人間として受け止められているのかを検証する、最良のテクストになるということだけは、まだギリギリ10代の馬鹿な僕にも理解できた。だから読んでみようじゃないか。そうも思えて、受け取った単行本を持ち帰り、とるものもとりあえず、読みふけることにした。
舞台は横浜、元町、港町。いいね。お約束だ。松田優作の数々の名作も、横浜舞台が多かった。いいじゃないか。
そして、あくまで物語設定は現代。とはいっても、最初にめくった1ページ目から、登場するテレビはダイヤル式のチャンネルがついているし、そこで突然かかってくる電話も、これまたダイヤル式のぐるぐるコードの固定電話。まぁ、この辺は「だって1984年(この作品が描かれた当時)はまだ、“それ”がリアルタイムだったんだよ」というオハナシなのだが。
主人公は“センパイ”と呼ばれる一人の男。元ミュージシャンの流れ者で、今は老齢淑女のジャズ歌手のヒモをやっている。
“センパイ”の中身は……。まぁ、後の狩撫麻礼氏の代表作『迷走王 ボーダー』の主人公・蜂須賀とほぼ変わらない。
ことあるごとに
「クソッ 男のくせに健全さを売り物にしやがって。どうせレコード棚にゃ“オフコース”か“松山千春”ってとこだぜ。カスめ!」
『唇にブルース・ハープ』
「感動的な歌い手は、昔から、事故死かアル中に 相場が決まってるんだ」
「フン、俺みたいな時代遅れの本格派が、現代のウスラバカどもにウケるワケがねぇ」
等々と言い放つ。
馴染みのバーの、ヤサグレ女店主からは
「やめときなよ、あんな奴。まるで、破滅型の天才芸術家気取りだけど、実はただの、気まぐれの女好きさ」
『唇にブルース・ハープ』
だの
「つくづく幸せな男だね、あの野郎はさ。好きほうだいに生きて、ヤバくなりゃトンズラ。女はやられっぱなし。借金は踏み倒し ククッ」
『唇にブルース・ハープ』
と言われてしまう男。
そんな“センパイ”が、10年ぶりに横浜に戻ってきて、昔ワルを徹底的に教え込んだ、チー坊という弟分の下に姿を現す。
“センパイ”は、チー坊に一人の女性を紹介する。いや、勝手に遠くから指定しただけで、そのU子という女性をナンパして、結婚しろと突然むちゃくちゃな命令を下す。
どうしてなのか。当然問いかけるチー坊に、“センパイ”は言い放つ。
「オレがまだ、おまえに会う前の遠い昔の話さ。別れ際にあの女はこう叫んだ……。“待ってるからね。いつまでも。いつか、迎えに来てくれるまで”……ってな。誰でも若い頃は、それぐらいの台詞は吐くもんさ。ずーっと忘れてたんだ。だが、ある日急に、この歳になって、あのセリフが重たくのしかかってきた……。もしかして、あの女……U子は、本当に今でも、オレのこと待ってるのかもしれない」
『唇にブルース・ハープ』
「どうして、オレなのさ」と問うチー坊に。
「おまえはオレをコピーしてた。オレもお前を教育したつもりだ。オレとお前はよく似てる。チー坊、今でも“ジョー・コッカー”が好きか? “太宰治”と“チャンドラー”を何度も読み返しているか!?」
『唇にブルース・ハープ』
頷くチー坊に「よし。おまえならきっとU子も好きになる。ホレるさ」と、強引に案件を押し付けてしまうエゴイスティックな“センパイ”。
一方、U子は。
一流会社のOLで、静かで理知的で聡明な美女。
しかし、上司からのお見合いの勧めを、どんな玉の輿相手でも断り、静かにハイライトを吸いながら、ブルースのコンサートに通うだけの日々を送る。
近づいてきたチー坊から、銜えたハイライトにライターを差し出されて
「ダメよ。他人の煙草に火を点けるような生き方は」
『唇にブルース・ハープ』
と言えてしまう女性。
“センパイ”に憧れて虚勢を張って生きるチー坊に、いつしか昔の恋人である“センパイ”を重ね合わせて、親密になっていくU子。
つまり、“センパイ”の願いは、目論み通りにかなう流れになるのだが、チー坊はU子の内面の真実に気づく。
それでもU子を落とせ! 抱け! と言い放つ“センパイ”の背中に、チー坊が叫ぶ。
「U子さんは、今でもあんたが好きだ! ハイライトのこと ブルースのこと 今でも全部、あんたが教えた世界に生きてる。とてもオレなんかが割り込めないよ」
『唇にブルース・ハープ』
それでも頑なに無視を決め込む“センパイ”とU子を、なんとか引き合わせようとするチー坊。
チー坊に惹かれながらも、決して破らない殻の中で生きるU子。
二人を引き合わせておきながら、胸に抱えた悲観主義を膨らませすぎて、酒に溺れて一つの曲を作り始める“センパイ”。
遠く離れた10年間を過ごしながらも、同じ“約束”を共有しあい、その証としての「同じ生き様」をそれぞれに抱きしめながら生きてきた、一組の男と女の物語。
しかし物語本編では、二人はすれ違い、行き違いながら、決して交わることもなく、その過程で“センパイ”が作り、気まぐれでレコードに吹き込んだ歌『ルフラン』は、「愛し合っていても出逢えない、男と女の永遠の輪廻。または繰り返しの歌」と呼ばれ、世の中に出ていくことになる。
やがて、横浜の港町で各所に、『ルフラン』という名のブルースがいつでも流れるようになり、しかし“センパイ”は、自分が作り謳ったその歌さえも、唾棄するようになる。
「スケベな唄だぜ……。未練たっぷりに、誰かに向けて、キザったらしくポーズを決めてやがる。……最低だ」
『唇にブルース・ハープ』
それを最後に、“センパイ”は『ルフラン』だけを港町に残して姿を消す。
クライマックス。
老齢淑女のジャズ歌手の、バーボン一本との引き換えの一手で、夜の霧の港で待つU子の前に、一人の男が船で戻ってくる。
“そこ”で何があったのかを、僕は今、ここでは書かない。
ただ。去りゆくU子が遺したモノローグ。
「嘘よ。みんな嘘よ。嘘もあなたがおしえてくれたのよ」
『唇にブルース・ハープ』
この言葉の意味を知りたい人は、どうかAmazonでもヤフオクでも、楽天市場でもブックオフでも、どんな手段を使ってでもよいので、どうかこの一冊を手に取って、ご自身の目で確認されることを切望する。
狩撫麻礼氏は、漫画マニアならばご存知の方も多いかもしれないが、漫画原作者の小池一夫氏が設立した劇画村塾の出身であり、『うる星やつら』の高橋留美子女史などと同じ第一期生であった。
以前、狩撫氏について、懇意にさせていただいている漫画家のかたおか徹治氏が、劇画村塾時代の思い出に触れて(かたおか氏は、漫画家としてデビューしていた後に、劇画村塾に一期生として入塾した経歴がある)「彼は天才だった。普段はバーか何かのマスターをやっていて、劇画村塾にもたまにしか顔を出さないのに、来るたびにものすごい傑作をもちこんでくる。彼の漫画の主人公、そのまんまだったよ」と教えてくださったことがある。
また、やはり漫画家の江口寿史氏の『江口寿史の正直日記』では、狩撫氏の部屋には、ビールだけが入った小さな冷蔵庫と、サンドバック以外はほとんど目立った物がなかった「彼の漫画の世界そのままだった」とも記述されている。
狩撫麻礼氏の作劇をして、ワンパターン、いつも主人公が同じ人間性だ、団塊世代特有のアジテーションが多すぎるなどの批判をよく目にするが、はたして僕などからすれば「だからなに?」で終わってしまうだけの話なのである。うん、そうなのかもしれないし、そうなのだろうね。『迷走王ボーダー』のスマッシュヒットの後、再び中村真理子女史と組んで、今度は癒し系青年と頑張り屋の姉のコンビを主人公にした新機軸漫画を目指してはじまった、『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)の『天使派リョウ』も、途中から、あからさまに“女版蜂須賀”みたいな登場人物の独壇場になってしまって、主人公姉弟がすっかり脇役に回ってしまった流れがあったけど、アレははたして「狩撫麻礼原作漫画は、何を描こうとしても同じになってしまう」からなのか、それともスピリッツの編集サイドから「やっぱり狩撫麻礼なら『ボーダー』を、もう一度!」という要請があったからなのか。
どちらにしても、その後、狩撫氏が“狩撫麻礼”という名前を捨て去り(もう、この辺の選択と実行が、既に“蜂須賀”であり“センパイ”そのままであるのだが)、エンターブレインの『月刊コミックビーム』や、古巣の『週刊漫画アクション』(双葉社)等で、毎回ペンネームを変えては新機軸に挑むファイティングスタイルで、市場論理(歴代狩撫麻礼漫画主人公や『迷走王 ボーダー』の蜂須賀が、一番嫌った価値観である)からすれば“間違った”進み方をしながらも、その先できっちり、『漫画サンデー』(実業之日本社)というマイナー漫画雑誌から、ひじかた憂峰というペンネームで、松森正氏と組んだ『湯けむりスナイパー』をヒットさせ、こちらは2009年にはテレビドラマ化もされるベストセラーとなった。
毎度のことながら、こと、狩撫麻礼氏の作品になると、僕は枝葉末節の断片しか書きたくないので書かず、枝葉の部分だけを書き記すにとどめ、後はこれを読んでくださった皆さんに託すだけという手法しかとれない。
それは「書評」「ヒョーロンカ」等という存在や行為を、誰よりも“蜂須賀”や“センパイ”そして狩撫麻礼氏が嫌うことを、長年染みついてきた「魂」で知っているからでもあるが、もっと根底を模索してみた時に抗えないのは、“なぜ”“あの時”、僕が愛した、僕を愛してくれた女性は、僕に向かって、この『唇にブルース・ハープ』を差し出し「あなたに似ている気がする」と、僕に手渡したのかが、実は未だに分かっていないからなのだ。
たしかに、今の僕の、物言いだの、考え方だの、アジテーションだのを見て「なんか狩撫麻礼漫画っぽい」と思うのであれば、そりゃぁこの作品をはじめて読んでから36年間、必死に“成りきろう”として張ってきた、見栄も虚勢もあるのだからして、少しはそうも感じてもらえるだろうが、それはそれで気恥ずかしいのも本音。
むしろ、僕自身は“36年前のあの時”に、この作品に出会い、衝撃を受けるとともに、そのちょっとキザでちょっとアンニュイで、かなりハード&ルーズな、このコミック・ノワールともいうべき「横浜を舞台にしながら、限りなくフランス恋愛映画に近い世界観を、バブルの時代の空気の中に詰め込んだ作風」に、心底惚れ込み、だから(実際にこの作品と出会ったのは、単行本発売の翌年の、1985年だったと思う)すぐに、リアルタイムで短期集中連載された『アホーマンス』に追いつき、その直後に運命的な映画『ア・ホーマンス』(1986年)との出会いを果たすのだ(この辺りは、過去にここで書いた『僕が無軌道に生きた20歳までの縁との全ての結合』参照)。
“そこまでしての奇跡”が起きてもまだ、“あの時”“あの女性”が、なぜこの一冊を僕に手渡してくれたのか。
多分おそらく、人生なんてものは概ね、“そこ”に大きな意味なんてものはないのかもしれないが、おそらく、まずは中村真理子女史がレディコミに向いた画風だったので、当時の僕の彼女が、もっと乙女チックな作風を期待して手に入れて読んでみたら、案外ハードボイルドな内容だったために拍子抜けし、当時ちょうど付き合っていた彼氏(僕)が、なにやらChandlerだの大藪晴彦だの松田優作だの、『傷だらけの天使』だの、ハードボイルドかぶれであったので、惚気が程よく作用して、同一視してしまったのかもしれないとか、その程度には僕であっても、現実というものは見えているのだ(そういえば、本作での“センパイ”とチー坊の関係は、どこか『傷だらけの天使』の修と亨の関係を思わせるものがある)。
そんな“事実関係”はどうだっていいのだ。
“それ”が一年だったか何カ月だったか、その時僕が、その彼女を愛していたことだけは“本当のこと”で、その、僕が愛して、僕をその時愛してくれていた女性が、この一冊を僕になぞらえて手渡してくれたのも“本当のこと”であるのだから、僕はその“本当のこと”だけを手掛かりにして、一生フラフラと“迷走”していけばいいだけの話なのだ。
答えなんか求めちゃいけないのだと理解しつつ、この先の人生をまだまだ、その答えを模索しながら、迷走していきたいとは思うのだよね。