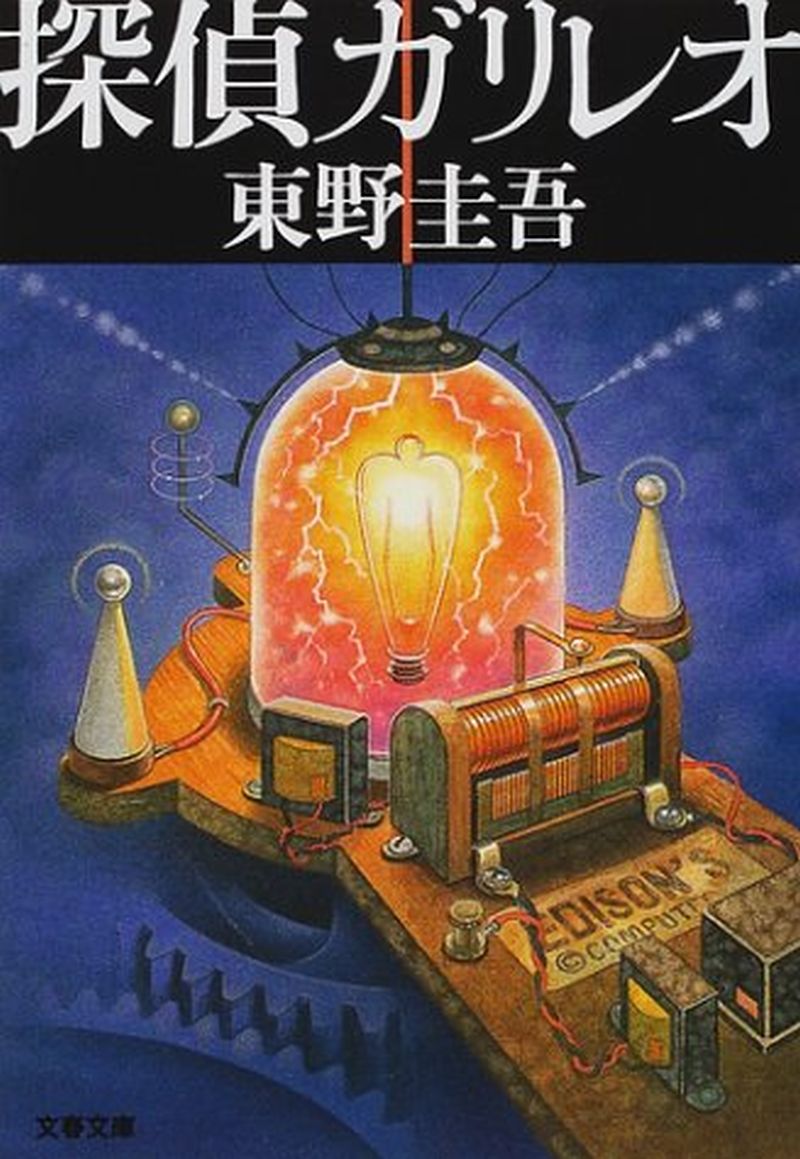このジレンマはやがて、その「心の中の闇を書いてしまいたくなるモチベーション」の背中を、押し捲る陣頭指揮者・橋本洋二氏の出現と共に、いっそう高まるのである。
金城氏は、この時期、必死に他作家作品による「日本という国家に対してと、その国家が加担した、ベトナム戦争へ対した揚げ足取り」をチェックして、それらに対するバランスアンサー脚本の執筆に追われていた。
その上で、自らが生み出したセブンを、光と調和のヒーローへとすべく、獅子奮迅の活躍と、キャパを超えた舵取りを行っていたのである。
この姿は、まさに「地球人へと姿を変えて、地球人に同調しながらも、宇宙正義や宇宙的価値観を捨てきれないでいるばかりに、常に地球人倫理と宇宙論理の狭間に挟まれながら苦悩し、人知れず両者の間で自分が緩和剤になろうと奮闘し、しかし、その姿と努力は、誰の目にもふれないばかりに、孤独なままに疲れていってしまうウルトラセブン」の姿と、近似的に被って見えてしまうのである。
ではこの時期において、ヤマトンチュではない、ウチナンチュである金城氏が、地球人ではないウルトラセブンに、本来どのようなスタンスを与え、どう動かしていくべきだったのか、という命題への一つの答えは、この時期に、金城氏に対して部下として仕えた同じウチナンチュ・上原正三氏によって『帰ってきたウルトラマン』(1971年)で描かれるのではあるが、それはまた、別の機会の評論に譲ることにしよう。
かように、迷走していった金城セブンが、どのような結末を迎えたか。
それは、この評論連載をお読みになっている皆さんの、殆どがご存知かと思うが、一つ言えることとしては、セブン放映時、全世界を巻き込んで混沌化していたベトナム戦争とアメリカ。
そのアメリカこそが、日本と同調し、同盟を結びながら正義を名乗り、客観的には狂騒的な偏執的な拘りで、ベトナムを手に入れようとして、国を襲い、村を焼き、人を殺し、狂い疲弊していく過程で、それでもなお、沖縄を巻き込みながら、その「血を吐きながら続ける、悲しいマラソン」の歩みを止めることなく、突き進んでいった現実を思うとき、そのアメリカの正義を信じ、アメリカに追従する日本を信じ、どれだけそこに、血なまぐさく醜悪な現実が見えてこようとも「それでも日本・アメリカを仰いで、生きていかなければならない沖縄人」として、頑なにすがろうとし続けた、金城氏の思いが、この作品のラストシーンにおける、ダンの台詞に込められているのは間違いないだろう。
金城氏は信じていたのだ、アメリカを、日本を。
そしてそれら「国家」という枠組みが、人類が築いた社会形態が、いつか必ず社会を救い、地球を救うのだと。
そして、それら個々に概念が違う思想を持つ、国家の隙間を埋めて、垣根と国境を越えて、絆が結ばれる日が必ずや来るのだと。
そして。
その、思想や価値観が違う、国家同士を真に結びつける要素こそ、国家理念が違っても、共通するはずの「正義」なのだと。
金城氏が、正義という概念にしか、国家同士の共通性を見出せなかった背景には、きっと、国家という枠組みに対する、果てしない絶望があったのかもしれないが、金城氏に流れている血の根本・琉球という国家が、アメリカ・日本という国家に翻弄され続けてきた、歴史を見返すとき、ここでセブンが語った「正義は一つ」という言葉を、我々には笑い飛ばす権利はないのかもしれない。