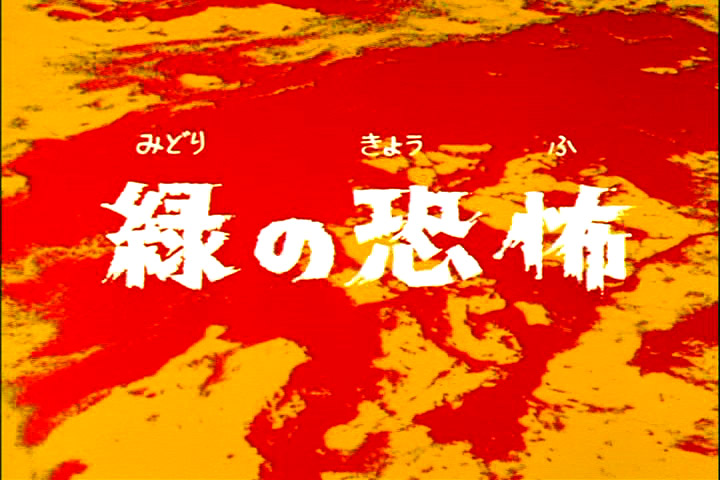一方では残念な欠落もある。
それは、毎度筆者が主張する「性の壁」としての、女性漫画家の小林女史ゆえの限界で、「男子主人公の辰吉のリアリズム」である。
それは、高橋留美子女史の『うる星やつら』のあたるや『めぞん一刻』の五代君にも共通して言えるのだが、少なくとも、劇中の恋愛でのいろいろ(もえとの)駆け引きや競り合い等を見ていると「あ、これはないな」という描写も少なくはない。
例えるなら、第36話『たまにはこんなラヴ・ストーリー』で、例によって本気なのか冗談なのかが判別できない(概ねにおいて異性作家は、異性の「その辺」って、「分かんない」から考えてないっていうのはある。東野圭吾氏の描く女性犯罪者みたいに)フランキー生徒会長からもえへの、ナンパ公園デート待ち合わせ騒動にしても、コミックス1巻の、初動の頃のもえと辰吉の関係性ならともかく、ドラマで言えば第3クールが終わる話数で、そこで辰吉の位置にいる“誰がどう考えても、自他ともに認める彼氏”であれば、あれほど頑なな、無視を決め込む態度はとらない。一言「行くな」と言えば済む問題であれば、意外と男子ってバカだから、素直に「行くなよ」とは言っちゃうものなのよ、とは元(今現在も)バカ男子の大賀さんは、素でそう思ったりもする。
あと、やはり男性脳的には、辰吉は確かに愛すべき男子ではあるが、最終回直前、某校生徒全員から信頼されながら、フランキーの次の生徒会長の椅子に納まる流れがあるのだが、はて、もえはともかく、辰吉個人にそれほどの突出した求心力があっただろうかと、その辺りはやっぱり、男としては多少納得がいかなかったりはするのだが。
しかし、こと、もえをはじめとした、もえの親友・岩(信じがたいが、これでちゃんと少女の苗字)や辰吉の母親、周囲の女子生徒など、女性の恋愛における心理の微妙な浮き沈みや葛藤、揺らぐ自尊心やコンプレックスなどは、これは本当に、体臭が嗅ぎ取れようかというほどに生々しい。
下手な少女漫画やレディコミが、女子の「夢」を相手に商売しなければいけない分、ある程度「少女としての理想像」を、メインヒロインに植え付けなければならないビジネスロジックがあるだけに、逆に青年漫画雑誌を舞台にした本作のもえの方が、どんな少女漫画のヒロインよりも、生々しかったりした。
辰吉の過去を知り、嫉妬し、自分が辰吉のオナニーの道具になんかなりたくないと、刃物を振りかざしたかと思えば、それまでの期間を、周囲のコンプレックスに気遣えずに振る舞えるほどにエネルギーをもらえてたのは自分自身であり、それは逆に「辰吉君に愛されている自分が気持ち良い」という状況だからこそ、明るく酔えていたわけであり、結局自慰行為に浸っていたのは自分なんだという回答に至る経緯。
その上で、瀬戸内寂聴のパロディみたいなテレビの尼僧の言うことを真に受けて「愛とはもらう物ではなく、与える物なのです」を真顔で頷いて、それを実践しようとした結果「てるてる坊主をつるして晴れを願っても、雨が降るときは降る」で、全てのトンネルから抜けて大笑いして(往年の、レナウン娘CMソングを歌いながら)一件落着するまでの流れは、どんなサスペンスジェットコースタームービーよりも、緊張感が高く、次の展開が読めずハラハラしながら、見事ハッピーエンドに着地しながらも、そこまでのプロセスがあまりに「男性にだけは分からない」「しかし、明確に、分かりやすく」描かれている心理の推移に、当時まだ思春期を抜け出せていなかった筆者などは、何度も何度もその流れを反復しては、自分の拙い恋愛経験からくる「あの時、自分の彼女も、こんな葛藤の中にいたのかもしれない」と思えば、なるほど全ての謎は解けたんだけど、時間は巻き返せないから、終わったテストの答え合わせで、落第点を取ってしまったバカならではの反省点ばかりを突きつけられてしまう感が半端なかった。
その上で、「女は本当は、男よりも強いんだ」という、筆者の亡母さんの言葉をそのままカリカチュアしたかのような、体育祭前後での、女子の「強さの底力」をネタに、ギャグとバイタリティで描き切った第27・28話『絶対秘密の100万パワー』や、教師による生徒イジメ(第11話『そんな小さいこと』)も、小学生の間で揺れ動く、道徳の崩壊(第15話『DOUTOKU』)等、サブカルチックなギャグと台詞の押収の中に混ぜ込まれた、数々の「思春期だって子どもだって、社会と地続きで、そこで笑顔になるには、楽しくやるには、絶対に環境論が必要なんだ」を、決して外さず描く小林じんこ女史は、「本当の10代」を、描き切ってみせてくれた。