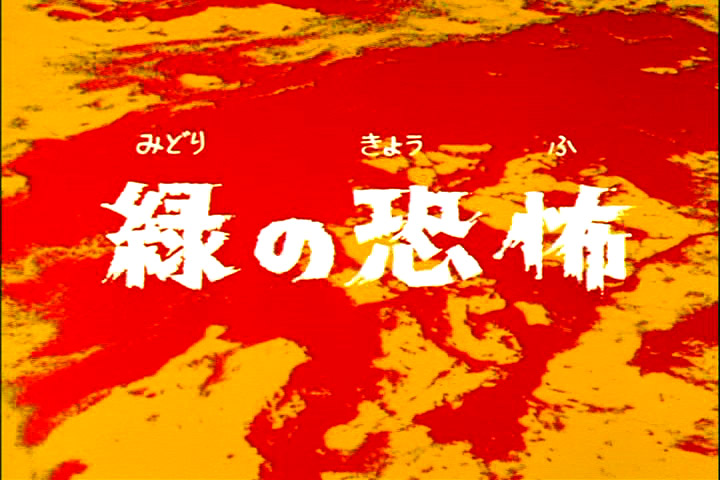筆者のミステリー文学購読撤退に関しては、もう一つの主原因として、赤川次郎氏の台頭が挙げられねばならない。
昭和世代の当サイト購読者さんであればもちろん、80年代に赤川氏が『セーラー服と機関銃』や『いつか誰かが殺される』『晴れ、ときどき殺人』などで(主に角川映画とのマッチメイクで)巻き起こした、いわゆる「赤川ミステリーブーム」をご存じかとは思うが、だがしかし、筆者の場合は当時、勢いと宣伝と評判に釣られて手に取った赤川文学に対して、その内容の軽さ、センスオブワンダーの無さなどから、嫌悪感と絶望感にも似た読後感を抱いてしまったことが、その後ミステリージャンルそのものから、距離を置いてしまった遠因にもなっている。
それは、あくまでもニーズの問題だったのっだろう。
そもそも、筆者個人がミステリー文学に望んでいたのは、あくまでも、あっと驚く仕掛けやトリックといった、本格推理要素か、犯罪という波紋が呼び招く非喜劇を冷徹に描く、リアリズムタッチの文学世界だったのである。
しかるに赤川文学は、そのどちらにも属さない、軽い文体とテーマで、気軽・手軽に読めるという、今の時代のライトノベルの先駆けのような存在であった。
もちろんそれは、なにより時代のニーズであったし、本格派・社会派ともに行き詰まりを見せつつあった当時のミステリー文壇においては、突破口にならんとするだけの気概と文才と、また「新しい、若い読者層の開拓能力」までをも、赤川次郎作品が兼ね備えていたことには異論はない。
なので筆者は、当時から批判はしなかった。
江戸川・横溝的な、本格的名探偵推理小説も、松本・水上的な、社会問題犯罪小説も、どちらも既に時代に取り残されて、80年代も中期を迎える頃には「ミステリー」というジャンルそのものが、好事家だけが嗜む、酔狂な趣味領域の袋小路へと追いつめられていたことは、筆者のような門外漢の目でも、はっきり認識できる程度には、日本推理文学は行き詰まっていたのである。
映像文化華やかりし、その80年代という時代にあっては、小説が頑なに守る、そこに書かれている文字列のみと読み手が真剣に向き合い、知力を振り絞ってイマジネーションの世界で作者とゲームに興じるという娯楽は、既に時代遅れのそしりを免れず、むしろ、形骸化し、ニュアンスとエッセンスだけを残しつつ、その実、中身は重たさも深刻さももたらすことなく、ライトな消費財としての立ち位置を確保するという意味では、赤川式ミステリーは、推理文壇においては巧みに機能した。
さっそく、というかあざとく、というか、赤川式ライトミステリージャンルは、すぐさま辻真先氏や日向章一郎氏などのエピゴーネン追従者を生み出したし、同じような行き詰まりを感じつつあったSF小説界においても『クラッシャージョウ』『グイン・サーガ』等々、その後のライトノベルの礎になる作品群が、この頃に生み出され始めた事実も、忘れてはならない。
この段階において、決して誤解されたくはないのは、この時期、赤川氏がミステリー界にもたらし持ち込んだ手法と技法、そして赤川氏の基本的なポテンシャルに関しては、筆者は決してその評価を軽んじるものではなく、むしろ、この時期においてはドンピシャで、このスタイルで新風を吹き込むしか、ミステリー界の動脈硬化や行き詰まりを打破することは、出来なかったであろうことは容易に想像がつくので、氏の功績や実力を、称えることはあっても貶めることはない。
ただただ、筆者が(身勝手に)ミステリーに求めるものが、そこ(赤川作品)にはなかったというだけのことなのだ。
しかしそれは(何度も繰り返し述べるが)時代の流れと、硬直化した推理文学が省みるべき要素だと、そこへの理解は自覚していたので、筆者は黙って、推理小説界という船から降りて、港で見送る道を選んだのである。
娯楽はいつでも、普遍的かつ大衆的なレベルと難易度で始まるが、そこで食いついた熱狂的な一部のファンの、エスカレートするニーズに応えようと、どんどん先鋭化していった結果、気がつくと、敷居が高くなりすぎて、一見さんお断り的な、閉鎖的排他的な世界に閉じてしまうということが、怏々として起きてしまう。
近年で、分かりやすい例で言うのなら家庭用ゲーム類だろう。格闘ゲーム、シューティングゲーム、RPGなど、本質的にはどれもこれも、楽しくて面白いものなのに、いつのまにやらシステムや操作法が複雑怪奇化してしまい、とてもじゃないが、素人には手を出せない敷居の高い代物になってしまっている。
それもこれも、ヘビーユーザーやマニアによる、「ここはもっとこうしたら」「これを取り入れればもっと面白くなる」などの意見を、「常に進化し続けなければ」という無言のプレッシャーの中で、送り手が無思慮に取り入れ続けた結果である。
「それ」を繰り返すことは、そのプロセスにおいてどんどんと「『もっともっと』がエスカレートするヘビーユーザー」と「着いていけずに置いてけぼりを食らって脱落するライトユーザー」の二極化を生む。
そして、ユーザーの分母が増えることもないまま、次々に後者(脱落者)は生み出され、前者はその数をトーナメント戦のように減らし続ける以上、その手法を繰り返している限りにおいては、その市場がシェアを拡大することはあり得ないのだ。
では、どうすればいいのか?
勇気ある決断をもって、その悪循環を断ち切るしかない。
それらゲームと、ほぼ同じ経過で行き詰まりを見せていた日本の推理文壇は、「あっと驚くトリックがあるわけでもない」「読む人を唸らせる、大どんでん返しがラストに待っているわけでもない」「人生に影響を与えるほどのテーマがあるわけでもない」「犯罪という行為を通じて、社会を討つわけでもない」そんな赤川次郎氏の登場と活躍によって、一気に活性化し、息を吹き返し、その後大量に産み落とされた、赤川氏のフォロワーと同時に、大勢のカウンターを呼び覚まし、文壇に召還することで、日本ミステリー文学界そのものが、それまでにないステージへ進化するきっかけを得たのだった。
つまり、東野・宮部・綾辻といった、この直後の時期に次々と頭角を現し始めた「日本ミステリーニューウェーブ組」は「赤川次郎を生みだしてしまったミステリー文壇に対しての危機感」が産み落とした(もしくは招き寄せた)「ポスト赤川」であると同時に、「カウンター赤川」ともいうべき存在であったのだとはいえないだろうか(それはいずれ東野圭吾論で述べたいと思うが、東野氏のデビュー昨『放課後』における文体や全体の空気感、そこには確実に、赤川氏の影響下にある部分と、アンチ赤川ともいうべき、東野氏ならではの原石の部分がはっきりと混在しており、東野氏における『放課後』から『新参者』までの25年は、その比率を、限りなく0:10へと近づけていく課程だったことが、氏の作品群を年代順に追いかけていくと分かるのである)。
事実、この世代の作家達は皆、凡庸な「本格派」「社会派」の枠に縛られることなく、しかしそれら「先人が積み上げてきた物」を決して軽視するのでもなく、赤川氏がミステリー界に強心剤を打ち込んだことで、血が巡り、体温を取り戻しつつあった推理小説という娯楽に対して、改めて、新しい可能性とビジョンをもたらそうという希望をみせてくれたのである。
さすがに、今回の論だけを以てして、筆者が背を向けていた「推理文壇の四半世紀」の全てを今回取り戻そうなどというのは、無謀にも程があるが、今回、当サイトでのミステリー連載を契機に、これはちょうど良い機会なのかもしれないと感じたのも事実。
ちょっと、この先、書評という手法を使って、筆者にとっても空白だった、80年代後期以降のミステリーにも、興味を持って向き合っていこうと思っている。