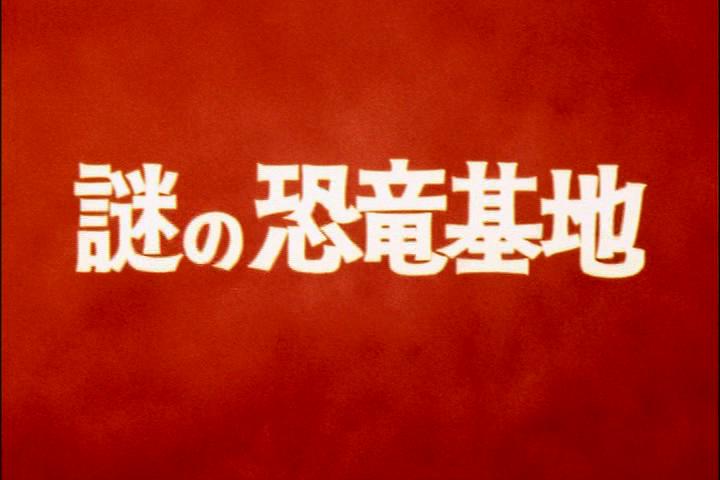本話はTBS映画部から出向した樋口祐三監督が、海堂太郎名義で脚本も執筆し、ホシノ少年を巧みに活かしたドラマ構成で、少年活劇として構成した佳作である。
樋口監督はその後TBSでは制作部に移った後、日本のドラマ史で欠かせない名作となった、ナショナル劇場版の『水戸黄門』(1969年~2011年)でプロデューサーを務めた。
樋口監督のウルトラ参加は、本シリーズのみになってしまったが、そこで演出された作品を俯瞰で見てみると『来たのは誰だ』以外の作品は、全てなんらかの形で子どもがキーパーソンとして機能する作劇に徹している。
それらの中で、樋口監督が海堂名義で書いた、つまり樋口氏単独で構築された本話と、樋口氏が金城哲夫氏と組んだ『恐怖のルート87』『まぼろしの雪山』等を、両方向性のエピソード同士を比較すると見えてくるのは、樋口監督が目指したのは「子どもが出てくる」という要素による、視聴者の子どもにとって親近感のあるドラマ世界であって、そこで子どもが、本質的な意味でドラマに関わることへのエクスキューズに関しては、むしろ余り拘ってなかったのではないかという仮説が、本話を見てみると成り立つ。
その辺りはむしろ、第二期ウルトラ的な「大人の視点」なのであるが、もしかすると『恐怖のルート87』『まぼろしの雪山』という、『ウルトラマン』(1966年)を代表する二大傑作が産み落とされた背景には、『ウルトラマン』という作品(商品)を、とてもストレートに解釈した、樋口監督からの「ゲスト子どもを主人公にしよう」というオファーがまず先に金城氏に対してあって、「子どもが鍵となるウルトラマンのエピソード」という商品コンセプト自体が、それを受けた金城氏を揺り動かしたという、そういった過程もまた、考えられるのではないだろうか?
その一方で、本話を語る上で欠かせないのが、ここで登場する怪獣ケムラーの魅力だろう。
いやむしろ、ドラマとしては、さしたるテーマも欠いた平坦なこの作品では、作品自体の魅力が、怪獣ケムラーの存在と魅力に委ねられているという、子どもが観るキャラクター活劇としては、非常に背筋が通った完成度を誇っているのである。
そしてこの作品を飾った主役・ケムラーを語るときに、忘れるわけにはいかないのが、初期ウルトラ怪獣の着ぐるみ造形作家として、今も語り継がれる稀代の芸術家、高山良策氏の存在ではないだろうか。
今回はその高山氏に関して、ちょっと書き記してみたい。
高山良策氏は戦前の1917年に山梨で生まれた。
画家志望の兄に啓発される形で、自らも画家を志そうとするが、卒業後は製薬会社でサラリーマン生活をするようになる。その時期、高山氏の運命を変えた出会いになったのが、画家・福沢一郎氏との縁であった。
福沢一郎氏は、日本芸術界において、きわめて初期にシュールリアリズムを確立した画家であり、日本の前衛芸術史を語るときに、なくてはならない存在である。作品的には1930年に発表された『溺死』を初めとして、『オームのいる群像』(1956年)『埋葬』(1957年)、『SLUM LORDS RICH ON OUR MISERY』(1965年)など、日本が高度経済成長を迎えようという、まさにその時期に、鮮烈な色使いとダイナミックな構成力で、日本美術界に前衛芸術の楔を打ち込んだ。
そんな福沢氏が1936年に、自宅アトリエの二階に開設した福沢一郎絵画研究所に、高山氏は1940年、日本水彩画会展に入選したのをきっかけに参加。そこで絵画を本格的に学び始めたのである。福沢一郎絵画研究所には、同時期に大塚睦氏の他、入江比呂氏、山下菊二氏らも参加して、後に「日本前衛美術界の拠点」と称されることになった。
(余談だが、シュールリアリズムの世界ではなぜか牛をモチーフにすることが多く、たとえばあのピカソも1938年に『ローソク・パレットと牡牛の頭』という静物作品があるし、現代アーティストとして知られる石川雷太氏の作品でも、屠殺された牛の頭部などがモチーフとして使われている。当然、日本シュールリアリズムの元祖でもあった福沢氏の作品にも、1936年に描かれた『牛』という作品があった。そういった前衛芸術史的な観点から見た場合、高山氏と、同じく前衛芸術の世界で活躍した成田亨氏がコンビで生み出した『ウルトラセブン』(1967年)のエレキングなどは、二人の前衛芸術家コンビによる、そういったアプローチの一つと解釈できないだろうか?)
そんな前衛美術の拠点であった、福沢一郎絵画研究所であったが、前衛芸術というスタンスやそれに伴う思想が、時の権力体制に目をつけられることになり、福沢氏は治安維持法違反の容疑で特高警察に検挙され、そこで研究所は解散になってしまう。
その後、高山氏は、1951年・1952年に連続して日仏現代美術賞で二等賞を受賞。前衛美術協会にも参加し、この時期から氏の画風もどんどん変化を遂げるようになって、画家としての代表作となる『抽象』を、1958年に描きあげた。そしてミクストメディアという手法で描かれた『黒い底で』『二つのニッシェ』(共に1960年)などを次々に発表。これらは幻想的抽象表現と、有機的な生理表現を混在させた新しいスタイルだとして、当事の日本美術界では、高い評価を受けることになった。