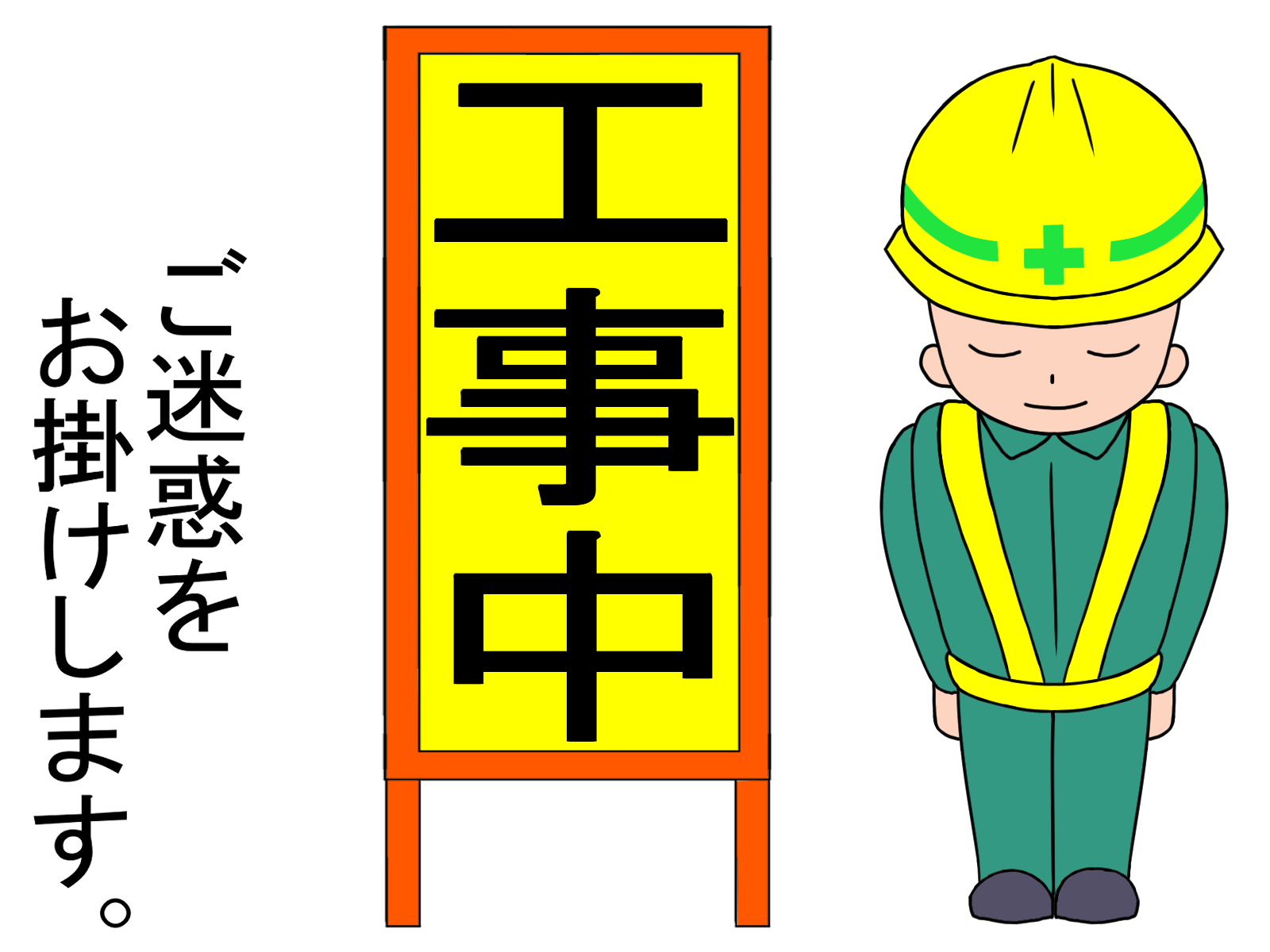子どもの為に命を授かり、子どもの為に存在し、そして子どもの成長と共に消え去る。高山氏にとって怪獣とは、そんな存在だったのかもしれない。
「怪獣というものは、この世に生まれなかったか、あるいは生まれても、いったんはすでに滅びた生き物ですから、これは断じて正義ではない、正義が滅びる道理はないんですからね。怪獣はだから悲しいのです。カタチは恐ろしくても、よくよく眺めると哀しくて、面白くて、愛嬌のある生き物です。(中略)この地球上において怪獣はもう一度だけ、自分の存在を主張する権利を持っているのではないでしょうか」
『週刊サンケイ』インタビュー1971年
時代は流れ、テレビや映画の世界を席巻した怪獣様の時代も、そう長くは続かなかった。怪獣文化が下火を迎えつつあった70年代中盤頃から、高山氏は徐々に絵画の世界へと戻っていった。その時代の高山氏の作風や、そこで絵画などの作品に込められていたテーマについて、2006年に川崎市岡本太郎美術館で行われた「ウルトラマン伝説展」のパンフレットではこう評されている。
「主題として選ばれる題材は社会への厳しい風刺ではあるが、表現方法に大きな変化が見られ、幻想的ではあるが具象的表現が前面に押し出されてくる。さらに年ごとに幻想性は高まり、社会の強さに潰されてきた者を、幻想的な高山独自の表現の中で、強さと弱さの共存する世界に置くようになっていく」
それはきっと、高山氏の中で奏でられた、幾多数多の怪獣達へのレクイエムだったのかもしれない。怪獣はいつだって社会の枠からパージされた存在であり、彼らに真の居場所は最初からなく、30分という限られた枠の中で、自分の存在を一度だけ主張して、ゆっくり目を閉じて消え去っていく存在であることを、脚本やドラマよりも、一番最初に感じて表現していたのは、高山氏だったのかもしれない。
そう考えれば、その主題そのままのテーマドラマだった『怪獣墓場』を撮った実相寺監督が、人生晩年、最後の仕事の一つとして、高山氏の功績を伝えた映像ドキュメンタリー『怪獣のあけぼの』を作ったというのは、実は偶然ではなかったのかもしれない。
「社会の強さに潰されてきた者」とは、もちろん氏が手がけた多くの怪獣に重ねあわされる。そして「強さと弱さが共存する幻想世界」とは、まさにそのままウルトラマンと怪獣が共存する、幻想世界に通じていたのではあるまいか。もし、それが筆者の思い込みゆえの解釈だったのだとしても、高山氏の、画伯としての人生の中で「怪獣」が与えた物は、きっと息づいていたに違いない。
少なくとも美術論壇の世界では、高山氏の描く絵画の作風が、怪獣時代を境に、社会風刺・文明批判などから次第に、縄文崇拝などと共に、より自然な、より体温を感じる世界観へ、変化していったという認識だけは確かなようであった。
それはもしかすると、氏が怪獣造形において、ウレタンやラテックスへ込めていた体温が、怪獣造形を離れた中で、より本来の創作である絵画へと、込められていった帰結的な結果なのかもしれない。
晩年、高山氏は肝臓癌を患い、闘病生活の果てに1982年に逝去された。
氏の最後の作品は、病院のベッドの上で描いた、自分自身の点滴中の、左腕のスケッチだったという。高山氏が最後に手がけた作品は、病気と闘う自分自身であったのだ。
ひょっとすると高山氏は、死を前にした自らを描く行為によって、自身が産み落としてきた怪獣達の住む世界へ、自分自身を落とし込んだのかもしれない。
没後も高山氏の功績を称えるイベントやモニュマンは後を絶たない。
高山氏の故郷でもある山梨県西桂町小沼では、町おこしの一環として1995年から高山氏の作品展示やイベントを開催している。また、同じ山梨県の山梨県立美術館では、高山氏の最高傑作とも呼ばれている油絵『傘のある風景』(1951年)が常設展示されている。
2001年には練馬区美術館で『高山良策の世界展』が、そして2003年には、池袋アーティストガーデンのオープニングイベントとして『高山良策展 刻まれた幻想空間』が開催されている。
氏が紡ぎだした怪獣達の生命力は、今もまだ怪獣を愛する少年達の中で息吹いている。氏が怪獣達に与えた「一瞬だけ主張できる存在」は、決して消えない刻印となって、怪獣と共に少年時代を過ごした全ての人達の中で、今もまだ遠吠えているのである。
高山良策
日本戦後美術界において、前衛芸術の旗手として活躍。
社会と人の繋がりと、縄文文化が持つ人の暖かさを追い求めた表現者。
1982年7月24日。肝臓癌で逝去。
享年62歳。