そしてメインの『紀伊』パート。正式なサブタイトルは『紀伊熊野の地之龍』。
以前も書いたかもしれないが、数年前に筆者は映画の企画に呼ばれて脚本を書いた。
それは「時代劇怪獣スペクタクルファンタジー」ジャンルであり、某カースタントプロダクションの50周年記念映画になる予定だったが、資本や協力関係があまりにも雑多にカオスになってしまったため、物語が、企画者の当初の構想を離れて迷走を始めてしまった。
その企画者が、(株)アルバトロスジャパンの村田修一氏であるのだが、筆者はその企画が袋小路に入った段階で声を掛けられ「一回まっさらな状況から、まともな脚本を書いてくれ」と頼まれ、正式な契約を経て2時間尺の脚本を手掛けた。
しかし、様々な事情から、その映画はお蔵入りになり、筆者の脚本も村田氏が絶賛してくれた出来に仕上がったが、こちらもお蔵入りになってしまった。
それから数年、あまりにもその作品がもったいないので、村田氏の許可を得て小説化しようと思い立った。
しかし、悲しいかな時代劇映画の脚本は書けたが、それを小説化するとなると、詳細かつ正確な時代考証と描写が求められる。むしろ、題材がモンスターファンタジーであればあるだけ、時代劇の世界観ベースは、正確さと細やかな描写が求められる。
ところが、筆者には、そこまでしっかり時代小説を書けるだけの、知識も考証能力もない。
司馬遼太郎や池波正太郎は大好物だが、御大先生方の諸作品がフィクションならではの嘘で書かれていることもしっかり知っているだけに、付け焼刃は致命傷になりやすい。
なので、熟考した結果、アクロバティックな手段をとることにした。
そもそもの映画脚本で書いた出来事、モンスターファンタジーの活劇シーンを「150年前の出来事」ということにして、小説版は現代を舞台にして、そこに「150年前の出来事」が絡んで、それと「折口くん」が向き合う、というスタイルをとることで、原作映画脚本オリジナリティを侵食せず、小説が独立して存在する価値をもつことに成功した。
なので、このパートのクライマックスは、決して怪獣退治ではなく、別の形の脅威と向き合い、解決するまでを描いている。
前回「今回の小説はディスカッションドラマである」はアジテーションしたかもしれないが、そこは筆者も古参オタク。
このシリーズは、毎回『古事記』や『日本書紀』に材を求めながらも、そこで起こる超常現象や怪奇現象に対して、「インテリ主人公」「有能だがおっちょこちょいで憎めない助手」「マスコット的存在ではあるが、時には事件を解くカギにもなるヒロイン」というトリオで物語が進行するという、いわば「市川大賀版『ウルトラQ』(1966年)」であるともいえるなと、ここは書き終わってから気付いたりしたものである。
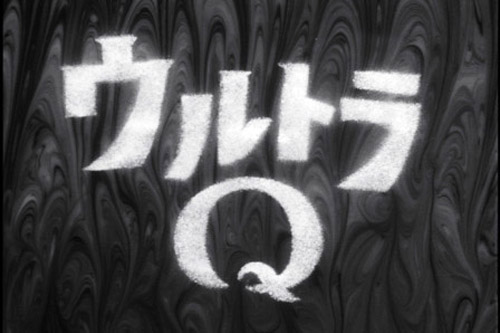

本シリーズを、今後も続けていくかどうかは、そこは資本主義の原理で売れ行き次第なのだが(笑)、筆者としては思春期から私的に書き続けてきたシリーズなので、機会さえあればなんらかの形で続けていきたいと思う。
まずは第二報。
8月上旬には、正式な購入先リンクと共に、改めてご紹介出来ると思うので、ぜひ続報をお待ちくださいませ。



















