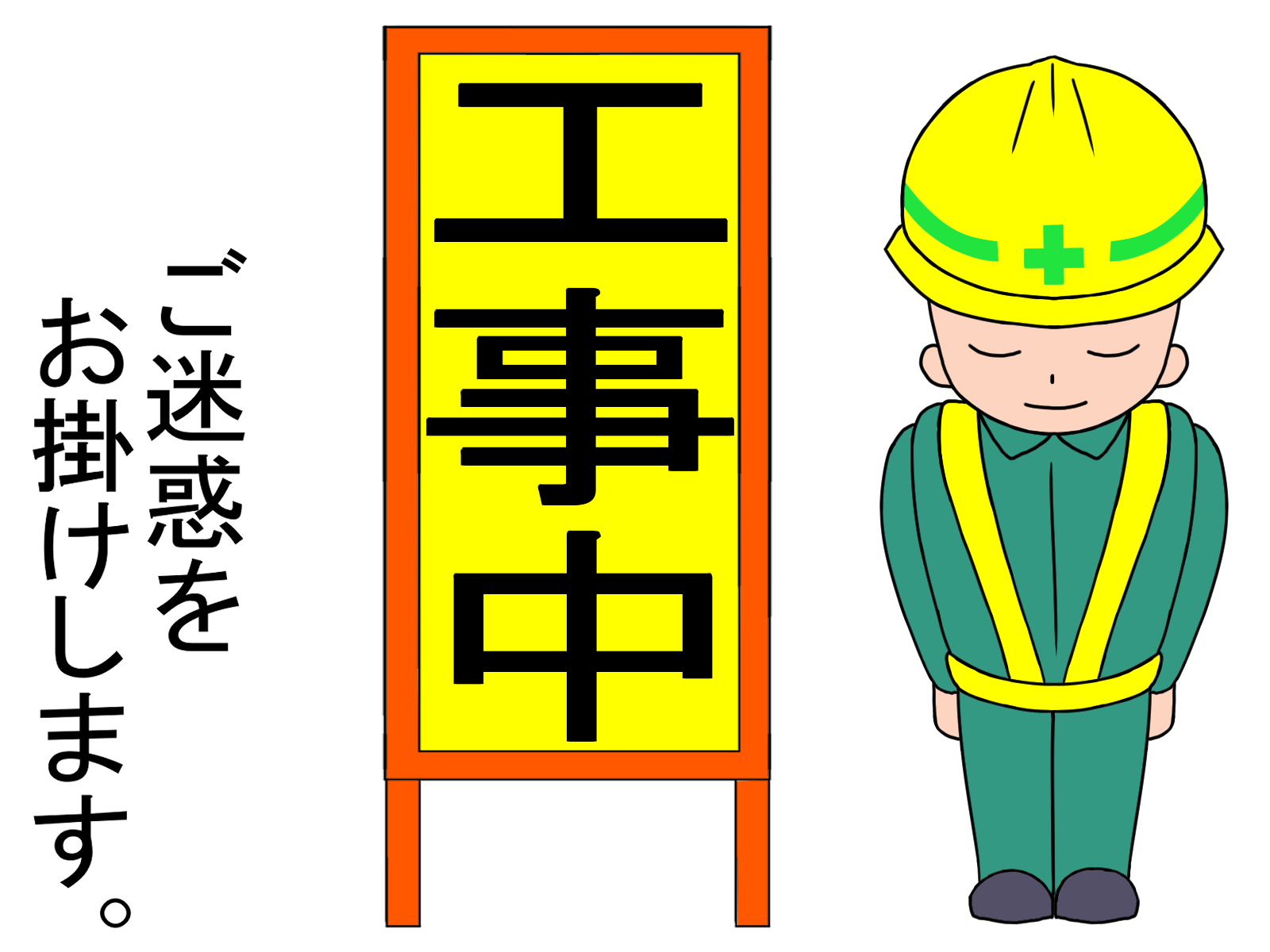“親分”の死 二度目
一方で、劇場版3作目制作渦中の1981年10月、日本サンライズ社長(当時)の岸本吉功氏が急逝した。富野監督にとっては、長浜忠夫監督急逝に続いてのショックであった。
その時の心象を、富野監督は自伝でこう記している。
しかし、岸本社長の死については、他人事ではなかった。自戒しようにも、抗し難い事実の展開 に、僕は、人の運のめぐりあわせに正直息をのんだ。
アニメージュ文庫『だから僕は…』富野由悠季著
なぜならば、オオタキ・プロの大滝社長(引用者註・富野氏が、虫プロ退社後に一時期所属していたCM制作会社の社長)の死んだ時に、僕は“二度あることは三度ある”という格言を信じ、以後は一人でやってゆこうと決意した。だから、日本サンライズに長く居座るということは、構造的に僕は岸本を親分にしたことになるのではないのかと懸念した。そのために、フリーとしての立場に固執して、岸本を日本サンライズの社長以上に思わないように努めていた。
しかし、構造をくつがえすわけにはゆかなかったのだろう。不克心ならず目というロ惜しみである。どこかで、僕は日本サンライズをあてにしていたのである。
そのために、岸本は死んだのではないのか、という疑義が僕に残ってしまった。僕は岸本の奥様だって知っていた。虫プロ時代の後輩に当る。その彼女に対しても、なにか、ひどく申しわけないことをした、と思っている。
僕が、創映社に来た時に予感したことが、現実のものとなったのではないか……という事実の展開は辛い。これを、僕は感じすぎとは思わない。人間の縁というものは、こういうものなのではないのか、という感覚があるからである。そういった感覚がなければ、「イデオン」とか「ダンバイン」の世界を創出することはできなかった、と思っている。
また、岸本社長急逝直後に収録された、『月刊アニメージュ』1981年12月号 「THE DIALOGUE 富野喜幸VS高橋良輔」では、サンライズ同窓の富野監督と高橋良輔監督が、対談でこう語りあっている。
高橋 トミさんの場合は、あるところで、親分を作らずという一匹狼宣言みたいなものをだいぶまえにして、それを守っているわけで、サンライズと互角にというところもあると思うんです。ぼくの場合は、自分のグループがあって、仕事をいろんなところでやるんですけれども、作り手の主体になるときには、どうしてもサンライズを選んでしまう。
富野 で、似ているところは、個人のクリエイティブな意識という部分に、ふたりともかなりこだわっている。そのふたりの共通の体質をくみ入れてくれる体質が、またサンライズにはあったんですね。
高橋 体質ね(笑)。
富野 それが、今回の岸本社長の死によってわかったことがひとつあるんです。それは、アニメのプロダクションというのは、その社長の人格の反映が会社だということが、間違いではなかったということを痛感した。
AM(引用者註・アニメージュ編集) それは、どういうことですか?
富野 つまり、ある時期の日本サンライズのカラーは、半分は長浜(忠夫)さん、半分はぼくが作ったとうぬぼれていた時期があるわけです。長浜路線と富野路線が両輪としてあるという感じでね。でも、そういうクリエイティブな面を保証することを岸本社長がかなり理解していて、さい配していた部分がある。結局『ハゼドン』にしても『0テスター』にしても、それぞれ、出崎統とか高橋良輔とか、個人のクリエイティブな面にこだわる人をCDに設定していったというのは、岸本社長のさい配があったからこそだという気がする。で、岸本社長が日本サンライズを仕切っていなかったら『ザンボット3』も『ガンダム』もなかったんじゃないか、そういう作品の風土をもたせてくれた日本サンライズの大きな政策は、岸本社長のもとでできあがっていったと思うんです。
高橋 いまトミさんがいったんですが、まさにそのとおりでね。岸本社長、なんにもしない人なんですよ。なんにもしないというのは、策をめぐらせないという点で、なにもしない。でも、なにかがおこったとき、寡黙になって正面にたってがまんするんですよ。それで押し切ってしまう。ああいう人が社長資質なんであって、でもそのへんの無理がかなりあったと思います。あの人のかげで、ずいぶん風をよけていたからね、ぼくらも。
富野 そう、ぼくなんか、個人プレーでかなり好きなことやらせてもらってたから、対スポンサー、対TV局ということえはたいへんだったと思う。
高橋 でも、岸本社長は実にしぶとい道を教えてくれたよね。つまり、相手のいうことをひとつは聞こう。でも、のこりの9つは、なんとかやりたいことができるんじゃないかっていうしぶとさをみせてくれました。
富野 もう、どうしようもない、というとこまでひっぱっていってくれるのね。それで、こちらが「こう軌道修正すればすむでしょ」というふうにわかるところまでひっぱっていってくれたんです。ふつうなら、途中でいくらでもつく作品チェックを回避してくれた。サンライズの場合、それは山浦(栄二)さんだったり、伊藤(昌典)さんだったりするわけだけれども、結局、それをがまんさせてくれていたのは、岸本さんなんですよね。
その社長の死を乗り越える形で、同年末12月27日には、朝日新聞の一面広告を全面カラーの、大河原邦男氏による「ガンダムのラストシューティング」のイラストが飾り、『機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙編』前売り発売告知が掲載された。
この時のキャッチコピーは「Last Shooting ‘82春 ガンダムは人類変革のさきがけとなる」