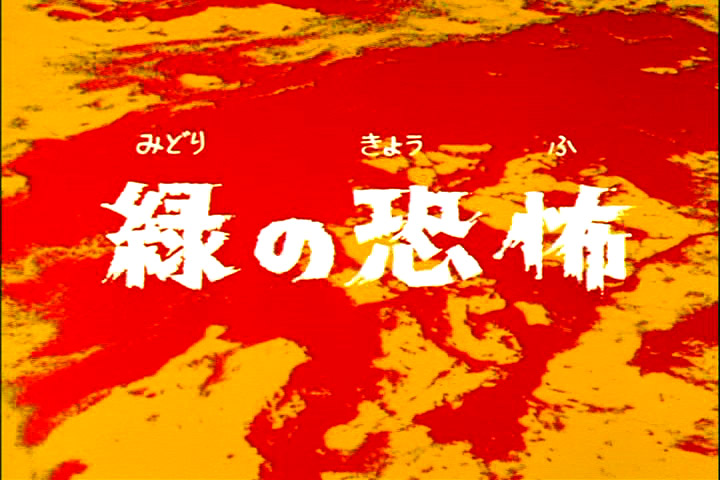今ではアニメ脚本家の大家として、また『宇宙皇子』をはじめとするライトノベルの元祖的な小説家として、広く認知されている藤川桂介氏はこの時期、『ウルトラマン』(1966年)『ウルトラセブン』(1967年)『快獣ブースカ』(1966年)などで、円谷作品と深くかかわりあっていた。
藤川氏は、本話の監督でもある飯島敏宏氏が、円谷プロに呼び込んだのではないかと、筆者はそう分析している。
そもそも飯島敏宏監督と、藤川桂介脚本のコンビは、1961年にTBSで製作されていた人気ドラマ『月曜日の男』からの縁で成立したと思われる。
飯島監督はこの作品からは、藤川氏の他にも若槻文三氏・山田正弘氏などを、円谷作品に招聘したと思われるのだ。
『月曜日の男』とは、当事のスパイ物ブームを背景に、『暗黒街の顔役 十一人のギャング』(1963年)などで知られる、待田京介演ずる探偵小説家・持等院丈太郎(通称J.J)が、毎回起こる様々な事件を、華麗なアクションで解決していくという、後の『探偵物語』(松田優作主演・1979年)の先駆けのような作品である。
その「事件推理アクション」というドラマでコンビを組んだ両者が、本作品において、そのドラマからインスパイアされた影響は本話にも顕著で、本話は「事件発生」「調査聞込」「科学分析」「捜査」という、疑似科学事件物としては王道を行く筋道立てで話が進行する。
そもそも、ウルトラマンが対峙すべき敵は、もちろんウルトラマンと呼応するように巨大でなければいけないのだが、しかしそれでは、怪獣が登場したと同時に、カタルシスとクライマックスがやってこなければならなくなる。
それでは序盤が成立しないし、起承転結も膨らまない。
そういった「クライマックスへ向けてのサスペンス描写」という点では、やがて『ウルトラマン』では「洋上から怪獣が、日本へ向かってくるサスペンス」(『大爆発五秒前』『沿岸警備命令』『オイルSOS』等々)「最初から怪獣のいる地域に、人間が舞い込む」(『バラージの青い石』『怪獣無法地帯』『宇宙船救助命令』等々)などといったルーティンを生み出して定着させていくのだが、本作品のクランクイン三本を任された飯島監督は、バルタン星人・ネロンガ・グリーンモンスの、どのキャラも、話の中盤からは姿を現すものの、物語序盤ではそれぞれが、その特性をもってして人間の住む世界に溶け込み「バランスゾーン」の影となって存在している構図を描いている。
我々が住む、この「バランスが取れた世界・バランスゾーン」の影には、もう既に、「アンバランスゾーンの使者」宇宙人・怪獣・植物が、それぞれにそれぞれの形で潜んでおり、それらが「人類の科学文明発達」という形でのテリトリー増幅によって、自分らの生存権とバッティングしてしまう。
というのが、飯島ウルトラマン初期三部作の基本構造なのである。
飯島ウルトラマンにとっては、クライマックスまでの時間は、それまでバランスゾーンに潜んでいた怪物達が巨大な姿を晒し、暴れ、そこが最初からバランスゾーンではなく、アンバランスゾーンであったことを、作品世界の人間たちへ、そして視聴者たちへ突きつけるまでの流れなのである。
さて、ここで少し話題を、本話で描写された、科特隊の愛すべき好人物・イデ隊員に移してみよう。
本話他・飯島作品で特に顕著なのが、このイデ隊員とアラシ隊員のギャグ描写であるが、特に飯島監督は本話と『侵略者を撃て』においては、イデをコメディリリーフとしてキャラ起ちさせようと奮闘した様子が伺える。
それはもう、放映後半世紀経っても愛され続ける、イデ隊員の受け止められ方を見れば、そこでの飯島監督のキャラメイクは大成功だったと明確に言えるわけだが、本話でもそのキャラは、サスペンチックで恐怖怪奇物的ムードを、上手く中和させる役割を果たしている。
飯島監督は、後に木下恵介ファミリーに属し、木下プロの社長にまでなったことでも判るとおり、人情喜劇を得意とする演出家でもあり、そこでの役者の扱いには定評がある監督なのだが、本話でのイデ隊員のキャラ描写(というか明確な演技の方向性)は、これはまさに明確に、当時一世を風靡していたクレージーキャッツの、植木等氏の影響がそこに垣間見えるのである。
特に本話において、怪奇な殺人事件の謎を追った科特隊が、オイリス島調査団の生き残り、浜口(若林映子)の元を訪れ、そこでイデが見栄をきるシーンなどでは、イデの台詞まわしや大きめでオーバーなアクションなどに、そこに無責任男・植木等の影響を強く感じ取れるのだ。
筆者は、ウルトラマニアであると同時に、日本最初のパンクバンドであるクレージーキャッツの心酔者であるから、本話のイデに植木等の影響を見てしまったのは、身贔屓ゆえかもしれないが、それでも、60年代当時に日本を席巻していた植木等の無責任男のブームと、それを送り出していた東宝のカラーを思うとき、東宝の血筋で作られていたウルトラシリーズにおいて、その作品で設定された、コメディ要員としての「イデ隊員」の中に、植木等の影響を見てしまうのは、それほど突飛ではないと思うのだ。
それほどに、当時の邦画界においては、クレージーキャッツと植木等がもたらした「現代的コメディキャラ」のインパクトは大きかった。
その原点となる『日本無責任時代』(1962年)をはじめとして、『日本一の色男』(1963年)『日本一のゴマスリ男』(1965年)などの「日本一シリーズ」や、『大冒険』(1965年)『クレージー大作戦』(1966年)『クレージー黄金作戦』(1967年)の作戦シリーズなど、クレージーキャッツ映画をメインで製作していた東宝に、社員俳優として所属していた二瓶正也氏が、イデ隊員というキャラを与えられた演技プランの中で、自社系列コメディキャラの金字塔である「植木等キャラ」を、モチーフの中に持っていたとしても、これはなんら不思議ではない。
ちなみにイデ隊員役の二瓶正也氏は、東宝所属の俳優として、1961年に岡本喜八監督・加山雄三主演の『暗黒街の弾痕』でデビュー。
この作品で二瓶氏は、後に『ウルトラマン』の『来たのは誰だ』で、怪奇植物ケロニアを演じることになる桐野洋雄氏と共に、名もない殺し屋のコンビで俳優デビューを飾っている。
その後、60年代東宝SF映画の名作『妖星ゴラス』(1962年)で円谷作品に初参加。その縁なのか、翌1963年には円谷戦記特撮作品の『青島要塞爆撃命令』にも出演。
ここで二瓶氏は、後に東宝コメディ映画の巨匠と呼ばれるようになる古澤憲吾監督と出会い、その後古澤監督がメインを担当するクレージー映画では、『日本一のホラ吹き男』(1964年)『日本一のゴマスリ男』『クレージー大作戦』などなどでバイプレイヤーぶりを発揮することになる。
この辺りの経験と、当事の東宝が持っていたカラーやイズムなどが影響した結果、イデ隊員のキャラメイクに、植木等のイメージが活かされたのではないだろうか。
後にクレージーと入れ替わるようにブームを作り上げたザ・ドリフターズなどは、明確に子ども層をターゲットにしたコメディアン・グループだったが、クレージーキャッツの時代とその映画たちは、まだまだ大人のためのギャグでありコメディであったわけで、この当事の植木等ブームに関しては、子ども達はその現象自体を脇から見守る立場に過ぎなかった。
そういう意味では、イデ隊員は「大人社会における植木等」のギャグとキャラを、巧みに、子ども向けのコンテンツの中にスピンオフした好例であり、そこからさらに、実相寺昭雄・佐々木守コンビや、メインライター金城哲夫自身が、「人間イデ隊員」を掘り下げていったときの深遠さは、やがて『故郷は地球』『まぼろしの雪山』『小さな英雄』などで発揮される。
それはある意味で、正体が知れず底知れない不可解さを蓄えて、それゆえ人気を博した「無責任男」の、子ども番組発信によるプロファイリングであったともいえるわけで、植木等の無責任男キャラが根底に隠し持っていた、ポテンシャルの高いインテリズムと繊細さは、大人になってから思い出したときのイデ隊員のメンタリズムと、全く違和感なく一致するのである。