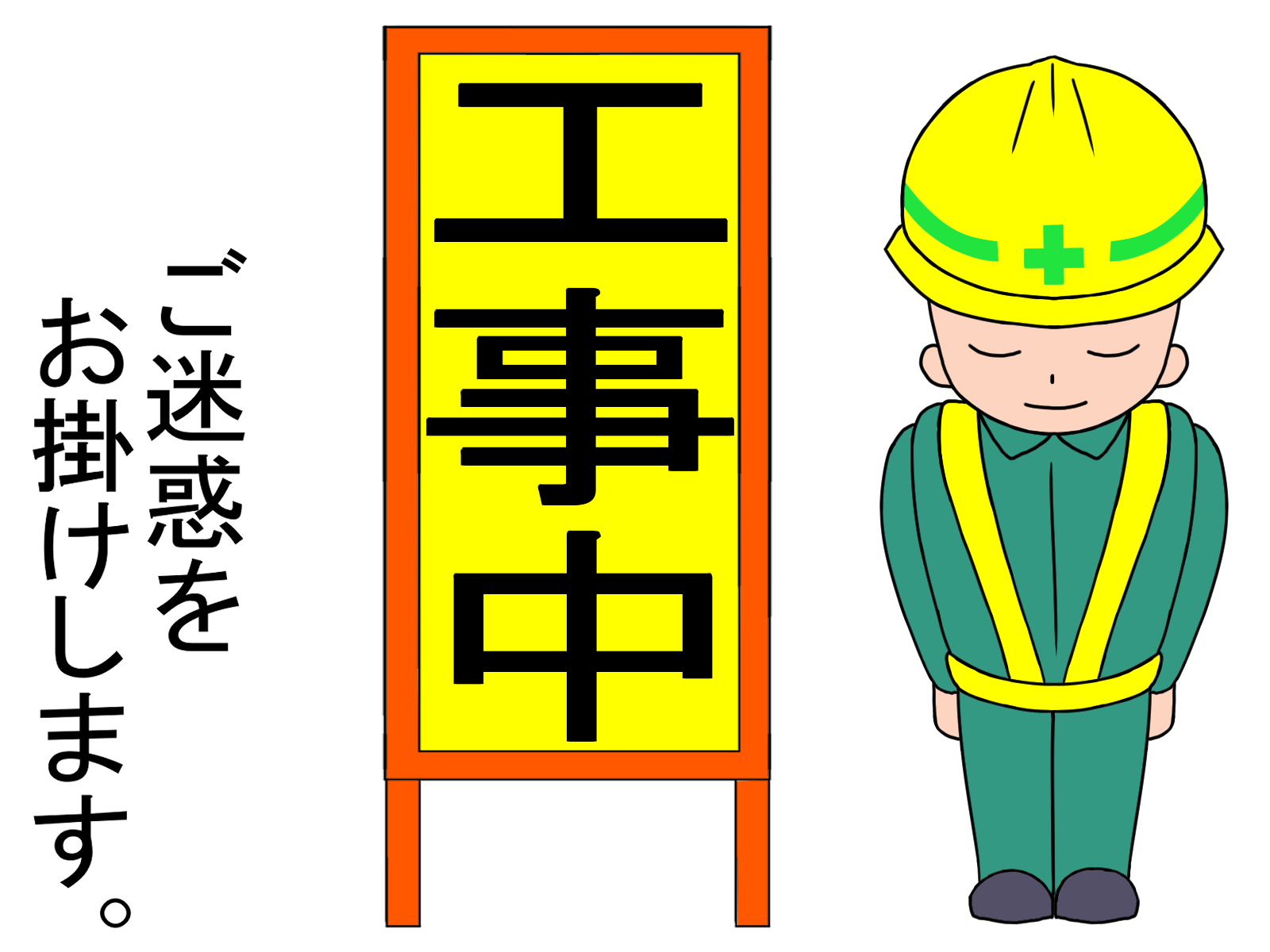例えばこの「モノトーン映画で、瞬間的に『赤』という色彩を使ってみせる」は、もちろんその始祖は黒澤明であり『天国と地獄』(1963年)のクライマックスなのだが、本作や、Steven Allan Spielbergの『シンドラーのリスト』(1993年)等は、その「意味」を上手く租借して、上質なパスティーシュとして機能し、同時にそれぞれ、自らの映画演出においても、意義と意味をしっかり醸し出していた。
(そういう「黒澤映画の『天国と地獄』への敬意とオマージュ」という意味においては、本作や『シンドラーのリスト』と『踊る大捜査線 THE MOVIE』(1998年)とでは、それこそ天と地とほどに、志も姿勢も、出来も品も違うのである。
上でも書いた「ラストの切なさ」は、筆者自身にとっては「あの80年代」という、自分自身が思春期から社会人へ移行しつつあった時代の持っていた「手放しで叫びたいことを叫べた世界感」を思い出させてくれる。
その上で、本作で押井監督がテーマに抱いていた、「透き通り澄み渡った紅」への憧憬(その意味は、劇中で天本英世演じる「立ち食いのプロ(笑)」によって語られる)。
押井守という人は、本当に「革命」に夢を見ていたのだなと、今改めてしみじみ思わされる。
そして、押井監督が夢見ていた「真の革命」とは「皮膚感覚で、情感と情念で、人と人が繋がる世界の構築」だったのだろう。
押井監督による「革命の必要条件」とはなんだったのかを、押井監督のその他の作品から窺い知ることはできる。
例えば押井ブランドを一躍有名にした、劇場用アニメ『機動警察パトレイバー the Movie』では、そこで首都を大規模テロに巻き込んで、国家を混乱させようとする天才プログラマーの帆場という男が登場して、最終的に彼の犯罪の目論見がはっきりするのだが、劇中では帆場は、自分の存在と犯罪計画を察知して、懸命に自分を追った者だけが、自分がそれまでに見つめてきた景色や、足跡を辿ることができるように、情報を誘導して残しておくような男として描かれ、その帆場の、レイバー(人型汎用機械)大量暴動テロ計画のクライマックスにおいて、自分を救おうとする人が現れた場合にのみ、未曾有の被害を回避できる可能性を残したという描写をされるが、しかし、帆場という男は劇中冒頭に自殺して、物語は全て彼の死後に展開されるという、そういった構造で、構築された作品であった。

押井作品での主人公(表層的な意味に限らず)は、いつでも「誰か」と繋がりたくて、しかし、データ越しやデバイスや情報越しといった「肉感を喪失した手段経由」でしか他人と繋がれない、リンクもシンクロも出来ないという苦悩を抱えている。
「それ」は、パトレイバーシリーズ以降「電脳」という要素を持ち込んだことで、より顕著に、分かりやすく記されることになるのだが、その前段階で本作までは特に「現実と区別がつかない夢」というガジェットが、巧みに使われていた。
そこでの逡巡や迷い、葛藤は「テーマや小道具にサイバー的な要素を、持ち込んだから」ではなく、そもそも人を取り巻き、自分が人である証明にもなる「意識」それがそもそも、非現実的な感触を、時として人にもたらすという「生理の真理」から来ていた問いかけであるゆえ、普遍性は高いのである(「そこ」は実は『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』では、主人公にダイレクトに語らせていたりもする)。
人が好き。
押井監督の作品は、実はそこへの愛で溢れているのだろう。
だからこそ、押井守は世界的にも認められ、その名も知れ渡るだけの作品を築けたのだ。
もっとも。
「この作品」に関してだけ言うのであれば、限りなく自主映画に近い、バケットと技術、企画とバックアップ体制なのだが(笑)