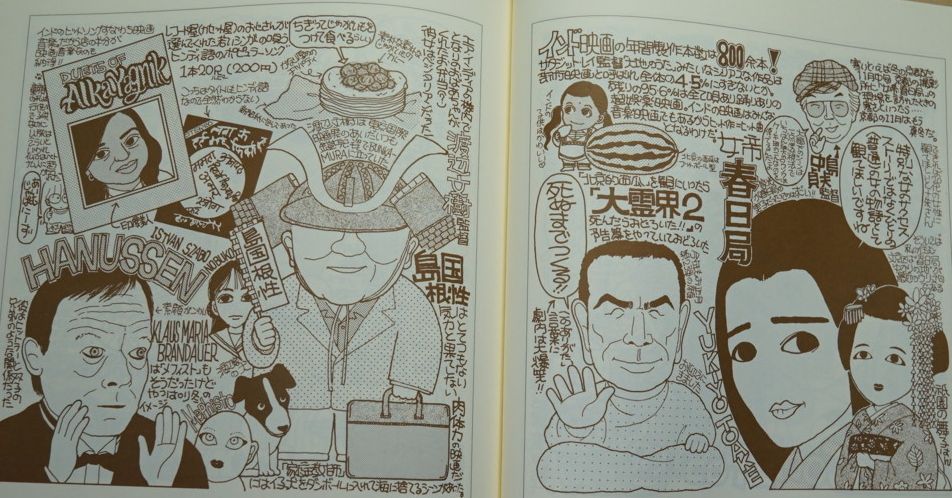というわけで、極力ネタバレを回避しつつの裏話的なアレコレなんだけど。
とりあえず、まずは大河さんとしては、今井氏の『膝枕』が金字塔たりえた「あの終わり方」が、逆に引き立つラストを用意しなければ、別編を書いた意味はなくなるだろうと、その程度はしっかり考えていた。
しかし、「作劇の道具」としての膝枕やひさ子や「男」は、あくまで今井氏の持ち物であり、子どもであり、コマであり、依り代である。おいそれと、迂闊にお借りしてどうこうできるものではない。世の中、やはり野に置け蓮華草という諺ではないが、登場人物やシチュエーションを借りた二次創作という行為は、向き不向きがあり、一次創作より二次創作が向いている人もいらっしゃるのだが、大河さんは二次創作がとことん苦手な人であり、されど今回向き合う作品のレーゾンデートルが「『膝枕』の外伝」にあるとするならば、キャラを借りるのでも、シチュを借りるのでもなく、ジャンルとして原作をきちんと踏襲した「軸をずらしたエピゴーネン」にする必要があった。
この「軸をずらした」が今回最優先要素であり、軸をずらさないのであれば、膝を胸に変えたり腕に変えたり、枕を炬燵に変えたりクッションに変えたり、無限に量産は可能ではあるのだが、どれ一つ「作ることに意味がない」物にしかならないので、例えば現状ムーブメントの産物として多数生み出されている『膝枕』の外伝の皆さんも、全て「どこで軸をずらすか」に挑んでいるというのが大前提。
そこでこの、大河流「軸ずらし」は、その手法と内容に関しては、語るほどの物じゃないので解説は割愛するが、テーマの置き場所をずらしてくれただけではなく、演ずる人の込めるテンションが描く放物線も変化させる効能がある。それでいながら、全体の構成と起承転結の転までは、『膝枕』を踏まえつつ、異なる意義を抱いた作品になる(という計算であった。当初は……)。
まず初動。「膝枕を、石(それも、パワーストーン的な)に置き換える」アイディアは、これは演じてくれたそらぺちさんの側から出た要望。というか、そういう意味ではこの作品は、そらぺちさんとのコラボに近く、今井氏のnoteにも掲載される予定がありながら言うのもなんだが、「そもそも論」でいえば、登場人物的な意味ではなく、話と設定とテーマ全体が、石好きのそらぺちさんに対する「アテガキ」であるともいえるだろう。
だからだろうか。珍しく筆者の作品ではコメディで終始せず、ある種のサイコパス的な落とし方をしたのは、ちょっとキツイが、石枕の物語を所望したそらぺちさんへの、愛をこめたアンサーであったのかもしれない。
その上で。
大河さんをよく知る人からは「またかよ。お前はそれ以外の執筆テーマをもてないのかよ」と言われそうだが「登場する女性を、如何に生々しく描くか」がメインストリーム。作劇は非日常であり、狂気であり、シェイクスピアから宮沢賢治から『半沢直樹』に至るまで、オハナシを作る、作劇をする、ということは、そこに「狂気を込める」作業が必須なわけであり、そこに狂気がある以上、それを取り巻く人間描写は、精密に生々しく正確に徹しなければ、ただの「嘘くさい嘘」になってしまうというのは、これは大河さんの信心。逆を言えば、作品の非日常と、それを受け止めているエンドユーザーの現実を、唯一繋ぐ命綱が「登場する人物が、ちゃんと生々しいこと」これに尽きると思っている。
普段はガンダムだのウルトラマンだのを論している筆者だが、そこでも出てくる問題に「性の壁」というものがある。
簡単に言ってしまえば「男性作家は、男は生々しく描けるが、女性は嘘くさくなり、女性作家は、女性を描くのは巧いが、男が虚像すぎる」というもの。
これ、生身の俳優さんが演じるドラマや映画だと気付きにくいが、アニメや漫画に置き換えると、少女漫画と萌え漫画を対比したりしてみると、まず、まぁ、この「性の壁」を越えられた作家って、人類文学史上で一桁いるか、いないかだろうなと思うわけです。
僕らの世代には伝説漫画の『うる星やつら』や『めぞん一刻』だって、ヒロインはそれぞれ生々しいのだが(男は、ちゃんと女性と付き合っていればこの真理にはすぐ気づける)、こと「諸星あたるや五代くん」とかは、嘘くさくてあり得ないとしか言いようがないのだ。
これは筆者独りよがりの思い込みではなく、同じことをアニメ版『うる星やつら』総監督(当時)だった押井守監督が「あたるにちゃんとした肉付けをしたかった」がゆえに、映画版『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』(1984年)という問題作を作ったわけだし、まぁ萌えアニメの美少女キャラなんて、いかにもな「解体新書を見ながら作ったフランケンシュタイン」だよなぁと思うわけですよ。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします