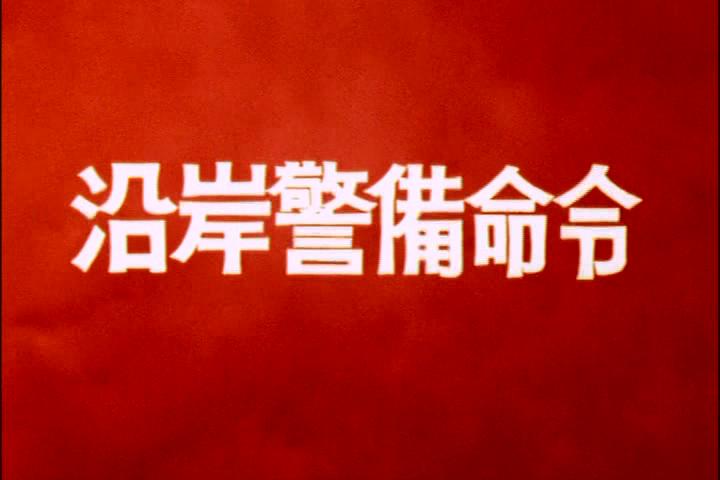やがて、時代は90年代を迎え、久住氏や泉氏が好んだ「70年代までをパロディという形で評価する」ブームも去ったが、久住氏独特の「人の、一番深くて恥ずかしい生理の部分をパロディ化する」コアは、社会と人が普遍的である以上、何かしらの「時代へのフック」さえあれば、充分新しい表現として巻き返しは可能なはずだった。
『美味しんぼ』『ミスター味っ子』等々、グルメ漫画と呼ばれる作品や、テレビのグルメリポートなどがバラエティ番組のメインで席巻したバブル期を通過し終わるころ、久住氏は「去りゆくバブル」を、自らが使い倒した「去りゆく70年代」に置き換えたガジェットとして使えるのではないかと思いついたのかもしれない。
そこで、久住氏は「新しい酒瓶に、古い酒を注いで出す」という自己プロデュースに乗り出した。
『孤独のグルメ』
漫画を担当したのは、「あえて」劇画調の泉晴紀氏とは真逆の、谷口ジロー氏。
谷口氏はもともと、関川夏央氏と組んだ『事件屋稼業』『リンド!3』や、狩撫麻礼氏と組んだ『青の戦士』『ナックルウォーズ』等「hard-boiled作家と組んだ、都会的でハードな漫画」を得意分野としていたが、その頃は、やはり関川氏原作で『坊ちゃんの時代』など、純文学的な漫画への挑戦が顕著な時期で、一言で言えば「端正で隙がなく、間抜けさとは縁遠い」作風の筆頭であった。
その、谷口氏が描く「孤独な貿易商。二枚目の中年が、ただ飯を食う」に、久住氏が原作を付けるだけで、その相乗効果は「バブル後の、失われし時代」と、究極にマッチすることを、久住氏は絶対に確信していたのではないだろうか。
実際に描かれた『孤独のグルメ』本編では、80年代の久住漫画の、トンデモなオチは一切なく、そこにはわざとらしいぐらい「hard-boiled風味な」「文学的な」ラストページが毎回描かれている。
それは、「浮浪者街に、一人無言で思いを馳せる姿」だったり、「主婦の現実に、やれやれと肩をすくませ、煙草に火をつけ苦笑いする姿」だったり、「失われた店(それも銀座)への郷愁に、肩を落とす姿」だったり、これらは絶対的に、谷口氏の画を逆算した演出でしかないのであるが、それまでの久住漫画を知らない層には、むしろ谷口氏の絵や作品傾向からもたれた偏見が(きっとそれすらも、久住氏は逆算して)、この、得も言われぬ「久住ワールド」へと、一気に読者層を引き込んだのだろう。
実は、まだまだ30年以上も昔の80年代。
筆者は一度だけ、久住氏と一緒に仕事をさせてもらったことがある。
角川書店が当時発行していた、サブカル総合雑誌『月刊バラエティ』において、久住氏はなんと「乞食(当時はまだ本当に、そう呼んでいたのだ)の恰好をして、渋谷で丸一日24時間、乞食になって体験ルポを書く」という企画。筆者は当時まだまだ、中学生でしかなかったので、本当にやったことはお手伝いとか、カメラマンさんへの差し入れとかのレベルでしかなかったのだが、その企画の最中の久住氏が、本当に心底楽しそうだったことだけは覚えている(近年になって再会した折、その話を出したら、喜んで笑っておられた)。
そんな形で「どんな事象、時代もパロディ化する」久住流なのだ。
「バブルが終わったばかりで、バブルの残り香が消えきっていない中年に、『もう、社会はバブルじゃないのだ』を突きつけるための、谷口起用のパロディ」だった『孤独のグルメ』は、ふとしたことから2012年に、松重豊氏主演で深夜ドラマ化されてから、一気に大ブレイクを始めた。
そもそも
「焼肉といったら 白い飯だろうが」
「うおォン 俺はまるで人間火力発電所だ」
「モノを食べる時はね 誰にも邪魔されず 自由で なんというか 救われてなきゃあ ダメなんだ 独りで静かで豊かで……」
等々の名台詞が、匿名掲示板等をはじめとするネット界隈では既知のネタとして通用していたというのもあり、ドラマのフォーマットとして「一人の中年紳士が、料理を注文して黙々と食べて独り言を言うだけで、特に何もドラマはない」は、大仰で陳腐なドラマよりも、リアクションが嘘くさいリポーターのテレビグルメよりも、逆によほどの、大衆のツボにはまったのだろう。ドラマはテレビ東京系の、深夜0時帯というにもかかわらず、視聴率はうなぎのぼりで、Season2は平均で3.5%を獲得。そのSeason2は東京ドラマアウォード2013において、連続ドラマ部門優秀賞を受賞。何度も高視聴率をたたき出し、追従類似ドラマ(の中には、ちゃっかり久住氏原作の他の漫画のドラマ化もあるが)も生み出し、いまやSeason6の始まりが待たれているほどだ。
これは素直に称賛すべき現状ではあるし、30年前から久住テイストを追いかけていた筆者などには、好ましい現象でもあるのだが。
この現象で、むしろ筆者の中でニュアンスでしかなかった印象論が、明確な手応えに変わったのも事実である。
辛辣な言い方に聞こえるかもしれないが、久住氏はやはり、あくまでプロデューサー気質であって、クリエイター気質ではないのだ。
要するに、久住氏はそもそも最初から、自身の作家性や表現姿勢で谷口氏と組んだのではなく、狙いとして「谷口画と内容のミスマッチ」を、上手く逆算してコンテンツをコントロールしたのだ。
それがはっきりするのは、ドラマ化されるようになってから描かれるようになった、主に単行本2巻からの内容の、路線変更に顕著だ。
それまでの主人公は、無口で、どこか遠くを見つめながら、食事だけに集中し、無言のままモノローグでだけはしゃぎ、食事を終えて現実の空間へ戻るときは、どこか空虚な目で空や街を見つめる、hard-boiled純文学という、谷口漫画の遺伝子を強く持った人間像であった。「それ」こそが、この漫画をネットの住民たちが支持した理由でもあり、称えた良さでもある。