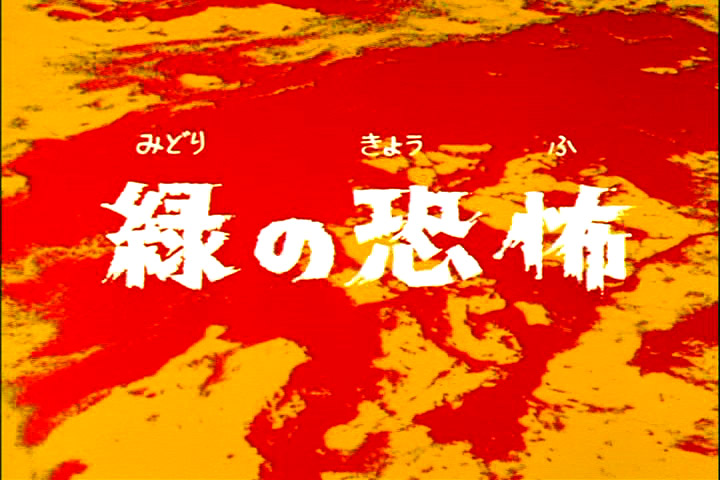本作は、1990年に、『ボクの女に手を出すな』(1986年)などで既にメジャーだった中原俊監督で映画化されて、第64回(1990年度)キネマ旬報ベスト・ワンなど、各賞を受賞した。
そこで登場する少女俳優たちは、紀子役のつみきみほ以外は、殆どオーディションで選ばれた新人であり、この映画で事実上の主演を担った中島ひろ子は、その後NHK『すずらん』(1999年)TBS『半沢直樹』(2013年)等でも重要な役をこなす、息の長い実力派のバイプレイヤー女優に成長したが、彼女がデビュー作『櫻の園』で演じたのは、敦子でも紀子でもなく、第三話『花酔い』で、それまでに登場した少女達を繋げる作劇で主役を張った、演劇部部長の由布子であった。
『花酔い』由布子
原作での由布子は、孤独で真面目な「良い子」として描かれ、他の女子と同じく、今まさに、自分の身長が実感で伸びようかという感覚の中で戸惑いながら、初恋相手だったいとこの「明ちゃん」への想いも逡巡したままに、それまで登場してきた、紀子や敦子との交流の中で、自分のコンプレックスやトラウマから逃げようとせずに、だから「今この瞬間の自分の想い」を、どこに向ければいいのかを、蒸留したようなイノセンスさで自覚する。
それは、漫画はオムニバスではあるが、時系列的には繋がっている関係上、敦子や紀子の変化を経て生まれた「奇跡」だったのかもしれないが、少女たちはそうして生きていくのだ、そうして強くなって、そうして自分を正しく愛せるようになっていくのだと、吉田女史の筆は暖かくその流れを描く。
映画版は、これを徹底した同時進行群像劇として描いたため、原作にはなかった、リアルタイム性と、既出のタレントイメージに縛られない人物像の差別化が、絶妙のバランスで作用して、過去のアイドル映画などにはなかった、その「刹那」を、原作とは全く違った形で刻み込むことに成功した佳作ではある。
だからだろう。
原作ではそれなりの、プロセスと心情変化を経た由布子の「今この瞬間の自分の想い」が、映画版だと多少唐突に、男性的な「女性は子どもであっても、理解し難い」的なとらえ方で描いてしまっているが、あくまでもドラマ性を廃し、淡々とした作劇に努めてきたクライマックスで、静かに行われた「愛の告白」だけに、そのシーンが与えた心震わせる「何か」をして、最終的に映画版『櫻の園』は、由布子がヒロインとして認知されるようになり、この作品は、原作漫画も映画版も、『櫻の園』という演劇が始まる瞬間を持ってエンディングを迎える。
「櫻の園」という言葉が持つ語感を、その散りゆく花びらを、少女一人一人の思春期の移ろう瞬間に見立てて、櫻の園たる女子高は、過去から未来までずっと、そういった瞬間を生み出していくのだという、文字通り男子禁制の真理がそこにはある。
生き物とも思えないような、萌え漫画のフランケンシュタインでもない、正義と勇気と友情に溢れた少年漫画の主人公でもない、女性であれば、誰もが通過していく「桜の下を通り過ぎる少女」達の群像劇。
この物語の最後を飾るのは、「もうあのぎこちないキスは 二度としてもらえないんだ」と、夜桜を見つめながら呟いた、敦子の姉の台詞。
「――風が最後の花を散らす頃になると
アントン・チェーホフ『櫻の園』
お互いの髪に振り散る花びらを いつもせつない気持ちで眺めた
何千回 何万回と「好き」と「嫌い」をくりかえして
感情だけが支配する場所
夫をもたない王女たちだけの国
――この桜は
私たちの頭上を飾る冠です」
中年で男性の筆者でも、「その瞬間」には跪こう。
吉田秋生女史は、大友克洋が決して描けない世界を、常に描けているからである。